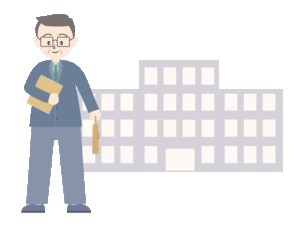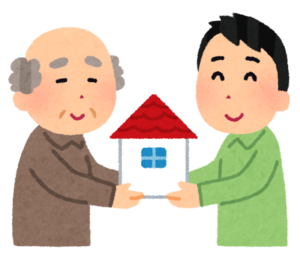今日は動産について書いていきます。まずは動産物権変動についてです。
動産の物件譲渡は引渡しがなければ第三者には対抗できません。また動産の物件譲渡は、当事者の意思表示のみによって効力を生じます。
ここでいう第三者とは、「引渡しの欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者」になります。欠缺を~お馴染みの内容ですね。要はここでの第三者とは、引渡しの不備を主張することによって、何らかの利益を得る者になります。
引渡しの方法には次の4つのパターンがあります。
①「現実の引渡し」といい、占有移転の合意と事実的支配を移転することです。A○→B●になります(ここでは○を元あった場所、●を新たに置かれる場所とします)
②「簡易の引渡し」といい、事実的支配が譲受人Bにある場合に、AB間の占有移転の合意だけでなされます。A→B○●になります
③「占有改定」といい、事実的支配を譲渡人Aに残し、Aが以降Bのために占有する旨の意思表示をすることです。A○●→Bになります
④「指図による占有移転」といい、譲渡人Aが現在動産を占有している代理人Cに対して、以降譲受人Bのために占有する旨を命じ、Bがこれを承諾した場合です。この場合は占有している代理人Cの承諾は必要ありません。Bのみの承諾があれば問題ありません。以上によって占有が移転します。次は即時取得というものについて見てみましょう。
「即時取得」とは動産を、「取引行為によって平穏にかつ公然と動産の占有を始めた者は、善意でありかつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」というものです。
たとえ取引した相手が無権利者であっても、その者を真の権利者として信頼して取引した場合には、真の権利者とは関係なくその取引は成立するというものです。動産の真の権利者からしたらたまったものではないですが、これは公信の原則と呼ばれ、取引の安全性を確保するために作られた制度です。
即時取得の成立要件として次のものが挙げられます。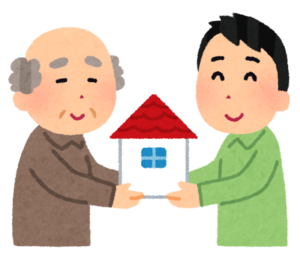
①目的物が動産であることです。不動産には登記制度があるため即時取得は成立しません
②取引相手が無権利者であることです。その者が真の権利者として信頼した場合ではなく、その者に代理権があると信頼した場合は、即時取得ではなく表見代理の方が問題となります
③有効な取引が存在していることです。相続の場合は適用されません
④取引者が、平穏・公然・善意・無過失であることです。裏を返せば、真の権利者が動産の権利を主張するためには、即時取得者の悪意有過失を証明しなければならないということになります
⑤取得者が占有を取得したこと
です。ここで問題になることは、引渡しがなされても、引渡しの方法によっては即時取得が成立しない場合が出てくることです。それは占有改定の場合です。占有改定では即時取得が成立しません。似たような場合でも、指図による占有移転の場合は成立します。
なお即時取得の特例として、取引相手が無権利者であっても、その動産が盗品または遺失物であった場合には、盗難または遺失のときから2年間に限って被害者や遺失者はその動産を取り戻すことができます。この場合には対価は必要ありません。しかし現在の動産占有者がその動産を市場を通じて善意で買い付けた場合には、その代価を弁償することが必要になってきます。
Related Posts

今日は請負契約について書いていきます。
「請負契約」とは当事者の一方がある仕事を完成することを約束し、相手方がその仕事の結果に対して報酬を支払うことを約束することによって効力を生じる契約を言います。これは有償であり、当事者双方の合意によって成立する契約になります。
請負契約においては、「請負人」は仕事を完成する義務を負います。請負の目的が物の完成である場合には、物を完成させるだけでなく目的物を引き渡す義務も負うことになります。
なお請負人は自ら労務を提供しなくても、原則自由に補助者や下請負人に仕事をさせることができます。ただし下請負人等の責に帰すべき事由についても、請負人が責任を負うことになります。
一方双務契約ですので注文者にも義務は発生し、完成した仕事に同時に報酬を支払わなくてはなりません。同時履行の抗弁権については先に記事にしましたが、ここでいう同時履行とは目的物の完成ではなく目的物の引渡しになりますので、目的物の引渡しと同時に支払い義務が発生します。
引渡しが請負業務の完了となると、作成中あるいは完成した目的物の引渡しまでの所有権はどうなるのでしょうか。
民法にそれについての規定はありませんが、その所有権は判例から、材料の供給者が請負人である場合は、その所有権は引き渡すまでは請負人にあり、材料の供給者が注文者である場合には所有権は注文者にあるとされています。
では次に、請負人の「瑕疵担保責任」について見ていきましょう。
仕事の目的物に瑕疵があった場合は、注文者は請負人に対して「瑕疵の修補」を請求することができます。売買の際の瑕疵担保責任については「隠れた瑕疵」であることが要件とされましたが、請負については「隠れた瑕疵」でなくても請求することができます。
ただし目的物の瑕疵が重要なものではなく、かつ修補にかかる費用がそれ以上に掛かる場合には、注文者は修補を請求することはできず、それに代えて損害賠償を請求することになります。
前記の重要でない瑕疵以外の場合は、注文者は瑕疵の修補に代えて、またはその修補とともに損害賠償を請求することができます。請負人が損害賠償に応じない場合は、それが支払われるまで未払い報酬の支払いを拒絶することができます。
また注文者の損害賠償請求権と請負人の報酬債権を相殺することもでき、請負人から瑕疵修補に代わる損害賠償を受けるまでは、その報酬全体の支払いを拒むこともできます。
目的物の瑕疵が重大であって契約の目的自体を果たすことができない場合は、注文者は契約の解除をすることができます。ただしこの場合でも建物等の土地の工作物については、額が非常に大きくなるため解除することはできません。
以上の瑕疵担保責任について、請求できる期間は原則引渡しから1年です。しかし土地工作物の場合は5年、堅固な工作物については10年になります。
最後に請負契約の終了について見ていきましょう。請負契約の終了は、法定解除や約定解除の他に次のような終了原因があります。
①仕事未完成の間における注文者の解除権
②注文者の破産による解除権
です。
①については、注文者は仕事が完成するまでは、「いつでも」損害を賠償して契約を解除することができます。完成した部分について利益があるときは、未完成部分のみ契約解除をすることもできます。
②について、注文者が破産手続開始の決定を受けた時点で、請負人または破産管財人が契約を解除することができます。
READ MORE

今日は時効について書いてみます。時効というと刑事ドラマなどでよく耳にする言葉ですが、法律では「ある一定の事実状態が一定の期間継続した場合に、その事実の法律上の根拠に合致するかどうかを問わずに、その事実状態を尊重して権利を認める」制度を言います。
時間の経過で証拠能力が希薄になる一方、その事実が継続している場合はそれ自体が重いということを尊重して制定された条項です。
では民法における「時効」について見てみましょう。時効完成の要件は、一定の事実状態が一定の期間継続することです。また時効が完成しその利益を得るためには、その意思表示をしなくてはなりません。「時効の援用(えんよう)」と呼ばれるものです。
時効の援用は時効の利益を受ける旨の意思表示であり、援用して時効の利益を受けるかどうかは個人の意思になります。時効を放棄することもできますが、時効が完成する前にあらかじめ放棄を行うことはできません。時効が完成してから放棄することになります。また放棄ではありませんが、時効が完成してもそれを知らずに債務を承認してしまった場合などは、もう援用をすることはできません。
時効の利益を受ける者は援用権者である当事者に限られますが、判例ではその者を「時効に因り直接に利益を受くべき者」としています。時効の効果は遡及効といって、最初の起算点にさかのぼって効果を発生することになります。
民事上の時効には一定の期間を経ることによって権利を取得する「取得時効」と、一定の期間を経ることによって権利を失う「消滅時効」があります。ではまず取得時効から見てみましょう。
「取得時効」とは、物の占有の継続に対して真実の権利を認める制度になります。他人の物であっても一定の期間占有をしていれば、その事実を尊重して権利が移転するという制度です。取得時効の要件は次の5つになります。
①「他人の物」を占有していること(場合によっては自分の物でも可とした判例もあります)
②所有の意思を持って占有していること(自主占有といいます)
③平穏かつ公然と占有していること
④一定期間占有を継続していること
⑤時効援用の意思表示がされること
になります。なお④の期間は、条件によって変わってきます。その物(不動産も含みます)の占有を開始した時に善意無過失であった場合は10年です。善意無過失でない場合(悪意または有過失)は20年になります。
善意無過失の判定はあくまでも最初の占有者が占有を開始した時点が起算点になりますので、前の占有者から占有を引き継いだ場合も(占有の事実が重要となりますので、占有する者が変わっても問題ありません)、引き継いだ時の善意無過失が問題になるわけではありません。最初の占有者が善意無過失であれば、取得時効の条件は10年になります。
なお②③の所有の意思についてですが、これは「占有者は所有の意志をもって、善意で、平穏にかつ公然と占有をするものと推定する」(占有の推定)とされています。ですので占有の事実があれば、所有の意思は推定されるものとされています。
時効取得の対象は、「所有権」と「所有権以外の財産権」になります。所有権以外とは、地上権・永小作権・地役権などです。一般債権の時効取得はできませんが、不動産における賃貸借権は例外として、要件が揃えば時効取得できます。
では次にもうひとつの「消滅時効」について見てみましょう。消滅時効とは、一定期間の経過によって債権などの権利が消滅してしまう制度を言います。消滅時効の要件としては次の4つがあります。
①権利不行使が一定期間継続すること
②法定中断のないこと
③時効援用の意思表示をすること
です。①の期間については、債権については10年で消滅し、債権または所有権以外の財産権は20年で消滅します。商法などに規定されている商事債権などの場合はより短い期間で消滅します。なお所有権については取得時効の対象とはなりますが、消滅時効の対象にはなりません。
時効については「中断」という制度も設けられています。時効が継続している場合であっても、
①請求
②差し押さえ、仮差し押さえ、仮処分
③承認(債権者に権利があることを認めること)
によって時効の進行が止まり、そこが起算点となってまた時効の進行が始まります。中断の効力は基本的には当事者およびその承継人に対してのみ生じますが、保証人や物上保証人に生じる場合もあります。
中断自由の請求については裁判上で行ないます。もしそこで却下や取り下げがあった場合は、中断の効力は失われます。なお裁判外で行う場合は「催告」と呼ばれ内容証明郵便等でされますが、その場合の効力は時効を停止させるにとどまり、中断の効果を得るためにはそこから6ヶ月以内に裁判上の請求を行う必要があります。消滅時効に関しては2020年施行の改正民法で見直しがなされていますので、確認ください。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category8/category10/entry36.html
https://kouseishousho-gunma.com/category7/entry18.html
READ MORE
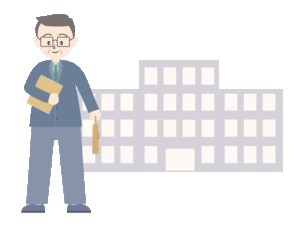
今回は債権者代位権というものについて書いていきます。
「債権者代位権」とは、債務者が何らかの理由によって自分の権利を行使しない場合に、債権者が自分の債権分を守るために債務者に代って行使できる権利をいいます。自分の債権分を守るということを別の言葉で言うと、債務者の「責任財産」を保全するということなります。
「責任財産」とは強制執行の際に引当となる財産のことであり、債務者が弁済することができない時に、あてにされる財産を言います。
債権者代位権を行使できるための要件は次のとおりです。
①債権の保全のために必要であること
②債務者自身がその権利を行使していないこと
③保全される財産が原則として金銭債権であること
④保全される財産が弁済期にあること
⑤債務者の権利が一身専属的な権利でないこと
になります。
①の場合は債権者が代位権を行使しないと、債務者が無資力状態に陥る恐れがあることが条件となります。無資力になると弁済が不可能になるので、責任財産を保全する必要がある、ということになります。なお債務が金銭債務ではなく特定債権だった場合は、無資力状態でなくても代位権を行使できます。その債権がなくなってしまえば、資力の状況にかかわらず困ってしまうからです。
②の場合にも制限があります。あくまでも債務者自身がその権利を行使しないことが要件であって、自ら行使した場合にはその行使した内容が債権者に不利益なものであっても、債権者はそれを押しのけて代位権を行使することはできません。
③については金銭債権が原則になりますが、金銭債権以外でも「代位権の転用」の場合には認められる場合があります。「代位権の転用」とは、金銭債権以外の債権でも代位権を行使する必要がある場合が出てくるため、これを拡張して適用させる概念です。
例を挙げると、建物を不法に占拠する第三者がいた場合に、建物の賃貸人が不法占拠者を除く等の手立てを講じない場合です。この場合は建物の賃借人が代位権を行使することができ、賃借権を保全するために賃貸人たる所有者に代位して、建物を不法に占拠する第三者に対しその明渡を請求することができます。その場合は直接自己に対して明け渡すべきことを求めることができます。
④については、弁済期前の例外として裁判上の代位や保存行為があり、この場合は債権者代位権を行使することができます。
では債権者代位権の行使はどのように行われるのでしょうか。
これは裁判上だけでなく、裁判外でも行使できます。また債権者はあくまでも「自己の名」において権利を行使するものであり、債務者の代理人としてするものではないことを確認ください。
そして代位権を行使できる範囲も、債権者の債権額の範囲に限定されます。債権者代位権を行使した場合の効果は直接「債務者に帰属」することとなり、債権者が複数いる場合は全債権者の共同担保となります。
なお債権者が代位権を行使してこれを債務者に通知すれば、以降債務者はこれを妨げることはできません。また債権の目的物が金銭であっても動産であっても、債務者への引渡しだけでなく、債権者への直接引渡しを請求することもできます。これは債務者への引渡しを請求した場合に、債務者が受け取り拒否やをしたり、その財産を消費してしまうことが考えられるからです。
ただし債務者の受領がなくても行えるもの(債務者でなくても行える登記移転等)については、直接債権者に引き渡す請求は行えません。
READ MORE

今日は婚姻の無効や解消について書いていきます。
まず婚姻の解消についてです。「婚姻の解消」理由には、
①離婚
②死亡・失踪宣告による解消
があります。
「離婚」については「協議上の離婚」と「裁判上の離婚」がありますが、まず協議上の離婚について見てみましょう。
「協議上の離婚」とは、夫婦お互いの協議によって成立する離婚になります。この場合には夫婦ともに離婚する意思があること(離婚意思の合致)と、離婚の届出を行うことが必要とされています。なお判例ではこの離婚意思の合致について、離婚そのものをする意思は必要とせず、届出をする意思のみで足りるとしています。
また離婚の際に未成年の子がいる場合は、必ず一方を「親権者」にしなければなりません。
離婚そのものをする意思であれ、届出をする意思のみであれ、それらを含む離婚意思のない者の離婚は当然に無効となります。「意思のない離婚」とは、詐欺または強迫によって協議離婚がなされる場合であり、この場合は取り消しを請求することができます。この取消権は、詐欺を見つけた時または強迫から免れた時点から3ヶ月で消滅します。また追認によっても消滅することになります。
協議上の離婚が成立しなかった場合は「裁判上の離婚」になります。離婚の場合は原則、訴訟を起こす前に家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚が成立しない場合に裁判上の離婚に向かいます。
離婚の訴えを提起する場合には、次の理由が必要になります。
①配偶者の不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
です。
裁判所はそれらの事情を考慮して、離婚の訴えを認めるか棄却します。なお②の悪意の遺棄とは、理由もないのに同居を拒んだり家計費を差し入れないなど、積極的な意思で夫婦関係を行わないことを言います。
以上、協議上であれ裁判上であれ、離婚が成立した場合には次の効果がもたらされます。
①身分上の効果
②子の処遇
③財産上の効果
です。
「身分上の効果」により、婚姻関係とそれに伴う姻族関係が消滅します。また姓(氏)を改めた者については、「婚氏続称の届出」をしない場合は、結婚前の姓に戻ります。
「子の処遇」についてはまず、その子の嫡出子たる身分には影響は及ぼしません。また未成年の子の場合は親権者が決められます。
「財産上の効果」としては、一方が他方に財産分与を請求することができます。その額や方法は当事者の協議によりますが、協議が成立しない場合は離婚から2年以内であれば家庭裁判所にも処分を請求できます。
次は婚姻の無効と取り消しについて見てみましょう。無効と取り消しはその効果や影響が異なりますので、婚姻の瑕疵の程度に応じて規定がなされています。
まず、より影響の大きい無効について見てみましょう。
「無効」とされた場合は、婚姻が最初から無効であるとされ、夫婦としての効果は何ら生じません。婚姻の無効は、次の場合に限りなされます。
①婚姻意思を欠く場合
②届出を欠く場合
です。
無効は請求がなされて成立しますが、無効を請求することができる者は当事者だけでなく、利害関係者は誰でも主張することができます。これは当事者が死亡していても主張することができます。
次の「取り消し」ですが、これは無効よりも限定的な効果であり、取り消しの効果は婚姻成立時までは遡及しません。取り消しまでの期間は婚姻が有効とされ、その期間は財産分与などの財産関係も適用されます。
婚姻の取り消しを請求できる者は、当事者およびその親族、また検察官になります。
無効は当事者の死亡後も請求できますが、取り消しでは当事者の死亡後の請求は当事者や親族のみが行え、検察官は請求をすることはできません。また重婚違反の場合は当事者の配偶者および前配偶者も請求できます。これも失踪宣告の記事で確認ください。
再婚禁止期間の違反については親子関係の証明も関わりますので、前夫についても取り消しを請求することができます。詐欺・強迫の場合は当事者のみの請求となります。
READ MORE

今日は共有について見てみます。
これも相続分野で頻出する言葉となりますが、「共有」とは、数人の者が共同所有の割合である「持分」を併せて1つの物を所有することを言います。単純に言えば、数人で1つの物を所有することですね。
「持分」とは今述べたように、共有物に対する所有権の割合のことです。持分の割合はそれぞれの意思表示や法律の規定(法定相続分等)により決まりますが、その割合が不明な場合は各共有者平等の持分であると推定されることになります。
持分は各共有者が原則自由に処分できます。共有目的物の利用については各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。
例えば1台の自動車を3人で共有しているとしますと、3人それぞれがその自動車を自由に使用することができます。しかし異なる目的を同時に行うことはできませんので、必要な場合は各自の持分に応じた使用時間配分を決められるということです。自動車を購入するのにAさんがその代金50%、BさんとCさんが25%を出資していたとすると、その割合で使用時間を決められるということになります。
相続に当てはめると、配偶者と子供が2人いる場合は配偶者が50%の持分であり、2人の子供はそれぞれ25%ずつの持分ということになりますね。
また持分は、使用する共有者の1人がその持分を放棄した場合や、共有者が死亡した際に相続人がいない場合はその持分は他の者に帰属することとなります。
共有物には日々の利用についても制約がありますので、それらについても見ていきましょう。
共有物の利用については、その内容や利用状況から次の3つに区分されています。
①保存行為
②管理行為
③変更行為
になります。「保存行為」とは修理や修繕など、共有物の現状を維持する行為であり、各自が単独で行うことができます。なお現状維持という観点からの妨害排除請求や消滅時効の中断なども共同で行われる必要はなく、各自が単独で行うことができます。
次の「管理行為」とは、共有物の性質を変えることなく利用したり改良する行為とされています。これには共有物の賃貸やそれに関する解除や取り消し行為などがありますが、この場合は単独で行うことはできず、共有の過半数の合意が必要になります。
過半数とは人数が基準になるものではなく、持分の価格を基準にしての過半数になります。Aが10でBが20の持分価格を有していても、Cが50を有する場合には必ずCの承諾が必要になります。
「変更行為」とは共有物の性質や形状を変更することを言います。具体的には共有物を売却したりその全部に抵当権等を設定する場合がこれに当たりますが、この場合は共有者全員の同意が必要になります。
最後に「共有物の分割」について見てみましょう。共有物については、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができます。分割の方法は現物分割、代金分割、価格賠償の3つがあります。
ここでの「現物分割」とは現物そのものを分割すること、「代金分割」とは共有物を売却してその代金を分割する方法です。「価格賠償」とは共有物を分割した際に持分に満たない者に、超過した者からその金額を補填することを言います。
共有分割の協議が整わない場合は遺産分割協議同様、裁判所に分割を請求することになります。なお遺言書による場合が多いですが、共有物を5年を超えない期間で分割を禁止する特約を付けることもできます。
READ MORE

今日は同時履行の抗弁権というものについて書いていきます。
契約の種類についてはいくつかありますが、ここでは2つの種類についてみてみます。ひとつ目はその契約が有償で行われるか、それとも無償でなされる契約かということです。契約の当事者同士が互いに経済的価値を得るものが「有償契約」であり、そうでないものが「無償契約」になります。
ふたつ目は、契約の当事者同士が互いに対価的な関係にある債務を負担する契約であるか、そういう性質を有しない契約であるかということで区分されるものです。前者を「双務契約」、後者を「片務契約」と言います。
双務契約というものは必ず有償契約の性質を持ちます。一方逆に、有償契約だからと言っても必ずしも双務契約とは限りません。消費貸借(お金を貸す場合など)は、一方が他方にする契約になりますので片務契約になります。ここで利息を付けない場合は無償契約になりますし、利息を付ける場合は有償契約になるからです。
前フリはそこまでにして本題の同時履行の抗弁権について見てみましょう。
「同時履行の抗弁権」とは、この「双務契約」における当事者の一方が、相手方が債務の履行を提供するまで、自分の債務の履行を拒絶することが出来る権利のことを言います。
たった今Aの代金を請求されても、Aという商品を配達してくれるまではその代金は支払いません、というようなことがこれに当たります。逆にAを配達したが支払いをしてくれない。代金を支払ってくれなければAは渡せませんという場合も同様になります。双務契約ですのでこの契約は当然有償契約ということになります。
同時履行の抗弁権は、次の内容を満たすことによって成立します。
①1つの双務契約から生じた対立する債務が存在していること
②双方の債務がともに弁済期にあること
③相手方が自己の債務の履行またはその提供をしないで、他方の債務の履行を請求したこと
です。
②の弁済期については、それぞれの債務の弁済期がどちらが先であっても後であっても問題はありませんので、同時期に弁済期が到来するものである必要はありません。
同時履行の抗弁権を有している者は、履行期日を経過しても違法性はなく、履行遅滞の責任は負いません。
これが訴訟になった場合についてですが、当事者の一方が債務の履行を請求し相手方が同時履行の抗弁権を主張した時は、双方の主張が堂々巡りになってしまいますので、裁判所からは、債務の履行を請求した側が債務の履行をし、それと引き換えに請求された側に履行を命じる、という「引換給付判決」がなされることとなります。
先に相殺の項で書いたように、同時履行の抗弁権が付着した債権を自働債権として相殺することはできないため、このような判決をすることになります。
READ MORE

今日は認知について書いていきます。認知は相続にも関係してくる分野になります。
配偶者を除き、相続人の第一順位は子になります。だんなさんが亡くなられていざ相続だという場合に、奥様と同居している成人のお子さんが3人いた場合には、通常はこの4人が相続人ということで相続の手続きを済ませることでしょう。
しかし相続を終えた後に、認知された非嫡出子が現れ、相続がやり直しになる場合があります。「嫡出子」とは法律上婚姻している夫婦間に生まれた子供を言い、「非嫡出子」とは法律上婚姻関係にない者の間で生まれた子になります。
この非嫡出子ですが、相続に際しては関わりを持ってくる場合があります。お子様たちとは血縁関係があることでしょうが、相続においては認知されているかいないかが重要な意味を持ってきます。認知されていなければ相続に関わりをもちませんが、「認知された非嫡出子」の場合は、相続権のある子になります。
「認知された非嫡出子」も他の子と同等の立場になりますので、遺言書のない相続の場合には、必ず戸籍をたどって相続関係を明らかにしておくことが重要になります。
では認知について見ていきましょう。前述した通り、「非嫡出子」とは婚姻関係にない男女間に生まれた子(婚外子)を言います。法的には婚姻関係にない内縁の妻との間に生まれた子も、家族が知らないいわゆる愛人との間に生まれた子もともに「非嫡出子」となります。
通常の婚姻関係にある男女間に生まれた子は「嫡出子」と言います。「非嫡出子」はその親との間に法律上の親子関係はありませんが、「認知」されると法律上の親子関係が生じます。
「認知」とは、非嫡出子の親が、その非嫡出子を自分の子として認める行為を言います。認知は生前に行うこともできますし、遺言で行うことも認められています(遺言認知)。また認知とは通常は父子関係における行為であり、母子関係においては分娩の事実により親子関係が当然に発生しますので、認知は不要になります。
認知により認知された非嫡出子は、父親との相続関係が認められることになります。法的に血族関係が認められ法定相続人になります。
たまにドラマなどで、愛人との間に生まれた子を、子供のない自分たちの実の子、非嫡出子として届け出るストーリーがあります。この場合はどうなるのでしょうか。
養子以外の子には血縁関係が必要となりますので、血縁関係のない戸籍上の妻の嫡出子となることはありません。不正の届出となり、事実が判明すれば嫡出子であることは否定されます。ただし判例からは「認知」の効果が認められ、認知された非嫡出子となります。
認知について話を戻します。「認知」には次のものがあります。
①任意認知
②強制認知
です。
では「任意認知」とはどのようなものを言うのでしょうか。
「任意認知」とは、父が自ら役所に「認知届」を提出して行う方法になり、遺言による方法も認められます。また認知は身分行為になりますので、未成年者や成年被後見人であっても、法定代理人の同意なしにすることができます。
なお任意認知は自らの意思ですることが必要になりますので、認知者の意思に基づかない認知届けは無効になります。
認知には次の例外を除き、子の承諾は不要です。認知に子の承諾を必要とする場合は次のとおりです。
①成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要になります
②胎児を認知する場合は、その母親の承諾が必要になります
③成年者の直系卑属(孫等)がいる、死亡した子を認知する場合は、その成年である直系卑属の承諾が必要になります
「強制認知」とは、父または母が認知をしないときに、その子や直系卑属が裁判により求めるものになります。ただしこれは父または母の死亡から3年以内にする必要があります。
任意認知も強制認知も、その効果は子の出生時にさかのぼって親子関係が生じます。この際も、第三者が既に何らかの権利を取得している場合には、その権利を害することはできません。
最後に「準正」について付け加えておきます。
「準正」とは、非嫡出子を嫡出子にする制度を言います。準正の要件は、「認知」+「婚姻」になります。認知により相続権が発生しますが、あくまでも「認知された非嫡出子」であることには変わりありません。これを嫡出子に変える制度になります。
「準正」には認知と婚姻の順序によって2つのパターンがあります。
①婚姻準正
②認知準正
です。
「婚姻準正」とは、認知が確定した後に父母が婚姻した場合で、婚姻の時から準正が発生します。
「認知準正」は婚姻をした父母が認知をした場合で、認知の時から準正が生じます(この場合も実務上は婚姻の時からとされています)。
順番はどちらであっても、準正が生じた子(準正子)は、嫡出子の身分を取得します。なお現在の民法では、相続においても嫡出子と認知された非嫡出子の相続分は変わりませんが、改正前は差がありましたので、この準正の手続きはより重要なものでした。
READ MORE

今日は民法の意思表示について書いていきます。
法律用語の場合、前回の善意・悪意のように独特の表現や意味が使われています。その説明においても独特の微妙な解釈の出来る言い回しがされる場合が多いです。心理留保を「うそ」というように噛み砕いて平易な言葉で説明される場合もありますが、それだとかえって範囲が狭まってしまう場合もありますので、基本的には遠まわしでも回りくどい言い方を使っていきます。
私も行政書士のホームページで主要業務の説明をしていますが、例えば建設業許可など建設業法という法律で決まっていることなので、文として読みやすくこそすれ基本的には表現をあまりいじることなく書いています。グーグル対策なのか個性を出すためかわかりませんが、無理に表現をこねくり回しているものも多く見られますが、そこに意味を見い出せませんでしたのでそういう体裁で作りました。グーグル対策的には良くないことなのかな?まあよいので、話を続けます。
意思表示とは一定の法律効果を期待して、意思を外部に表示する行為のことです。意思表示は、
①効果意思
②表示意思
③表示行為
という段階を経ますが、③の表示行為がなされても、①②の意思を欠く場合には、意思表示があったとはいえないとされています。これを意思主義と言いますが、ここでの効果意思とは、一定の効果の発生を期待してする意思のことであり、表示意思とは意思表示のことでもありますが、効果意思を表示しようとする意思のことです。表示行為はそれらの行為を行うことです。
意思主義では単に行為を行っただけでは意思表示とは言えず、期待する効果が存在しており、またそれを表に出したいという意思がないと意思表示には当たらないということです。
民法を含む私法には、
①権利能力平等の原則
②私的所有権絶対の原則
③私的自治の原則
という3大原則があり、私的自治の原則からは意思主義が望ましいとされています。
効果意思を欠く場合を意思の不存在といい、効果意思を作る状況に瑕疵がある場合を瑕疵ある意思表示といいます。ちなみに「瑕疵」もよく使われる言葉ですが、これは本来備わっているものが備わっていない状況をいう概念です。単純に言えば「きず」のことですかね。
先ほどの効果意思を欠く場合を意思の欠缺(けんけつ)といいます。欠缺とは、ある要件が欠けていることを言います。
意思主義の対義語に表示主義がありますが、発信する側から見た場合には意思主義が有効とされますが、商売などにおいて相手方は表示をのみを見て判断するする場合が多くなります。その場合には効果意思や表示意思は推測でしかありませんので、相手方を保護するという立場から、表示そのものを重視する表示主義も認められています。
ではこれらの意思表示の中でも、法律で無効とされたり取り消されたりする意思表示について見ていきましょう。これらには、
①心理留保
②通謀虚偽表示
③錯誤
④詐欺
⑤脅迫
の5つがあります。心理留保は相手方を保護する表示主義に基づいたものであり、他の4つは意思主義の意思の欠缺によるものとなります。
まず「心理留保」とは、表意者が表示行為に対応する真意のないことを知りながらする単独の意思表示のことです。平たく言えば冒頭の「うそ」のようなものです。表示主義に基づいていますのでその意思表示は有効となります。効果意思や表示意思がなくとも成立します。相手方を保護するものですね。
しかしこれはあくまでも相手方が善意であった場合に限られ、相手方が表意者の真意でないことを知っていた場合や知ることの出来た場合、いわゆる悪意の場合はその意思表示は無効になります。保護される必要がないということになります。
次の「通謀虚偽表示」とは複数の者が、相手方と通謀してする真意でない意思表示のことです。通謀とは、あらかじめ申し合わせて企むことです。これが成立する要件は、
①意思表示が存在すること
②表示と具体的に期待する法律効果が不一致であること
③真意と異なる表示をすることについて、相手方と通謀している
ということです。当事者間では保護されるべきものではありませんので、無効となります。
ここに関与してくる第三者に関してですが、表示後に登場した第三者には対抗できません。「第三者」というのは「当事者および包括承継人以外のもので、虚偽表示の外形を基礎として新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者」を言います。めんどくさい表現ですが、法律できちんと定義されているんだから仕方がありません。これは覚えどころで、私も記述の試験対策で覚えました。新たに云々の前には、それぞれの法律の場面に関与してくる第三者の状況が入ってくることになります。
行政書士の勉強は合格基本書と過去問があれば独学でも問題ないと思いますが(私もそうでしたが)、自分でノート(バインダー式)を作ることと、記述式の想定問題集(私はLECのものを買いましたが、試験に出るまで何年でも使えますよ)は買ったほうが良いと思います。バインダー式であれば、別の参考書からの違う観点を追記したりできますし。
READ MORE

今日は弁済というものについて書いていきます。
弁済とは、債務の本旨に従って、債務の内容である一定の給付を実現する行為のことです。単純に言えば、借りたものを返すということになります。この弁済という行為は、債権の目的が達成されたという事実によって債権を消滅させる行為ですので、法律行為には当たりません。
以前別の記事で法律行為の意思主義について書きましたが、債務の給付者が自分の意思表示の効果として債権を消滅させるものではないので、法律行為に準拠する準法律行為に当たります。言い換えると準法律行為とは、意思表示によらないで法律上の効果を発生できる行為のことを言います。
https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/826
弁済とは実際に給付が実現されて達成されるものですが、民法では実際に債務者がそのもの自体を弁済しなくても、給付を実現するために必要な準備を行い、債権者側に協力を求めることによって法律上の効果を発生させることができます。これを「弁済の提供」と言います。
弁済の準備ができあとは弁済を実現するばかりとなっても、債権者側の都合や諸事情によって実際の弁済に至らないケースがあります。債務の履行については不履行責任が発生する場合もありますので、現実の弁済と区別して、弁済の提供という規定が設けられています。
弁済の提供は、債務の本旨に従って、現実または「口頭の提供」というものによって行われます。今述べたように、債務者は弁済の提供による法律効果によって、損害賠償や契約解除、遅延利息の支払いといったような債務不履行責任から免れることになります。
では弁済の提供について続けて見ていきましょう。
まず弁済の提供の方法ですが、今述べたとおりこれには「現実の提供」と「口頭の提供」という2つの方法があります。弁済の提供ではまずは原則として、現実の提供をしなければなりません。
現実の提供とは実際に弁済が完了するであろう状態であり、債務者が債権を消滅させるためにできる限りのことを行い、債権者側が受領などの協力をすれば弁済が完了するというような状況を言います。
これに対し「口頭の提供」とは、
①債権者があらかじめ受領を拒んでいる場合
②債務の履行についての登記など、債権者の行為を必要とする場合
に認められます。
口頭の提供とは、債務者が債権者に口頭で行うものですが、これは、債務者が現実の提供をするのに必要な準備をしたことを債権者に通知し、受領を催告することで足りることとされています。
なお判例からは、債権者が契約自体を否定するなどして、弁済を受領しない意思が明確と認められる場合には、債務者は口頭の提供さえもしなくても、債務不履行責任から免れることとされています。
また物を引渡して給付を行う場合ですが、目的物が特定物である場合には現状のまま引き渡せば足りることとなりますが、不特定物の場合には瑕疵のない物を調達して引き渡さなくてはなりません。
READ MORE

今日は民法の中の物権変動というものについて書いてみます。
物権とは先日の記事に書きましたが、民法では債権並ぶ財産権です。「物」を支配する排他的な権利であり、代表的なものには所有権があります。
物権は先に対抗要件を具備したものが優先となります。また物権は債権に優先しますが、例外として対抗要件を備えた不動産賃借権は物権と同様の扱いになります。
物権には占有権が発生しますので、占有を阻害された場合にはこれを取り除く権利が発生します。これを物権的請求権と言いますが、具体的には次の3つがあります。
①返還請求権であり、占有回収の訴えにより目的物の返還を請求するもの
②妨害排除請求権であり、占有保持の訴えにより妨害の除去や妨害行為の禁止等を求めるもの
③妨害予防請求権であり、占有保全の訴えにより将来の妨害の原因を除去して未然に防ぐもの
です。物権変動とは、物権の発生や変更、消滅のことを言います。変動の原因は当事者の意思表示のみによるものであり、 契約等は必要ありません。また時効や相続によっても変動します。
変動の時期は当事者双方の意思表示が合致した時点であり、その時点をもって権利が移転します。
物には特定物(NO999のこの車)と不特定物(お店にあるレクサス)がありますが、特定物の売買における変動の時期は、特約がなければ契約と同時に所有権が移転し、特約があれば特約で定めた時期に移転します。不特定物の売買における変動の時期は、目的物が特定したときになります。
では次に不動産物件の変動を見てみましょう。不動産は物権変動をしても、登記がなければ第三者には対抗できません。登記とは不動産における公示のことです。公示とはそれをすることによって、その事実を公衆一般に知らしめることです。ですので不動産登記制度は、その土地の所有者や債権者を公にする制度になります。
不動産の所有権を主張するものが複数いる場合では(二重譲渡の場合等)、その優劣は登記の先後によります。不動産は登記を行わないと、完全に排他性のある物件を取得できないことになります。ここでこの不動産の物権変動の条項に出てくる用語について触れておきます。
まず「第三者」とは、これは本試験においても重要な事項ですが、「当事者もしくはその包括承継人以外の者で、登記の欠缺(けんけつ)を主張するにつき正当な利益を有する者」のことです。この場合の第三者には単純悪意者は含みますが、背信的悪意者は除外されます。
「背信的悪意者」とは物権変動の事実を知っており、かつ登記を備えていない者に対してその不存在を主張することが信義に反する者のことです。具体的な例としては、AさんがB土地を最初に購入しかつ未登記であった場合に、それをネタにAさんに高値で売る目的でB土地を二重に購入したCさんがこれに当たります、この者に対しては登記なくして対抗できます。
READ MORE