民法 寄託契約について
今日は寄託契約というものについて書いていきます。
「寄託」とは、当事者の一方が相手方のために「特定物」の保管をすることを約束して、その特定物を受け取ることによって効力を生じる契約を言います。保管する者を「受寄者」、預ける側を「寄託者」と言います。
寄託は無償で行う場合と有償で行う場合がありますが、無償で寄託を受けた場合は、”自己の財産に対するのと同一の注意義務“で保管すれば良いとされています。無償の場合は、日常自分の物を管理するのと同じくらいの注意で足りるということです。
一方有償の場合は、”善良な管理者の注意義務“、いわゆる「善管注意義務」を負います。
この2者の違いですが、前者は重過失の場合には損害賠償責任を負いますが、軽過失の場合は責任を負いません。これに対して善管注意義務がある場合は、軽過失でも責任を負うこととなります。
前回委任契約の義務について触れましたが、保管するのに必要な費用については委任の規定が準用され、寄託者に対して請求することができます。なお受寄者は寄託者の承諾なしには寄託物を使用することも第三者に保管させることもできません。無償であっても有償であっても同様です。
寄託契約は寄託物が返還されれば終了します。
返還についてですが、寄託者側は、たとえ当事者同士で返還の時期を定めた場合であっても、いつでも返還を請求することができます。一方の受寄者においては、返還の時期の定めがある場合には、やむを得ない事由がない限り期限前に返還することはできません。
では返還の定めがない場合はどうでしょうか。寄託者はいつでも返還の請求をすることができますし、受寄者においてもいつでも返還することができます。
Related Posts

今日は商法のあれこれについて書いてみます。
商法は私法の一般法である、民法の特別法に位置づけられます。法律の場合は特別法が一般法に優先しますので、商法に記載のある項目は、基本的に民法に優先します。一方、商法に記載のない項目については、民法が準用されることになります。では商法で使われる用語を見ていきましょう。
まず「商人」とはどのようなものでしょうか。商法における商人とは、「自己の名をもって商行為をすることを業とする者」です。業(ぎょう)とするがポイントですが、これは営利目的で同種の業務を反復的・継続的に行うものになります。目的自体が実現されるかどうかは問われるものではなく、同種の業務を反復的・継続的に行っている事実があれば、業として行っているということになります。
商人は、自分自身が法律上の商行為から生ずる権利義務の帰属主体となりますが、必ずしも自身が現実に営業活動を行う必要はありません。他の者に命じて行わせても構いません。一方、営業主のために商行為を代理する者は、権利義務の帰属主体ではありませんので、商人には当たりません。
この商人という資格を得るための要件は、特定の営業を開始する「準備行為」をした者になります。営業自体を開始していなくても、準備行為をした時点で商人の資格は得られるものとなります。準備行為については相手方のみならず、それ以外の者にも客観的に開業準備と認められるものでなくてはなりません。
未成年者や成年後見人の代理の者が商人になる場合については、登記が必要になります。しかし未成年の場合でもその者が結婚をしている場合は、「成年擬制」といって成年と同等の立場とみなされ、登記は必要ありません。成年擬制については、婚姻が解消されても擬制が解かれることはありません。
個人の場合の商人の資格取得については以上の通りですが、会社の場合については、設立された時に商人資格を取得することとなります。商人資格を喪失する場合は、自然人は残務処理が終了した段階で商人資格を失い、会社は清算が終わった時に商人でなくなります。
次に「商行為」というものについて見てみましょう。商行為には、
①絶対的商行為
②営業的商行為
③付属的商行為
があります。絶対的商行為とは営利性が強く、1回限りでも商行為として商法の適用を受けるものを言います。内容としては投機購買(1号)、投機売却(2号)、取引所においてする取引(3号)、手形その他商業証券に関する行為(4号)があります。
営業的商行為とはいわゆる一般的な商売や取引であり、営利目的で反復継続して行うものを言います。
付属的商行為とは営業のための補助的行為を言います。営業用の機器設備を購入するといった、開業のための準備行為などがこれに当たります。
では、「商業登記」について見てみましょう。
商業登記には次の9種類があります。
①商号登記
②未成年者登記
③後見人登記
④支配人登記
⑤株式会社登記
⑥合名会社登記
⑦合資会社登記
⑧合同会社登記
⑨外国会社登記
商業登記の効力として、登記された後でなければ善意の第三者には対抗することができません。また登記の後でも第三者に正当な理由がある場合は対抗できません。なお故意または過失によるものについては不実登記といい、第三者に対抗することはできません。
次は「商号」というものについて見てみましょう。
商号とは商人が営業をするに際し、自己を表示するために用いる名称を言います。商号は商標やマークとは異なるものです。
商号には原則や制約がありますが、まず「商号選定自由の原則」というものがあります。商号は自由に決めてもいいですよという原則になりますが、会社法(もとは商法の一部でした)からは、会社の種類によって株式会社等の文字を用いなければならないとか、会社でないものは商号中に会社と誤認させる文字を使用してはならない、ということも規定されています。
また「商号単一の原則」というものもあり、ひとつの会社にはひとつの商号しか使用することはできません。個人商人の場合については「一営業一商号の原則」とされ、営業種ごとにひとつの商号が許されます。営業種を変えれば、別の商号をつけても良いよということになります。
商号の効力として、登記の有無にかかわらず、商号を選定した者に商号使用権と商号専用権を与えます。これらの効力によって、他の者が同一または類似した商号を不正に使用することは禁止され、この権利を侵害したり侵害するおそれのある者に対しては、侵害の停止または予防を請求することができます。この禁止に違反した者は100万円以下の過料に処されることとなります。
なお商号は商法だけでなく、不正競争防止法によっても守られています。
商号は譲渡することもできます。これは営業とともに譲渡するとき、または営業を廃止するときに限りすることができるものです。この譲渡については、当事者間では意思表示のみで効力が生じますが、登記をしなければ善意悪意を問わず、第三者には対抗できません。
READ MORE
今日は民法における委任契約というものについて書いていきます。
「委任」とは当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力が生じる諾成契約になります。
「諾成契約」とは、当事者の意思表示のみで成立する契約のことを言います。ちなみに当事者の合意のみでは足らず、物の引渡しや給付を成立要件とする契約は「要物契約」と言います。
委託する側を「委任者」、承諾する側を「受任者」と言います。ここで委任とは法律行為を委託すると言いましたが、法律行為以外の事務の委託も当然あるわけで、それは「準委任」と言い委任の規定が準用されます。
委任をするにあたっては、委任者側にも受任者側にも義務や責任が発生します。
ではまず委任者側の義務について見ていきましょう。委任者は原則、受任者に経済的に負担をかけないという義務を負い、具体的には次のような義務が発生します。
①報酬支払い義務
②費用前払い義務
③立替費用償還義務
④債務の弁済または担保供与義務
⑤損害賠償義務
です。
まず①についてですが、民法においては委任というものは、原則無償委任になります。ですので、報酬の支払い義務が発生するためには報酬支払いの特約が必要になります。また特約があった場合でも、その報酬は原則後払いになります。
②では、委任された事務を処理するについての必要な費用について、事前に受任者から請求があった場合には前払いをする必要があります。あくまでも遂行に必要な費用の場合です。
③の立替費用とは、必要な費用が前払いされずに、受任者によって立替えられた費用のことです。この場合は立替えた費用を請求できるのみならず、支出以降の利息も請求することができます。
④の債務とは、委任事務を行うについての費用的なものに収まりきらず、受任者が債務を負った場合のものを言います。この場合の債務は必要と認められる範囲に限られますが、その弁済を自分に代わってするようにと、受任者は委任者に対して請求することができます。まだ弁済期の到来していない債務については、委任者に担保を請求することもできます。
⑤の損害賠償義務とは、受任者が自分に過失がないにもかかわらず損害を被った場合に、委任者に損害賠償を請求できる権利になります。この場合の委任者の責任は無過失責任(委任者に責任がなくても負う責任です)になります。
委任契約はその目的を完了したときに終了しますが、それ以外にも終了となる場合があります。
まず、理由がなくても当事者双方が一方的にいつでも解除が行える、「無理由解除」(告知と言います)というものがあります。もともと委任契約というものは無償契約が原則であるように、当事者間の信頼関係が基礎となるものになります。ですので、この信頼関係が崩れた時など、委任契約を継続することが難しいからです。
しかし関係が崩れたから一方的にというのも理不尽ではありますので、やむを得ない事由がある場合を除き、相手方に不利な時期の解除については、損害賠償を条件に認められることとなります。
また告知以外でも、委任者が死亡したり破産手続開始の決定を受けたときや受任者が死亡したり破産手続開始の決定を受けたとき、あるいは後見開始の審判を受けた場合は、当然に終了します。
READ MORE
今日は民法における事務管理というものについて書いていきます。
「事務管理」というとピンときませんが、いわゆる人のためにする「おせっかい」のことです。良かれとおせっかいでしたことも、場合によっては費用や損害が発生してしまうこともありますので、民法では「事務管理」という用語で法律効果を与えています。
具体的にはAさんの旅行中に台風でAさん宅の窓が割れてしまった場合に、Bさんが見過ごすことができずに業者に頼んで窓を応急修理した場合などです。
ではあらためて見ていきます。「事務管理」とは、法律上の義務がないのに、他人のためにその事務を行う行為を言います。事務とは行った行為のことです。この行為は契約に基づくものでもありませんし私人間の行為なので、本来法律の立ち入る必要のないことではありますが、おせっかいをした者に一定の法的保護を与えるために設けられた規定になります。
その条項では、義務なく他人の事務の管理を始めた者は、その事務の性質に従い最も本人の利益に適合する方法によってその事務管理をしなければならない、としています。またその者が本人の意思を知っている場合や推し量れる場合は、その意思に従って事務管理をしなければならないとされています。要は一旦事務管理をした場合には、必ず適切な手段をもって対応しなさいということになります。
事務管理の成立要件として、次の4つが挙げられます。
①法律上の義務がないこと
②他人の事務を管理すること
③他人のためにする意思があること
④本人の意志や利益に反することが明らかでないこと
です。
これらの要件が満たされると事務管理の効力が発生しますが、この場合はその違法性や費用の発生などが問題になってきます。
まず違法性についてですが、事務管理については勝手に他人のことについてするものですので、ともすれば権利の侵害にあたる場合も出てきます。しかしこの場合は違法性が排除され、不法行為には当たりません。
事務管理が開始した場合には、管理するものは原則、遅滞なく本人にその旨を通知しなければなりません。次に事務管理について発生した費用が問題になる場合があります。管理する上で必要な費用が発生した場合には、本人に請求することができます。これは単なるかかった費用ということでなく、本人にとって必要な者であれば認められます。
なお事務の管理方法が不適切なために損害が発生した場合については、事務管理の不履行責任を問われる場合があります。事務管理をする者は、一旦管理を始めた場合は本人等が管理できるようになるまで原則、善管注意義務を負うこととなります。この義務に反した場合には損害賠償が発生することもありますが、危急の場合には悪意重過失の場合のみ賠償責任を負うこととなります。
READ MORE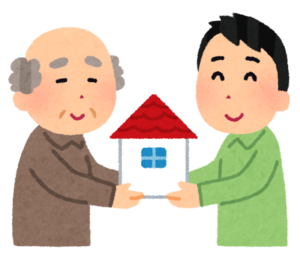
今日は動産について書いていきます。まずは動産物権変動についてです。
動産の物件譲渡は引渡しがなければ第三者には対抗できません。また動産の物件譲渡は、当事者の意思表示のみによって効力を生じます。
ここでいう第三者とは、「引渡しの欠缺を主張するについて正当な利益を有する第三者」になります。欠缺を~お馴染みの内容ですね。要はここでの第三者とは、引渡しの不備を主張することによって、何らかの利益を得る者になります。
引渡しの方法には次の4つのパターンがあります。
①「現実の引渡し」といい、占有移転の合意と事実的支配を移転することです。A○→B●になります(ここでは○を元あった場所、●を新たに置かれる場所とします)
②「簡易の引渡し」といい、事実的支配が譲受人Bにある場合に、AB間の占有移転の合意だけでなされます。A→B○●になります
③「占有改定」といい、事実的支配を譲渡人Aに残し、Aが以降Bのために占有する旨の意思表示をすることです。A○●→Bになります
④「指図による占有移転」といい、譲渡人Aが現在動産を占有している代理人Cに対して、以降譲受人Bのために占有する旨を命じ、Bがこれを承諾した場合です。この場合は占有している代理人Cの承諾は必要ありません。Bのみの承諾があれば問題ありません。以上によって占有が移転します。次は即時取得というものについて見てみましょう。
「即時取得」とは動産を、「取引行為によって平穏にかつ公然と動産の占有を始めた者は、善意でありかつ過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する」というものです。
たとえ取引した相手が無権利者であっても、その者を真の権利者として信頼して取引した場合には、真の権利者とは関係なくその取引は成立するというものです。動産の真の権利者からしたらたまったものではないですが、これは公信の原則と呼ばれ、取引の安全性を確保するために作られた制度です。
即時取得の成立要件として次のものが挙げられます。
①目的物が動産であることです。不動産には登記制度があるため即時取得は成立しません
②取引相手が無権利者であることです。その者が真の権利者として信頼した場合ではなく、その者に代理権があると信頼した場合は、即時取得ではなく表見代理の方が問題となります
③有効な取引が存在していることです。相続の場合は適用されません
④取引者が、平穏・公然・善意・無過失であることです。裏を返せば、真の権利者が動産の権利を主張するためには、即時取得者の悪意有過失を証明しなければならないということになります
⑤取得者が占有を取得したこと
です。ここで問題になることは、引渡しがなされても、引渡しの方法によっては即時取得が成立しない場合が出てくることです。それは占有改定の場合です。占有改定では即時取得が成立しません。似たような場合でも、指図による占有移転の場合は成立します。
なお即時取得の特例として、取引相手が無権利者であっても、その動産が盗品または遺失物であった場合には、盗難または遺失のときから2年間に限って被害者や遺失者はその動産を取り戻すことができます。この場合には対価は必要ありません。しかし現在の動産占有者がその動産を市場を通じて善意で買い付けた場合には、その代価を弁償することが必要になってきます。
READ MORE
今日は共有について見てみます。
これも相続分野で頻出する言葉となりますが、「共有」とは、数人の者が共同所有の割合である「持分」を併せて1つの物を所有することを言います。単純に言えば、数人で1つの物を所有することですね。
「持分」とは今述べたように、共有物に対する所有権の割合のことです。持分の割合はそれぞれの意思表示や法律の規定(法定相続分等)により決まりますが、その割合が不明な場合は各共有者平等の持分であると推定されることになります。
持分は各共有者が原則自由に処分できます。共有目的物の利用については各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。
例えば1台の自動車を3人で共有しているとしますと、3人それぞれがその自動車を自由に使用することができます。しかし異なる目的を同時に行うことはできませんので、必要な場合は各自の持分に応じた使用時間配分を決められるということです。自動車を購入するのにAさんがその代金50%、BさんとCさんが25%を出資していたとすると、その割合で使用時間を決められるということになります。
相続に当てはめると、配偶者と子供が2人いる場合は配偶者が50%の持分であり、2人の子供はそれぞれ25%ずつの持分ということになりますね。
また持分は、使用する共有者の1人がその持分を放棄した場合や、共有者が死亡した際に相続人がいない場合はその持分は他の者に帰属することとなります。
共有物には日々の利用についても制約がありますので、それらについても見ていきましょう。
共有物の利用については、その内容や利用状況から次の3つに区分されています。
①保存行為
②管理行為
③変更行為
になります。「保存行為」とは修理や修繕など、共有物の現状を維持する行為であり、各自が単独で行うことができます。なお現状維持という観点からの妨害排除請求や消滅時効の中断なども共同で行われる必要はなく、各自が単独で行うことができます。
次の「管理行為」とは、共有物の性質を変えることなく利用したり改良する行為とされています。これには共有物の賃貸やそれに関する解除や取り消し行為などがありますが、この場合は単独で行うことはできず、共有の過半数の合意が必要になります。
過半数とは人数が基準になるものではなく、持分の価格を基準にしての過半数になります。Aが10でBが20の持分価格を有していても、Cが50を有する場合には必ずCの承諾が必要になります。
「変更行為」とは共有物の性質や形状を変更することを言います。具体的には共有物を売却したりその全部に抵当権等を設定する場合がこれに当たりますが、この場合は共有者全員の同意が必要になります。
最後に「共有物の分割」について見てみましょう。共有物については、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができます。分割の方法は現物分割、代金分割、価格賠償の3つがあります。
ここでの「現物分割」とは現物そのものを分割すること、「代金分割」とは共有物を売却してその代金を分割する方法です。「価格賠償」とは共有物を分割した際に持分に満たない者に、超過した者からその金額を補填することを言います。
共有分割の協議が整わない場合は遺産分割協議同様、裁判所に分割を請求することになります。なお遺言書による場合が多いですが、共有物を5年を超えない期間で分割を禁止する特約を付けることもできます。
READ MORE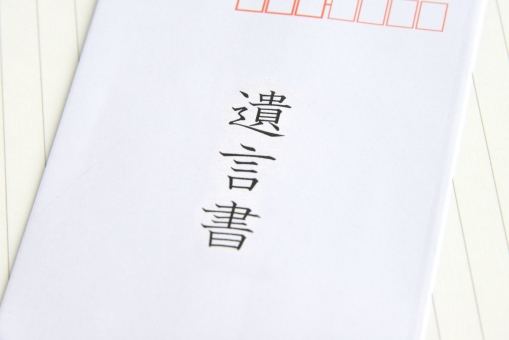
今日は相殺というものについて書いていきます。
「相殺」とは、2人のものがお互いに同種類の債権債務を有している場合に、その債権債務を対等額で消滅させる、相殺する側の一方的な意思表示のことを言います。
相殺の効果は債権債務の現実の履行を省略することにあり、相殺適状を生じた時にさかのぼって抗力を生じます。お互いの債権が相殺の要件を満たしている状況を「相殺適状」と言います。
相殺には「する側」と「される側」がありますが、相殺する側の債権を「自働債権」(自動ではありません)と言い、相殺される側の債権(相殺する側の債務)を「受働債権」と言います。
相殺が成立するには次の5つの要件があります。
①2つの債権が対立していること
②双方の債権が同種の目的を有すること
③双方の債権が弁済期にあること
④双方の債権が有効に存在していること
⑤相殺を許す性質の債権であること
です。
要件③についてですが、受動債権(相殺される側)については債務者が「期限の利益」を放棄することができますので、必ずしも弁済期にある必要はありません。ですので条文にあるように双方が弁済期にある必要はなく、自働債権のみ弁済期にあることが必要になります。
要件④の、双方の債権が有効に存在していなければならない、という要件についても例外があり、債権が時効によって消滅していた場合でも、その債権が時効消滅前に相殺することができる状態に既になっていた場合には、この債権を自働債権として相殺することができます。なお、お互いの債権が相殺の要件を満たしている状況を前述の「相殺適状」と言います。
要件⑤の相殺を許さない性質の債権についてですが、自働債権に「同時履行の抗弁権」などの抗弁権が付いている場合には相殺することができません。一方、受働債権に抗弁権が付いている場合には、相手方の利益を特に害することはないため、相殺することも許されます。
また自働債権が差し押さえられてしまった場合ですが、これは法律によって処分等が禁止されることになるため、相殺をすることができなくなります。
先に相殺は一方から相手方への一方的な意思表示と言いましたが、裏を返せば相殺の意思表示がない限りは相殺は行われず、債権は消滅しないことになります。また相殺する側の一方的な単独行為になりますので、相手方の同意は必要ありません。
なお相殺の意思表示には、条件や期限などを設けることはできません。
最後に相殺が禁止される場合について触れておきます。次のような場合は相殺が禁止されます。
①当事者が相殺禁止の特約をした場合
②受働債権が不法行為にもとづく損害賠償請求権である場合
③受働債権が差押禁止債権である場合
④受働債権が支払いの差し止めを受けた場合
です。
②について説明をしますと、例えば不法行為を受け損害賠償権を有した被害者が、その加害者に借金をしていた場合が挙げられます。この場合では、加害者側が被害者に貸していた100万円で、被害者側からの100万円の損害賠償権を相殺する、ということはできないということになります。
これは相殺がなされてしまうと、被害者側が現実の救済を受けられなくなってしまうことと、それがために報復などの不法行為を誘発するおそれがあることが理由になります。
なお立場を入れ替え、被害者側の債権を自動債権とし、被害者側から相殺することは判例から認められています。
READ MORE
今日は民法の不当利得について書いていきます。
「不当利得」とは、法律上の原因がないにもかかわらず、他人の財産や労務によって利益をうけ、そのために他人に損失を及ぼすことを言います。不当利得を得た者は、その利益の存する限度(現存利益)においてこれを返還する義務を負います。また利得を得る際に悪意であった者については、利得の返還とともに損害賠償の責任も負います。
不当利得の成立要件は次の4つになります。
①利得が存在すること
②損失が存在すること
③利得と損失の間に因果関係が存在すること
④法律上の原因がないこと
です。
ちなみに「現存利益」とは、自分の利益として残っている利益を言いますが、単純に手元に残っている現金や預貯金ということではありません。現に利益として残っているものを言います。
わかりにくいですが、例えば不当利得が10万円あったとした場合、食費に2万円使ってしまったとします。この場合の2万円は自分の利益のために使ったのですから、お金は残っていなくても栄養を得たという効果が残っています。ですので残った8万円に2万円分の食費が足されて、10万円が現存利益となります。
一方、ギャンブルなどの遊興費に2万円を浪費してしまった場合は、利益としてはなんら残っていないことになります。この場合は浪費した2万円分は差し引かれて、現存利益は8万円となります。
不当利得の具体例としては次のようなものがあります。
AさんがBさんに有名画家の絵を100万円で売ったとします。契約が成立し、BさんはAさんから絵の引渡しを受け代金を支払いました。しかし後日この絵が偽物であったことが判明したので、BさんはAさんに「不当利得返還請求」をしました。しかもAさんはこの絵が偽物であることを知っていて(悪意)販売したので、損害賠償も請求しました。という形になります。
このような不当利得ですが、次の場合には特則が付されています。
①債務の不存在を知っていてした弁済
②期限前の弁済
③他人の債務の弁済
です。
どのようなことかと言うと、①は、自分に債務がないことを知っていながら弁済を行った場合です。不合理な行為ですが、このような不合理な行為をした者には保護を図る必要もないことから、その給付したものの返還を請求することはできません。ただし、強制執行を避けるために必要的にした場合や、その他の事由によってやむを得ず行った場合には返還請求を行うことができます。差し当って請求されている弁済を行わないと、差押がなされるなどの場合です。
②の期限前の弁済とはどのようなものでしょうか。通常の弁済には「期限の利益」があり期限までは弁済を行う義務はありませんが、この期限の利益を行使せずに、期限前に弁済を行った場合です。この場合はみずからが権利を行使しなかったのですから、不当利得(弁済から期限までの利息分)返還請求をすることはできません。ただし債務者が錯誤によってその給付を行った場合には、債権者は不当利得を返還する必要があります。
③の他人の債務の弁済とは、他人の債務を自分の債務と誤信して弁済してしまった場合です。この場合では、債権者が善意で債権証書を消失したり、担保を放棄したり、債権を時効で消滅させたりしてしまった時などは、弁済者は不当利得の返還請求をすることはできません。これは弁済者の過失より善意の債権者の保護が優先されるからです。
この場合の弁済者については、あくまでも債権者に対して返還請求できないのであって、本来の債務者に請求することはできます。誤ってした弁済を泣き寝入りするものではなく、本来の債務者に対して求償権を行使することができます。
READ MORE
今日は詐害行為取消権について書いていきます。
「詐害行為取消権」とは、債務者がその責任財産を減少させる法律行為(詐害行為)をした場合に、債権者がその行為を取り消し、減少した財産を回復させる権利をいいます。これは強制執行を行う前の準備段階として、総債権者の責任財産の保全を目的とした制度になります。
「詐害行為取消権」の成立要件としては、次の6つが挙げられます。
①保全される財産が金銭債権であること
②保全される財産が、詐害行為前に成立していること
③債務者が詐害行為時および取消権行使時に無資力であること
④財産権を目的とした法律行為であること
⑤債務者に詐害の意思があること
⑥受益者や転得者が悪意であること
です。
では、詐害行為取消権の行使の方法や効果について見ていきましょう。
詐害行為取消権は、債権者が必ず「自己の名」で行ないます。また債権者代位権と異なり、必ず「裁判上」で行わなければなりません。
取り消しを行える範囲は、債権者の被保全債権額の範囲に限定されます。建物のように目的物が不可分の場合は、被保全債権額が建物価格に足りなくても、詐害行為の全部を取り消すことができます。
詐害行為取消権を行使できる期間は、債権者が取り消しの原因(詐害行為)を知った時から2年間(消滅時効)となります。知らない場合も詐害行為から20年で時効(除斥期間)となります。
詐害行為取消権の効力は全債権者の利益のために発生することとなり、受益者や転得者から取り戻された財産は、全債権者の共同担保となります。目的物の引渡しについては債権者代位権同様、原則は債務者への引渡しとなりますが、直接債権者への引渡しを請求することもできます。
とは言っても、詐害行為取消権には効果の及ぶ範囲が定められています。債務者であっても自分の財産を処分することは自由であるはずですが、詐害行為取消権はこの自由を制約するものとなりますので、その制約を最小限に抑える内容となっています。
これから、詐害行為取消権の被告は債務者ではなく、受益者または転得者にすべきとしています。
また取り消し判決がなされる場合でも、その効力の及ぶ範囲は取り消し債権者と相手方(受益者または転得者)の関係でのみ詐害行為の抗力を失わせるものであって、第三者の法律関係には影響は及ぼさないとされています。
READ MORE今日は代理について書いてみます。
民法の規定における「代理」とは、代理人が本人(代理される者)のためにすることを示して(「顕名」といいます)、相手方に対して意思表示をし、その法律効果を本人に帰属させる制度を言います。代理には「任意代理」と「法定代理」があります。では代理について見ていきましょう。
まず代理の要件ですが、
①代理人に有効な代理権があること
②本人のためにすることを示すこと(顕名)
③代理権の範囲内で意思表示をする
ことです。顕名は口頭でも署名でも問題ありません。口頭というのは、「Aさんの代理のB」ですと相手に告げる場合などです。
顕名がない場合の代理行為は代理人自身のためのものだとみなされますが、顕名がなかった場合でも、相手方がその事情を知りまたは知ることができれば代理の効果は認められます。代理行為のすべてが代理される本人に帰属します。
代理の禁止事項が2つあります。一つは「自己契約」であり、代理人が本人の相手方になることをいいます。もうひとつは「双方代理」であり、当事者双方の代理人になることをいいます。これらは債務を履行する場合や本人があらかじめ了承した場合を除き原則無効となりますが、事後に本人が追認した場合は有効となります。
代理人の権限を代理権と言いますが、代理権があっても認められない行為に「代理人の権限乱用」があります。これは代理人が代理人自身や第三者の利益を図る意図を持って、代理の形式のまま本来の権限の範囲内の行為をすることをいいます。この場合の行為も本人に帰属する(この場合の本人は、その代償を代理人に求めることになります)ことになりますが、相手方が代理人の意図を知りまたは知ることができたときに限っては、本人の責めにはならないとされています。ここもポイントです。
代理人が代理人を設けることを「復代理」といいます。間違えやすいですが、複数の複ではありません。
復代理とは、代理人が自己の権限内の行為を行わせるために、代理人自身の名でさらに代理人を選任し、本人を代理させる行為をいいます。代理人の代理人ではなく、あくまでも本人直接の代理人となります。
これには法定代理と任意代理がありますが、法定代理の場合は常に復代理を選任できるのに対して、任意代理の場合は本人の許諾がある場合や、やむを得ない事由があるときでなければ復代理人を選任できません。
代理人は誰にでもすることができ、本人が承知の上であれば成年被後見人のような制限行為能力者であっても代理人となれます。
代理人に似た概念に「使者」というものがありますが、代理人が意思決定ができるのに対し、使者の場合は意思決定はあくまでも本人がします。使者は本人の意思を完成させるだけの者になります。
代理に関しては無権代理と表見代理というものがありますが、次回これについて書いていきます。
READ MORE今日は普通養子縁組の解消について書いていきます。
縁組も婚姻同様、他人同士の意思の合致による行為になりますので、お互いの意思が合致しなくなった場合も、婚姻同様にその関係が解消されることとなります。
婚姻の場合の離婚に当たるものが、「離縁」になります。「離縁」には
①協議離縁
②裁判離縁
があります。
「協議離縁」とは、当事者同士の協議によってするものを言います。離縁の成立要件は縁組の時と同様に、形式的要件と実質的要件になります。形式的要件はこれも届出になります。実質的要件は当事者間の、養親子関係を終了させる意思の合致になります。
未成年や成年被後見人の場合は通常単独で協議を行うことはできませんが、未成年であっても15才以上の者は単独で離縁をすることができ、成年被後見人の場合も本心に復している場合は単独ですることができます。
配偶者のある者が未成年者と縁組をするには、夫婦揃っての縁組が必要でしたが、離縁についても夫婦がともにしなければなりません。
縁組の当事者の一方が死亡した場合はどうでしょうか。この場合の一方の生存者は、家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。これを「死後離縁」と言います。養親子関係自体は当事者の一方または双方が死亡すれば消滅しますが、法定関係は存続しますので、相続も発生します。
また配偶者死亡の時同様、縁組によって生じた法定血族関係は当然には消滅しませんので、これらの関係を消滅させるには、家庭裁判所の許可が必要になります。
離縁の無効や取り消しの場合も、婚姻の場合と同じです。離縁意思の合致を欠いたり、代諾権のない者が代諾した場合は無効になります。
また詐欺や強迫によって行われた離縁は取り消しをすることができます。この場合は詐欺を発見し、または脅迫から免れた時から6ヶ月以内に、家庭裁判所に請求をします。取り消しの効果は離縁の時点に遡及することとなり、離縁はなかったものとなります。
「裁判離縁」は、協議離縁が成立しなかった場合に、家庭裁判所への請求によってなされます。裁判離縁の成立する要件としては、
①他の一方から悪意で遺棄されたとき
②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
③縁組を継続し難い重大な事由があるとき
になります。
離縁の効果によって、養親子関係および法定親族関係が、離縁の日から消滅することになります。
また養子は離縁前の氏に戻ることになり、原則として離縁前の戸籍に入ることになります。離婚の場合の氏については婚氏続称という制度がありますが、離縁にもあります。
離縁の場合に離縁前の氏を継続する時は離婚よりも要件は厳しいものとなり、縁組が7年以上継続されている必要があり、離縁の日から3ヶ月以内に届出を行う必要があります。
READ MORE
コメントはまだありません
