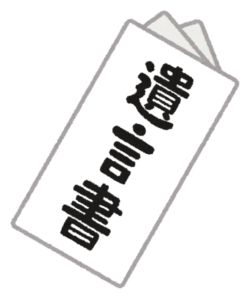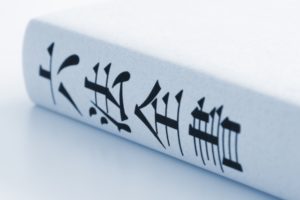相続分野の民法の一部改正が7月1日に施行されます。
それに先立ち、本年1月13日に自筆証書遺言書の方式緩和(自書以外の財産目録可)の改正民法が施行されました。これは、財産目録について、従来は手書きでないと認められていなかった要件を、銀行通帳等を添付すればパソコンや自分以外の他者の作成によるものでも認めるという内容になります。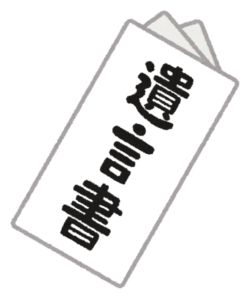
ニュースでも流れたのでしょうか、当職のホームページの当該ページへのアクセスも、2-3ヶ月にわたって通常月の1.5倍ほどに上がっています。相続に比べると遺言ページへのアクセスは多くないのですが、普段意識していなくてもニュースになると興味がわくのでしょうか。そのままご依頼いただけると、なおありがたいのですが。。いつかご依頼いただけることをお待ちしております。
さて要件緩和によって自筆証書遺言の作成については多少ハードルは下がりましたが(財産の多い方はなおさら)、そのほかの自筆遺言の要件についての知識はまだまだ低いようです。もちろんご自身で時間をかけて勉強し、ご自分で書かれる方もいらっしゃると思いますが(最大のメリットは費用面ですが)、要件不備で遺言書としての法的効果がなかったり、相続人にかえって迷惑を掛ける自筆証書遺言の多いことも確かです。
もちろんご自身はよかれと思って書かれている訳ですが、中途半端な知識で書かれるため、法律要件を満たしている遺言書は必ずしも多くはないと思われます。日付間違いや誤記などのケアレスミスの場合、あるいは署名の不備等の場合は相続人の方々の合意があれば大きな問題はないと思いますが、これとて訴訟になった場合は認められない場合も多くなります。
一番困るのは、相続人や相続財産の特定が曖昧な場合です。例えば、「預貯金を子供3人に等分に」という記述であれば、単純に分割することは可能ですし、銀行もその記述をもって払い戻しに応じてくれると思います。しかし、「不動産を子供3人に平等に」という文言であれば、どの不動産をどのように分割するのか特定できませんので、不動産登記は難しくなります。この場合は遺産分割協議によって具体的に不動産を分割し(あるいは特定の相続人に単独に)、分割協議書に明記する必要が出てきます。
この遺言書の場合も相続人の皆さんが不仲でなく、遺言者に寛容であれば遺言書の文言に則した形で協議は行われるのでしょうが、えてしてその遺言によって利益を受ける者は拡大解釈でその文言を了とし、利益を害する者は断固反対する。そのような事態も決して少なくはないでしょう。
このような遺言書があった場合は意見が分かれる、あるいは協議の前段部分で時間を取られる弊害が大きくなります。また協議が成立しても後々までの遺恨の原因になります。
自筆証書遺言を書かれる場合でも必ず専門家に指導を仰ぐ、あるいは公正証書遺言にする。費用はかかりますが、本来の目的を達成するためには必要なことです。行政書士のような専門家は時間を掛けて勉強し、また数々の事例からベストのアドバイスを行っていきます。
Related Posts

今日は民法における委任契約というものについて書いていきます。
「委任」とは当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力が生じる諾成契約になります。
「諾成契約」とは、当事者の意思表示のみで成立する契約のことを言います。ちなみに当事者の合意のみでは足らず、物の引渡しや給付を成立要件とする契約は「要物契約」と言います。
委託する側を「委任者」、承諾する側を「受任者」と言います。ここで委任とは法律行為を委託すると言いましたが、法律行為以外の事務の委託も当然あるわけで、それは「準委任」と言い委任の規定が準用されます。
委任をするにあたっては、委任者側にも受任者側にも義務や責任が発生します。
ではまず委任者側の義務について見ていきましょう。委任者は原則、受任者に経済的に負担をかけないという義務を負い、具体的には次のような義務が発生します。
①報酬支払い義務
②費用前払い義務
③立替費用償還義務
④債務の弁済または担保供与義務
⑤損害賠償義務
です。
まず①についてですが、民法においては委任というものは、原則無償委任になります。ですので、報酬の支払い義務が発生するためには報酬支払いの特約が必要になります。また特約があった場合でも、その報酬は原則後払いになります。
②では、委任された事務を処理するについての必要な費用について、事前に受任者から請求があった場合には前払いをする必要があります。あくまでも遂行に必要な費用の場合です。
③の立替費用とは、必要な費用が前払いされずに、受任者によって立替えられた費用のことです。この場合は立替えた費用を請求できるのみならず、支出以降の利息も請求することができます。
④の債務とは、委任事務を行うについての費用的なものに収まりきらず、受任者が債務を負った場合のものを言います。この場合の債務は必要と認められる範囲に限られますが、その弁済を自分に代わってするようにと、受任者は委任者に対して請求することができます。まだ弁済期の到来していない債務については、委任者に担保を請求することもできます。
⑤の損害賠償義務とは、受任者が自分に過失がないにもかかわらず損害を被った場合に、委任者に損害賠償を請求できる権利になります。この場合の委任者の責任は無過失責任(委任者に責任がなくても負う責任です)になります。
委任契約はその目的を完了したときに終了しますが、それ以外にも終了となる場合があります。
まず、理由がなくても当事者双方が一方的にいつでも解除が行える、「無理由解除」(告知と言います)というものがあります。もともと委任契約というものは無償契約が原則であるように、当事者間の信頼関係が基礎となるものになります。ですので、この信頼関係が崩れた時など、委任契約を継続することが難しいからです。
しかし関係が崩れたから一方的にというのも理不尽ではありますので、やむを得ない事由がある場合を除き、相手方に不利な時期の解除については、損害賠償を条件に認められることとなります。
また告知以外でも、委任者が死亡したり破産手続開始の決定を受けたときや受任者が死亡したり破産手続開始の決定を受けたとき、あるいは後見開始の審判を受けた場合は、当然に終了します。
READ MORE

今日は婚姻の効果について書いていきます。婚姻は役所に届出をすることが形式上の要件となっており、届出をしない限りは法律上の夫婦とは認められません。
「婚姻の効果」については次のようなものがあります。
①夫婦同氏
②同居・協力・扶助義務
③貞操の義務
④成年擬制
⑤契約取消権
です。
「夫婦同氏」については改正を求める声もありますが、現行民法においては夫婦は共通の氏を名乗らなければなりません。法律の婚姻効果を発生させるためには戸籍上同一の性にしなければなりませんが、ペンネームや職場で旧姓を名乗ることについて等は差し支えありません。
「同居・協力・扶助義務」については、婚姻を継続するにあたっての基本的な義務になります。
「貞操の義務」についても明文化されており、これについては裁判上の離婚原因にも当たります。
「成年擬制」とは、未成年でも婚姻によって成年に達したものとみなされ、成年と同様の権利義務を与えられることです。この効果によって通常未成年では行えない養子縁組行為や、登録なしで営業をすることができるようになります。なお一度婚姻をすれば、これが解消された場合であっても成年擬制の効果は消滅しません。
「契約取消権」とは、婚姻中に夫婦間でしたお互いの契約について、婚姻中はいつでも取り消すことができるというものです。夫婦間の問題については法による強制は立ち入らないということであり、履行後であっても取り消せます。しかし第三者が関与するものについては、その権利を害しての取り消しはできません。
次に夫婦の財産制度について見ていきましょう。
夫婦は「夫婦財産契約」という契約で、自由に夫婦の財産関係を定めることができます。これは契約がない場合の民法の規定による「法定財産制」に対して、自らで取り決める契約になります。日本では民族性からかあまり普及していませんが、数年前に俳優さんと女性弁護士の結婚の際に話題になりました。
通常は公正証書で残したりしますが、この契約の形式は次のとおりかなり厳格なものになります。
①婚姻届出前に締結しなくてはなりません
②婚姻届出までに登記を行ないます
③登記がなければ夫婦の承継人および第三者に対抗することができません
④婚姻届出後はその契約を変更することはできません
次は財産契約を結ばない場合の「法定財産制」についてです。
「法定財産制」は次の3つからなります。
①婚姻費用の分担
②日常家事債務の連帯責任
③財産の帰属と管理における夫婦別産制
です。
①の費用の分担については特に問題はありませんが、②の「日常家事債務の連帯責任」とは、日常発生する家事(特別でない行為)によって生じた債務については、一方が第三者に対して他方の免責を告げたときを除いて、夫婦ともに連帯責任を負うというものです。
ここでの日常家事の範囲については、客観的にその法律行為の内容等を十分考慮して判断するものとされています。
「夫婦別産制」とは、夫婦の一方が婚姻前から有している財産、および婚姻中であっても自分の名前で得た財産については、夫婦それぞれの個人的な財産とすることを言います。
これに対して夫婦どちらに属するか不明な財産については、夫婦共有のものと推定されます。
READ MORE

今日は瑕疵ある意思表示の続きです。まず「錯誤」について見てみましょう。
民法第95条に錯誤について規定されています。「意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない」という条文です。
錯誤とは表意者の意思と表示に不一致があっても表意者がそのことを知らない場合をいい、その意思表示は原則無効になります。この無効は第三者に対しても対抗できます。錯誤には「要素の錯誤」と「動機の錯誤」があります。
まず「要素の錯誤」とは法律行為の重要な部分についての錯誤であって、錯誤がなければ表意者だけでなく、他の人でもその意思表示をしなかったであろうと考えられる場合です。
例えばAさんがB土地を売るつもりが、C土地をB土地だと錯誤してしまってC土地を売ってしまった場合がこれに当たります。この場合はAさんはC土地を売ってしまったことを無効を訴えることができますが、Aさんに重大な過失がある場合は、無効を訴えることはできません。重大な過失とは文字通り、看過すべきでないほどの過失をいいます。
しかしAさんに重大な過失があった場合でも、相手方が悪意(表意者の錯誤に気付いていた)である場合や、当事者の双方が錯誤に陥っている場合は、重大な過失があったにせよ無効を訴えることができます。双方の錯誤とは今の例で言えば、Aさんとともに相手方のDさんもC土地をB土地だと勘違いして、お互いの契約を結んでしまった場合がこれに当たります。お互いが間違えていたということで、契約を無効にできます。
要素の錯誤とは別に、「動機の錯誤」というものがあります。要素の錯誤が意思表示そのものにあるのに対し、動機の錯誤とは意思を形成する動機が構成要素となり、表意者の動機と表示に不一致があっても表意者がこれを知らない場合の錯誤を言います。
AさんがB土地の近くにショッピングセンターが建設されることを聞いたため、値上がりを見越してB土地を購入をするといった場合では、ショッピングセンターの建設予定が動機になります。動機の錯誤とは、例えば建設予定は噂だけで実際は建設されないけれどもAさんはこれを知らない場合がこれに当たります。
この場合は無効を主張できますが、通常の契約のたびに思い違いを理由に無効を主張されても困ってしまいます。民法では動機の錯誤を主張できる要件として、もう二つの要件を規定しています。
ひとつはその動機が相手方に明示されていなければならないということです。今の例で言えば、契約をする不動産会社に対し、「近くにショッピングセンターが建設されるから、土地の値上がりを期待して買う」ということを伝えている場合です。また明示でなく黙示であっても相手方がその意図を知ることができた場合もこれに当たります。意図を伝えず、心の中で思っていただけでは無効は主張できません。
もう一つは表意者に重大な過失がないことです。
「要素の錯誤」であっても「動機の錯誤」であっても、無効を主張できるのはあくまで意思表示をした当事者に限られます。他の者はすることはできません。民法の規定は意思表示者を保護するためのものですので、表意者自身が無効を主張しない場合は認められません。
しかし例外として、表意者が錯誤の事実を認めている場合でかつ債権保全の必要性がある場合には、第三者による主張も認められます。
今まで見てきた、無効にすることができる意思表示である「心理留保」「通謀虚偽表示」「錯誤」の他に、取り消すことのできる意思表示に「詐欺」と「脅迫」があります。
「無効」というのは法律上当然に効力がないということであり、いつでも誰でも(錯誤は本人のみですが)主張できます。一方の「取り消し」は、その法律行為が取り消されるまでは一応有効であることと、取り消された場合はその事実が起こった時点までさかのぼって無効になることが、「無効」と異なる点です。
本人のみならず、代理人などの特定の者もすることができます。また追認された場合は初めから有効になる性質があり、追認可能時から5年(発生から20年)で時効になります。
取り消すことのできる意思表示のひとつである「詐欺」ですが、取り消すことはできても善意の第三者には対抗できません。だまされた本人にも多少の責任はあるということです。また相手方以外の第三者が詐欺を行った場合には、相手方がその事実を知っていた場合に限り取り消すことができます。
もうひとつの「強迫」による意思表示も取り消すことができます。強迫は善意の第三者にも対抗できます。詐欺にあった者と違って、強迫をされた者に落ち度はないからです。
よく刑事ドラマなどで「脅迫」という言葉がでてきますが、「強迫」とは違うのでしょうか。「脅迫」は人を脅して何かを要求することですが、これは刑法上の法律用語になります。一方の「強迫」は民法上の法律用語になります。ややこしいですが、法律では独特の用語が使われます。漢字や読み方が普段使っている言葉と異なることも多いですね。遺言の「ゆいごん」「いごん」も同じようなものですね。
READ MORE
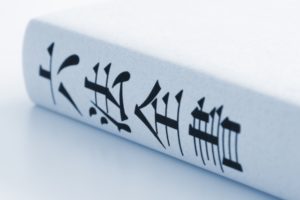
しばらく民法について書いていきたいと思います。相続や遺言については民法に規定されています。また私人間の契約関係や家族関係についても民法に規定されていますので、民法を学んでおくことは、相続の際にも役に立ちます。
民法は、私人間の生活関係を規律する私法の一般法であり、財産法と家族法からなります。全体は①総則②物権法③債権法④親族法⑤相続法の5つに分けて整理されています。
財産法である物権については、所有権絶対の原則が支配しています。私人は自己の所有物を自由に支配できるというものです。しかしこれにも唯一、公共の福祉の制約があります。
公共の福祉の制約は民法のみならず、憲法をはじめとしたあらゆる法律のベースにあるものです。その解釈についてはむつかしい争いがあるようですが、要はいくら自分が自由にできるといっても、公共(周りの人々)の権利や迷惑を冒してまでは認められませんよということですね。
自分の家の裏手の道路に障害物を置いて、住民の通行を妨害していたおじさんが捕まりましたが、公共の福祉の制約は知らなかったようですね。また自分の家の木の枝が境界線を道路に思い切りはみ出して、いくら危険であっても、頑として枝を切らないじいさんがいましたね。民法の規定では、近所の人がこの空中に突き出た枝を自ら切ることはできなくて、切ってくれと要請するしかありません。境界線をはみ出した根っこの場合は、住民自ら切ることができますが。行政の怠慢ではありますが、この場合は道路法で対処するか、万が一この枝によって負傷した場合に管理責任を問うて損害賠償を請求するかですかね。
話が脱線しましたが、もうひとつ財産法には債権があります。債権関係は私的自治の原則というものが支配しています。
私人間の私的法律関係は個人の自由意思で形成されるものであり、国家は介入できないとされています。しかしこれには様々な制約があります。
今回の民法改正にもありましたが、債権は特に法律が強く関与しているため、時代や経済の要請によって変化して然るべきものでもあります。現代では経済的弱者(賃借人等)救済のための制約が種々設けられています。
一方の家族法について現在の民法では、戦前までの旧民法とは考え方において根本から変更されたものとなっています。
家族法の基本原理は、個人の尊厳と両性の本質的平等を基礎として、家族は夫婦を中心としたもの規律されています。戦前までの民法における家族の考え方は、夫婦ではなく親子を中心とした考え方でした。これが家長制度の裏付けともなっています。
家族法はあくまで夫婦二人を主な対象としていますので、前述の財産法における自由な個人の権利義務とは相容れない部分もあります。ですので一般的に財産法の基本原理は家族法には適合しないものとなっています。
さて、民法のような「私法」とはどのようなものでしょうか。
私法とは、国家と国民の基本的な関係について定めた憲法のような「公法」に対し、「私人と私人との法律関係」を規律する法をいいます。言い換えると、社会生活上当然に生ずる私人間相互の関係を規律する法ということです。
私法によって保護される権利を「私権」といいます。私法は、法律関係を充足すると法律効果が発生するというスタイルをとりますが、私権の行使に関しては「制約原理」というものがあります。私権は法律で認められはしても、そこには一定のルールがありますということです。
1つめは先ほどの公共の福祉の原則です。2つめは「信義誠実の原則」といって、よく「信義則」という言葉で使われます。今の国会では特によく出てきますが、相手の信頼を裏切らないように行動しましょうということです。
これに関連しては、「禁反言の法理」や「クリーンハンズの原則」といった言葉も使われます。前者は自らの行為と矛盾した態度は許されないということ、後者は法を尊重する者のみが法の尊重を要求できるというものです。
3つめは「権利濫用の禁止」です。たとえ認められた権利であっても、社会性に反しての濫用は認められないというものです。濫用の基準は、得る権利と失う利益を比較検討して判断するとされています。
これら信義則や権利濫用については、表立って出されるものではなく、他の条文で決着しない場合に適用されるものとなります。
READ MORE

今日は婚姻の無効や解消について書いていきます。
まず婚姻の解消についてです。「婚姻の解消」理由には、
①離婚
②死亡・失踪宣告による解消
があります。
「離婚」については「協議上の離婚」と「裁判上の離婚」がありますが、まず協議上の離婚について見てみましょう。
「協議上の離婚」とは、夫婦お互いの協議によって成立する離婚になります。この場合には夫婦ともに離婚する意思があること(離婚意思の合致)と、離婚の届出を行うことが必要とされています。なお判例ではこの離婚意思の合致について、離婚そのものをする意思は必要とせず、届出をする意思のみで足りるとしています。
また離婚の際に未成年の子がいる場合は、必ず一方を「親権者」にしなければなりません。
離婚そのものをする意思であれ、届出をする意思のみであれ、それらを含む離婚意思のない者の離婚は当然に無効となります。「意思のない離婚」とは、詐欺または強迫によって協議離婚がなされる場合であり、この場合は取り消しを請求することができます。この取消権は、詐欺を見つけた時または強迫から免れた時点から3ヶ月で消滅します。また追認によっても消滅することになります。
協議上の離婚が成立しなかった場合は「裁判上の離婚」になります。離婚の場合は原則、訴訟を起こす前に家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚が成立しない場合に裁判上の離婚に向かいます。
離婚の訴えを提起する場合には、次の理由が必要になります。
①配偶者の不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
です。
裁判所はそれらの事情を考慮して、離婚の訴えを認めるか棄却します。なお②の悪意の遺棄とは、理由もないのに同居を拒んだり家計費を差し入れないなど、積極的な意思で夫婦関係を行わないことを言います。
以上、協議上であれ裁判上であれ、離婚が成立した場合には次の効果がもたらされます。
①身分上の効果
②子の処遇
③財産上の効果
です。
「身分上の効果」により、婚姻関係とそれに伴う姻族関係が消滅します。また姓(氏)を改めた者については、「婚氏続称の届出」をしない場合は、結婚前の姓に戻ります。
「子の処遇」についてはまず、その子の嫡出子たる身分には影響は及ぼしません。また未成年の子の場合は親権者が決められます。
「財産上の効果」としては、一方が他方に財産分与を請求することができます。その額や方法は当事者の協議によりますが、協議が成立しない場合は離婚から2年以内であれば家庭裁判所にも処分を請求できます。
次は婚姻の無効と取り消しについて見てみましょう。無効と取り消しはその効果や影響が異なりますので、婚姻の瑕疵の程度に応じて規定がなされています。
まず、より影響の大きい無効について見てみましょう。
「無効」とされた場合は、婚姻が最初から無効であるとされ、夫婦としての効果は何ら生じません。婚姻の無効は、次の場合に限りなされます。
①婚姻意思を欠く場合
②届出を欠く場合
です。
無効は請求がなされて成立しますが、無効を請求することができる者は当事者だけでなく、利害関係者は誰でも主張することができます。これは当事者が死亡していても主張することができます。
次の「取り消し」ですが、これは無効よりも限定的な効果であり、取り消しの効果は婚姻成立時までは遡及しません。取り消しまでの期間は婚姻が有効とされ、その期間は財産分与などの財産関係も適用されます。
婚姻の取り消しを請求できる者は、当事者およびその親族、また検察官になります。
無効は当事者の死亡後も請求できますが、取り消しでは当事者の死亡後の請求は当事者や親族のみが行え、検察官は請求をすることはできません。また重婚違反の場合は当事者の配偶者および前配偶者も請求できます。これも失踪宣告の記事で確認ください。
再婚禁止期間の違反については親子関係の証明も関わりますので、前夫についても取り消しを請求することができます。詐欺・強迫の場合は当事者のみの請求となります。
READ MORE
今日は普通養子縁組の解消について書いていきます。
縁組も婚姻同様、他人同士の意思の合致による行為になりますので、お互いの意思が合致しなくなった場合も、婚姻同様にその関係が解消されることとなります。
婚姻の場合の離婚に当たるものが、「離縁」になります。「離縁」には
①協議離縁
②裁判離縁
があります。
「協議離縁」とは、当事者同士の協議によってするものを言います。離縁の成立要件は縁組の時と同様に、形式的要件と実質的要件になります。形式的要件はこれも届出になります。実質的要件は当事者間の、養親子関係を終了させる意思の合致になります。
未成年や成年被後見人の場合は通常単独で協議を行うことはできませんが、未成年であっても15才以上の者は単独で離縁をすることができ、成年被後見人の場合も本心に復している場合は単独ですることができます。
配偶者のある者が未成年者と縁組をするには、夫婦揃っての縁組が必要でしたが、離縁についても夫婦がともにしなければなりません。
縁組の当事者の一方が死亡した場合はどうでしょうか。この場合の一方の生存者は、家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。これを「死後離縁」と言います。養親子関係自体は当事者の一方または双方が死亡すれば消滅しますが、法定関係は存続しますので、相続も発生します。
また配偶者死亡の時同様、縁組によって生じた法定血族関係は当然には消滅しませんので、これらの関係を消滅させるには、家庭裁判所の許可が必要になります。
離縁の無効や取り消しの場合も、婚姻の場合と同じです。離縁意思の合致を欠いたり、代諾権のない者が代諾した場合は無効になります。
また詐欺や強迫によって行われた離縁は取り消しをすることができます。この場合は詐欺を発見し、または脅迫から免れた時から6ヶ月以内に、家庭裁判所に請求をします。取り消しの効果は離縁の時点に遡及することとなり、離縁はなかったものとなります。
「裁判離縁」は、協議離縁が成立しなかった場合に、家庭裁判所への請求によってなされます。裁判離縁の成立する要件としては、
①他の一方から悪意で遺棄されたとき
②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
③縁組を継続し難い重大な事由があるとき
になります。
離縁の効果によって、養親子関係および法定親族関係が、離縁の日から消滅することになります。
また養子は離縁前の氏に戻ることになり、原則として離縁前の戸籍に入ることになります。離婚の場合の氏については婚氏続称という制度がありますが、離縁にもあります。
離縁の場合に離縁前の氏を継続する時は離婚よりも要件は厳しいものとなり、縁組が7年以上継続されている必要があり、離縁の日から3ヶ月以内に届出を行う必要があります。
READ MORE
今日は寄託契約というものについて書いていきます。
「寄託」とは、当事者の一方が相手方のために「特定物」の保管をすることを約束して、その特定物を受け取ることによって効力を生じる契約を言います。保管する者を「受寄者」、預ける側を「寄託者」と言います。
寄託は無償で行う場合と有償で行う場合がありますが、無償で寄託を受けた場合は、"自己の財産に対するのと同一の注意義務"で保管すれば良いとされています。無償の場合は、日常自分の物を管理するのと同じくらいの注意で足りるということです。
一方有償の場合は、"善良な管理者の注意義務"、いわゆる「善管注意義務」を負います。
この2者の違いですが、前者は重過失の場合には損害賠償責任を負いますが、軽過失の場合は責任を負いません。これに対して善管注意義務がある場合は、軽過失でも責任を負うこととなります。
前回委任契約の義務について触れましたが、保管するのに必要な費用については委任の規定が準用され、寄託者に対して請求することができます。なお受寄者は寄託者の承諾なしには寄託物を使用することも第三者に保管させることもできません。無償であっても有償であっても同様です。
寄託契約は寄託物が返還されれば終了します。
返還についてですが、寄託者側は、たとえ当事者同士で返還の時期を定めた場合であっても、いつでも返還を請求することができます。一方の受寄者においては、返還の時期の定めがある場合には、やむを得ない事由がない限り期限前に返還することはできません。
では返還の定めがない場合はどうでしょうか。寄託者はいつでも返還の請求をすることができますし、受寄者においてもいつでも返還することができます。
READ MORE
本日は私のホームページ上に載せている遺言書についてのQ&Aについて書いてみます。といってもQ&Aページのものではなく、遺言を書かれる動機固めのイントロダクションになります。では順番に。Q:遺言書などを書いたら、子供たちにあらぬ詮索をされるかもしれない。今現在円満に暮らしているし、相続の話しで家族の中に波風を立てたくない。A:今現在ご円満だからこそ、円満なまま仲良く暮らしていって欲しいのではないですか。遺言書のことは皆さんに表立ってお伝えする必要はありません。行政書士と相談しながら、最善の方法で作成していきましょう。Q:自分の家族に対する愛情は平等だ。でも今の子供たちの暮らしぶりを考えて、財産の分け方を決めても良いのではないか。いやいや私が決めるよりも子供たちが決めれば良いことではないか。A:相続人当事者同士で、遺産分割が円満に成立する場合ばかりではないようです。お子様にもご家族や関係者が大勢いらっしゃり、お子様ご自身の意思だけで決められるとは限りません。そうなった時には行事役のあなたはその場にはいらっしゃいません。今現在の状況を客観的に判断されて、みなさんを円満にまとめられるのは、あなたを置いて他にはいらっしゃいません。Q:遺言書を書こうとは考えているが、どこから手をつけて良いかわからない。具体的に想いを形にしたいが。A:遺言書は「だれに、何を、どのように」になります。まず遺言書を残されようと思い立った動機をご自身が再確認し、その目的を達成する方法を考えれば良いと思います。Q:健康に不安はないし遺言や相続のことなどまだ当分先のことだから、今考える必要はないかもしれない。A:みなさんそうおっしゃいます。遺言書は別に今書く必要はないものです。ただ、いざという時には遺言を残せないかもしれません。法的効果のある遺言には要件があります。そうならないためにも、もし相続に多少なりともご不安があるのであれば、「思い立ったが吉日」ではありませんか。Q:誰に相談したらよいかわからないし、自分の思いを口に出すのは恥ずかしい。A:遺言書には皆さん、今まで言えなかったご家族への感謝の言葉を残されます。普段は気恥ずかしくて、面と向かってはなかなか言えないものです。でもこれは最後のメッセージになります。形にした時点でご自身の心のつかえもとれるでしょうし、そこから新たなものも見つかるかも知れません。ご遠慮なくお話しいただき、その想いを形にしていきましょう。Q:誰かに依頼すると費用が発生すると思い、ふんぎりがつかない。A:行政書士の報酬や、公証役場の手数料は決して安価なものではありません。むしろ普段の生活の中では高額なものになります。しかし見返りに得られる価値は、決してお金に変えられるものではありません。ご負担になるようでしたらそれはご自分で書かれるのも良し、あくまで判断されるのはお客様ご自身になります。Q:自分で書こうと思ったが、書き方がわからない。自分で書いた場合のデメリットはあるのだろうか。A:このホームページに自筆遺言の書き方も載せてありますのでご一読ください。自筆遺言の最大のメリットは、もちろん費用がかからないことです。簡単に書く事も、書き直しもできます。今回の民法改正によって、自筆遺言のハードルも多少下がりました。デメリットは自筆遺言書自体がトラブルの原因になることです。簡単に書く事ができるために内容の裏付けがなかったり、保管が不十分であったり。ご予算等に合わせれば良いことですが、行政書士へのご依頼のほとんどが公正証書遺言であることもまた事実ですQ:遺言書を書いても保管方法がわからないし、もし相続が終わったあとに出てきたらトラブルのもとになってしまうかも知れない。A:上のご質問同様、自筆遺言の記載を確認ください。民法改正によって自筆遺言の保管や検認手続きなどについては使い勝手が良くなりましたが、多くのトラブルの原因が解消されるわけではありません。Q:遺言書を書いたあとに気が変わるかも知れない。気安く書かない方が良いのではないか。A:もちろん遺言書は気安く書かれるべきものではありません。慎重にご家族の将来を見据えて書かれるものですが、状況が変わることもありえます。そのような場合でも、遺言書は撤回することもできますし、それを破棄して新たなものを作成することもできます。遺言書は常に日付の新しいものが有効となります。Q:遺言書を書いてしまうと、自分の財産を自由に使えなくなるのではないか。A:ご自身の財産は、当然ご自身で自由に処分することができます。遺言書に縛られることはありませんし、日々の生活を見据えて書かれることだと思います。万が一状況が変わって大きな財産を処分することになっても、その際に考えれば良いことになります。ご心配はごもっともです。でもそのご心配を解きほぐし、一歩前にすすんでみませんか。
READ MORE

遺言書がない相続が発生した場合、相続関係を確定させるために関係するすべての戸籍謄本を取得しなければなりません。
被相続人に存命の配偶者とお子さんがいらっしゃれば、1/2の遺産は配偶者の方に権利がありますが、残りの1/2はお子さんで等分します。お子さんといっても現在の配偶者の方のお子様だけではなく、離婚歴がある場合はその方との間にできたお子さん、また非嫡出子でも認知しているお子さんがあればその方、また離縁されていない養子の方も同権利になります。
相続が発生した時点ですでに亡くなられているお子さんがいらっしゃれば、そのまたお子さん(孫)が代襲相続しますので、その方々の戸籍や住民票が必要になります。戸籍を取得する際に併せて「戸籍の附票」というものも取得し、その方が引っ越された履歴を追い、現在ご存命で相続の権利があることを証明していきます。
さて、相続人が被相続人のご兄弟のみの場合は、難易度が一段上がっていきます。前述の場合同様、ご兄弟に知れていない兄弟が存命か確認していく作業が必要になります。これは被相続人のご両親の出生時に遡った(銀行等によっては出産一定年齢等の場合があります)戸籍謄本を取得し、知れていないご兄弟が存命か確認しなければなりません。
その方を含めたご兄弟が亡くなられていた場合は、同様に代襲相続が発生します。ただしお子さんの相続の場合は、代襲者の死亡による再代襲制度がありますが、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められていませんので、それ以下の方は調べる必要はありません。
戸籍取得は場合によっては数10枚に及び、またご兄弟の場合は戸籍を取得し追跡していく権限はありませんので、行政書士にご依頼をいただければと存じます。
READ MORE

前回記事の、共同相続人に成年後見人がいる場合や、行方不明者に財産管理人が指名された場合の遺産分割協議です。
当然これらの者は共同相続人の代理人になりますので、遺産分割協議に参加し、これらの者も含めた全員の合意で協議が成立することになります。
しかしこの成年後見人や財産管理人は共同相続人の権利代弁者でありますので、職責上、決して不利な内容で合意することはありません。
協議の成立に有効な条件であっても、むやみな妥協は代理人の責任問題になりますので、必ず法定相続分以上のものを主張されます。不必要な上積みは要求されませんが、客観的に見て常識的な数万円程度の譲歩しかなされません。
ですので遺言がない相続の場合に、共同相続人間で生前の故人が口にしていた意思とおりに遺産分割が合意されつつある場合でも、このような代理人が介入した場合には、法定相続分を下回る額で合意に至ることは容易ではありません。
READ MORE