成年後見人が代理する遺産分割協議
前回記事の、共同相続人に成年後見人がいる場合や、行方不明者に財産管理人が指名された場合の遺産分割協議です。
当然これらの者は共同相続人の代理人になりますので、遺産分割協議に参加し、これらの者も含めた全員の合意で協議が成立することになります。
しかしこの成年後見人や財産管理人は共同相続人の権利代弁者でありますので、職責上、決して不利な内容で合意することはありません。
協議の成立に有効な条件であっても、むやみな妥協は代理人の責任問題になりますので、必ず法定相続分以上のものを主張されます。不必要な上積みは要求されませんが、客観的に見て常識的な数万円程度の譲歩しかなされません。
ですので遺言がない相続の場合に、共同相続人間で生前の故人が口にしていた意思とおりに遺産分割が合意されつつある場合でも、このような代理人が介入した場合には、法定相続分を下回る額で合意に至ることは容易ではありません。
Related Posts
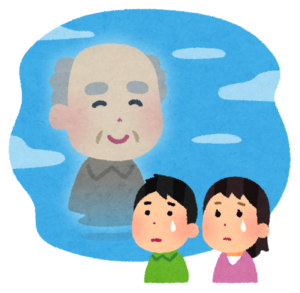
今日は遺言書のない相続について記載します。
■筆者の相続ホームページ
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/
相続は多かれ少なかれ突然発生します。亡くなられた方が長く病で伏せってらしても、そのような状態ではなかなか事前に相続のことまで気が回りません。その方ご自身が相続人の方の今後を考えられて遺言書を作成する場合もありますが、考えている内に遺言書自体を作成する認知能力などが失われてしまいます。
では突然やってきた相続の場合どうすれば良いでしょうか。当面は配偶者やお子さんなどの一番身近な方が死亡届や年金、税金関係など役所の手続きをすませたり、金融機関に連絡をされると思います。当面葬儀などの資金が必要になるでしょうから、必要額を事前に亡くなられた方の口座から引き出しておく必要もあります。
とりあえずの段取を終え落ち着かれたら、次は相続について考えなければなりません。一般的に被相続人(亡くなられた方)の財産には、現金や預貯金の他、不動産があります。その他有価証券等がある場合もあります。これらを相続人全員で協議し、それぞれの取り分を決めなくてはなりません。
まず配偶者の方やお子さんなどの一番身近な方が主導となり、相続人に当たりを付けます。そこから関連するすべての戸籍を取り、並行してすべての財産を探索してまとめ上げます。身近の方が亡くなられてそこまで気が回らないこともあるでしょうが、できる限り早く手を付けることが肝要です。お忙しければ当職のような行政書士などの代理人に依頼することもお勧めします。
なぜ急がなければならないかというと、相続には法律でいろいろな期限が決められているからです。例えば3ヶ月以内にしなければならないことは、財産を相続するか放棄するかの決断です。相続放棄は3ヶ月以内に手続きをしないと、以降は相続放棄ができなくなります。たとえ借金が残された財産より多くても、負債も含めて相続人に法定相続分だけ相続され、被相続人の借金を返済しなければならなくなります。多くの借金が想定される場合には、非常に重大な期限になります。
また逆に相続財産が多い場合も重要な期限があります。それは10ヶ月以内に相続税を納めなければならないことです。期限内でしたら住宅などの特例措置もあります。相続財産が多い方は、出来れば早めに行政書士などの専門家に依頼し、速やかに相続手続きに着手されることをお勧めします。
READ MORE
今日は付言について書いてみます。
「付言」は「ふげん」と読みます。付言とは遺言書に自分のメッセージとして付け加える言葉です。付言自体には法的効果はありませんので、遺言書の方式を満たす要件にはなっていません。しかし多くの方が文面に残されているようですし、行政書士としても基本的にはおすすめをすることにしています。
また書面への付言という形ではなく、別途手紙という形で残される場合もあります。しかしこの場合は公正証書遺言のように公証役場で保管がなされず、またその真偽も定かではないため信ぴょう性が疑われることもあり、お勧めはできません。
付という文字がつくと、付記や追記という言葉が思い浮かんでしまいますが、もちろんこれらのように、後から付け加える(意図的な場合もあるでしょうが)という性質のものではありません。むしろその遺言書を書かれた本来の動機や目的から発する言葉だと考えます。
遺言を残す動機はいろいろあると思いますが、ひとつには自分が苦労して残した財産を、自分の意思で自分の思う通りに配分したいという考えです。これは自分がいなくなっても、その財産を有効に活用することのできる子を中心に相続させたいというような合理的な理由もあるでしょうし、今まで自分にしてくれた行為や与えてくれた愛情への論功行賞的な理由の場合もあるかも知れません。
また例えば子供ごとに異なるそれまでの支援状況も加味した上で、それらを差し引いてそれぞれ平等な相続額にという場合もあるでしょうし、それぞれの暮らしぶりから行く末を案じてということもあるかも知れません。
もうひとつの動機は、自分が亡くなったあとも、相続でもめることの無いようにとの家族への配慮や愛情から発せられるものです。遺言書を書こうか悩まれている方の多くは、むしろこちらの動機が強いのではないかと思います。
でもそのような愛情から発した遺言書も、内要によっては感情的なしこりを残す場合も出てきます。
多くの場合には相続財産は不動産など、簡単に分割できないものになります。また現に今どなたかが住まわれている家も相続財産(生前贈与されていても相続財産に加わります)になりますので、それを相続の段階で分割しようといってもなかなかできることではありません。
遺言書がなかった場合の相続では必ずおこる問題ですが、そもそもそういうゴタゴタでご家族の方に心身の負担をかけたくないという思いで遺言書を書かれたはずです。かといって実際にはその住まわれている家や不動産などの財産を均等に分けることは非常に困難なことですし、多少なりとも偏りが出てしまいます。そこにどなたかの不満がでないとも限りません。
遺言書というものは元来無味乾燥なものです。そこには相続人や相続財産などが淡々と記載されているだけで、ご本人の本来の意思など確認しようもありません。意思を読み取ったり推察することはできるでしょうが、誤解の生まれる余地も多分にあります。ましてや相続分に偏りがあった場合などは、相続分の少ない方からの不満はあって当然だと思います。
財産を偏りなく相続させることはとてもむつかしいことです。不動産が多い場合などはなおさらです。愛情の多い少ないで相続分を考えたのではなく、事情があってしたことであれば、その理由は伝えてあげた方が良いと思います。
付言はご自分の感情を伝える最後の方法であるとともに、ご遺族の方にとっても、あなたのご意思を知る最後の機会に違いありません。
最後にひとつ。くれぐれも愚痴や恨み言は残さないようにしましょう。
ご家族が円満に相続を終えていただくためにも、あなたが遺言書を書かれた動機や意図を伝えることが重要になります。付言とはそのときそこにいないあなたに代って、そのメッセージを伝える役割を担っています。
http://yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry21.html
READ MORE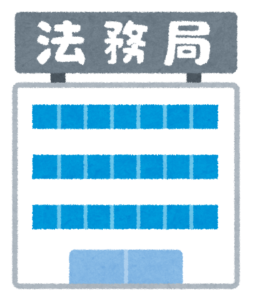
今日は相続に関して、法定相続情報証明制度について書いていきます。平成29年5月29日から開始された制度です。
相続は被相続人の死亡によって開始しますが、遺言書があった場合は基本それに基づいて相続が執行されます。遺言書がなかった場合は相続人全員で遺産分割協議を行ない、それぞれの配分財産を決めます。相続財産はだいたい現金預貯金や不動産といった形をとりますので、当然管理も預貯金であれば金融機関、不動産であれば法務局が行うこととなります。
契約者や名義人は亡くなったとはいっても被相続人ですので、仮に相続人であるからといって、簡単に払い戻しや手続きには応じてくれません。金融機関であれば被相続人の死亡したことを通知した時点をもって口座が凍結され、たとえ相続人である子が葬儀費用が必要だといった場合でも払い戻しには応じてくれません。
この場合は葬儀費用はとりあえず自分たちで別途捻出し、相続関係を確認できるすべての者の戸籍謄本(被相続人の出生からさかのぼったものが必要です。相続関係一覧表にしてあることが望ましいです)や財産目録等を提出し、種々の手続きを行って初めて相続の払い戻しに応じてもらえます。
法務局においても、相続後の土地や家屋についての名義変更を行うためには、同様の戸籍すべてが必要になります。また戸籍が必要である金融機関等が複数ある場合には、戸籍謄本をその数分取得するか、あるいは1機関ごとに提出と返還を繰り返すことになります。
これらの作業を相続人が行うことは非常に煩雑で手間のかかることになりますので、土地の名義変更や登録を行わない者が出てきます。相続後に登記をしないことについては法律で罰則が設けられていないことから、名義人の不明な土地や家屋が散在することとなり、いまや社会問題にもなっています。
法定相続情報証明制度とはそういう戸籍の提出をまとめて出せるようにし、提出と返還の作業を繰り返さなくても良いように設けられた制度です。具体的には、戸籍一式を揃えて法定情報一覧図を作成し、法務局からその一覧図の写をもらいます。法務局や他の金融機関でも、その一覧図の写の提出のみで手続きが行えるというものです。
相続人や代理人等が法務局に申請を行いますが、申請できる法務局は被相続人の本籍地か最後の住所地にある法務局、あるいは請求人の住所地にある法務局か被相続人名義の不動産がある場合はその所在地の法務局になります。
メリットは相続人本人が申請を行う場合には、それなりに手数が省けるということになります。しかしまだ開始後間もない制度であるため、現時点では使い勝手が悪い点もあります。たとえば再交付が必要になった場合では、申請人本人によって申請をした法務局に申請を行わなくてはならない点です。
他の相続人が行う場合には、都度申請者の委任状が必要になります。またこの制度は戸籍謄本の情報をまとめる目的だけであるため、相続放棄や欠格等の情報は網羅されていません。それらの情報が必要な場合は、結局別の資料を用意することになります。
もっとも前述の提出と返却の件ですが、基本的に行政書士が銀行に代理で手続きを行っても、提出した書類はその場でコピーし返却されますので、実務上はあえてこの制度を使うメリットは少ないと考えます。大元の目的が相続不動産の登記促進であるならば、いずれにしても法律面での規制等、抜本的な方策が必要なんでしょう。
READ MORE
今日は相続の取りすすめ方について書いていきます。
相続は被相続者が亡くなった時点から、被相続人の自宅において開始します。相続を取りすすめていく者(執行人)については、配偶者や子などがいる場合はわかりやすいですが、通常は相続人の中で相続額の大きな、主だった者が中心となって相続を進めていきます。
相続が始まったら、まず遺言書を探します。遺言書が見つかった場合には、その遺言書の方式が自筆であるかそれとも公正証書によるものかを確認します。
遺言書が自筆証書遺言書であった場合は、必ず封を開けずにまず家庭裁判所に「検認」を申請しなければなりません。家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所となります。身近な相続人であれば他意はなくとも中身を見たくなるのは人情でしょうが、勝手に封を開けてしまうと法による罰則が規定されており、5万円以下の過料に処せられることになります。
またこの時点でのうっかりで止まっていれば相続人としての資格に問題はありませんが、つい出来心であっても、遺言書を自分に有利なように書き加えたり廃棄してしまったりした場合は、その者は欠格者として法律上当然に相続人としての地位を失ってしまいます。決して見つけても開封してはいけません。
万が一開封してしまった場合にも、「検認」手続きは必ず受けましょう。検認手続きを受けて「検認済み証明書」を取得しておかないと、金融機関からの払い戻しや法務局での不動産の名義書換などが行えません。
では家庭裁判所における「検認」とはどのようなものでしょうか。
相続人から「検認」の申請が出された場合は、家庭裁判所はわかっている相続人全員に、期日を決めての出頭文書を送ります。そしてその期日に出頭した相続人全員立会のもと、遺言書の開封を行います。提出された遺言書について、検認日においての遺言書の形状や加除訂正の状態・日付・署名、内容等が確認されます。内容が正しければ相続人全員同意のもと検認の効果が確定します。そして当日立ち会えなかった相続人には、その旨の連絡がいきます。
しかし検認自体の効果については、その遺言書が適正に書かれたものであり、かつ相続人立会のもとに確認したものであるという証拠保全の手続きとしての性質を持つものであって、内容自体についての可否や整合性を保証するものではありません。
行政書士や公証人とのやりとりの中で調製されたものではないため、その内容が偏っていたりあるいは財産内容等があやふやである場合には、あらためての協議が必要になることもあります。また内容によっては被相続人自身の自筆であることの証明が必要になる場合や、あとに書かれた遺言書がないかの探索等が必要になる場合があります。
一方、遺言書が公正証書遺言であった場合には検認の手続きも必要なく、内容的にも妥当なものがほとんどであるため、概ね遺言書のとおりにスムーズに相続が進んでいきます。遺言書の内容の確認と事務的な段取が主体となり、分配内容による葛藤がないではないにせよ、比較的短期間で相続が完了することが通常です。
いずれにしても相続に関しては、法的に効果のある遺言書があった場合は、ほとんどは遺言者の意思に従って行われます。公序良俗に反したものであったり遺留分を侵害していたりする場合を除けば、遺言者の意思を尊重するということになります。
しかし遺言書の効力が100%であるかといえば、そうとばかりはいえません。たとえ遺言書があったにしても相続人全員の協議が整えば、そちらの協議を優先することも構いません。ただし遺言書に指定された、行政書士等の遺言執行人がいる場合は、その者との協議も必要になります。被相続人との契約を執行する義務がある者との調整をすることが、最終的な相続の方法を決める有効な方法かと考えます。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry19.html
READ MORE
今日は本題の普通方式の遺言について書いていきます。通常作成される遺言のほとんどはこの普通方式になります。
普通方式には「公正証書遺言」「自筆証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類がありますが、公正証書遺言は平成29年には110,191件作成されており、年々増加しています。それに対し秘密証書遺言の作成は、わずか130件にとどまります。
一方、自筆証書遺言については裁判所が受理した「検認」数でしか確認することはできませんが(2年以内に法務局による保管制度が開始されます)、その数は16,708件にとどまります。
新規作成された件数と相続が開始した件数とで比較対象が異なりますが、昨今は遺言の役割が理解され始め、手近な自筆証書遺言が作成される機会が相当増加していると思われます。すでに公正証書遺言の作成数を上回っているとさえ言われている中で、自筆証書遺言による方式の不備や内容の偏りや不明確さによるトラブルも危惧されています。
先に触れてしまいましたが、それではそれぞれの種類について、作成方法やメリット・デメリットについて見ていきましょう。
先に書きました、民法に規定される「普通方式」の遺言については、3種類の方式が定められています。各方式、厳密な作成ルールが規定されており、内容に不備があると法的効果が得られないことになります。3種類の方式は、①自筆証書遺言(民法968条)②公正証書遺言(同969条)③秘密証書遺言(同970条)になります。
まず①の自筆証書遺言について見ていきましょう。
「自筆証書遺言」の作成方法は、いたってシンプルです。遺言者本人が、遺言書の全文、日付および氏名を自書し、捺印して作成します。
全文には財産目録などすべてを含みますが、今回の民法改正によって、平成31年1月13日から目録については自書でなくても良いことになりました。財産が多い場合などは書く事が負担であった財産目録は、パソコンなどで作成しても良いことになります。時流に合わせた改正になりました。
ここで言う自書とは文字通り遺言者みずからが自分の手で記述することをいい、口述であったり他人が手を添えることも原則認められていません。
日付については、明確に作成した当日の日付を自書します。西暦であっても元号であっても構いませんが、日付印であったり特定されない日付、例えば9月吉日等の場合は無効となります。判例からは、遺言者自身の70歳の誕生日に書いたとか、11月末日に書いたという記載があれば、それは自書した日を特定できるということになります。
遺言は撤回することも書き直しすることも自由にできます。しかし法的効果を有する遺言が複数見つかった場合は、内容が矛盾する部分については必ず後の遺言が有効になります。ですので、遺言が書かれた日付というものが極めて重要になるのです。
次の氏名については、これも当然自書しなければなりません。しかし氏名は戸籍上の氏名である必要はなく、遺言者が誰であるか疑いのない程度の表示がなされていれば良いこととされ、ペンネーム等の通称でも問題ありません。また氏や名のどちらか一方のみであっても、他人との混同が生じない場合には有効とされます。これらは民法に直接の記載はありませんが、判例から確認されます。厳密な規定と言いながら腑に落ちない部分ではありますが、余計な問題を起こさないように、必ず自分の本名を自書するようにしましょう。
次は押印についてです。印を押す場合には捺印という言葉も使われますが、雑学として、一般的には自分で書いた名前(自書)に印を押す場合は「捺印」、自書以外に印を押す場合は「押印」と言うようです。「押捺」という場合には拇印も含むようです。ここでは名前に印を押す場合ばかりではないので、「押印」という言葉を使います。
押印する印については実印を押すという規定はないため、いわゆる認印や拇印でも良いとされています。しかしトラブルを防ぐ意味からも、実印や銀行印で押印することをお勧めします。
押印する場所も特に決まっていないので、どこに押しても構いませんが、やはり自書した上か横に押すのがセオリーでしょう。どちらにしても遺書本紙に押印することが必要で、封印した封筒のみへの押印は無効になります。
ここでもう一つ問題になることは、遺言が複数に渡った場合の押印は、各紙面に必要かどうかということです。通常契約書などの場合は、例えば1枚目と2枚目のあいだに後から作成された用紙が差し込まれないように、1枚目と2枚目のつなぎ目に「契印」というものを押します。「契印」は1枚目と同じ印を使用します。ここもトラブルがないように、契印を押しておきましょう。
次に訂正があった場合の方法について説明します。「加除訂正」と言いますが、遺言書の加除訂正の要件は、
①遺言者自身によりなされること
②変更の場所を指示して訂正した旨を付記すること
③付記部分に署名すること
④変更箇所に押印すること
です。
余白に文言を後から付け加えた場合もこの方法に則ります。この加除訂正の方式に間違いがあった場合は、その加除訂正自体が無効となりますが、遺言書全体は当然無効にはなりません。加除訂正される前の元の内容が判別できれば元の内容が生きることとなり、判別不能な場合はその部分が一切記載されていないものとして扱われます。
加除訂正は非常に面倒な手続きですし、誤りも発生しやすいものですので、変更等がある場合は新たに書き直された方が良いと考えます。またその際はトラブル防止のために、必ず前の遺言書は破棄しましょう。なお自筆証書遺言は日本語に限られず、外国語で作成することもできます。
READ MORE
遺産分割協議に請われて立ち会うことがあります。当然交渉に関与したり、協議自体に関わることはありませんが、相続人や財産関係等で差し支えない部分については、調査した内容などにお答えすることになります。公正証書遺言があればその内容にしたがって相続を行っていけばよいですし、遺留分が発生する場合は、問われれば遺留分減殺請求権(7月1日からは遺留分侵害額請求権)についてご説明することになります。
相続人が配偶者とその子たちであって、特段不仲でなければ代表相続人の方(通常は配偶者の方か高齢であれば長男等)がリードして、あうんでそれぞれの相続分を決めていかれることになると思います。通常は相続人がたとえ少人数であっても単独相続でない限りは、不動産登記や銀行の払い戻しに、「遺産分割協議書」「財産目録」「相続人関係説明図」を求められます。
まず相続財産をキチンと整理して財産目録を作成します。ここではプラスの資産だけでなく、負債などのマイナスの資産も明確に調査する必要があります。借金をしていた可能性があるのに単純に相続をしてしまいますと、負債の方が大きいマイナスの相続になってしまいます。
マイナスの相続の場合は、3ヶ月以内に相続放棄の手続きをとれば、負債を含めた一切の遺産相続を放棄することができます。3ヶ月というのはここで重要な期間になってきます。もし安易に一部の財産を処分してしまったり、3ヶ月を過ぎてしまいますと、「単純承認」をしたことになり、もう相続放棄をすることができなくなり、負債の一切も相続人全員で返済する義務が生じてしまいます。遺産相続を受けるかどうかの判断材料とすることが、「財産目録」を作成することの目的のひとつになります。また相続人全員で合理的に遺産分割するための判断材料になる書類でもあります。
次の「相続関係説明図」とは、法定相続人全員の相続関係を証明した一覧になります。遺言書がなければこれを基に各自の相続分を調整していきますし、遺言書があれば遺留分算定の基礎となります。相続税には基礎控除というものがありますが、ここで法定相続人の人数を確定しませんと、控除額を確定することもできません。
また調べなくても明らかに法定相続人が確定できる場合は大きな問題はないですが、被相続人が離婚をしていた場合や人間関係が複雑な場合には、戸籍を厳格にたどって相続人を確定しておきませんと、後からあたふたする事態となります。
普段わかっている相続人以外に相続人がいる場合(離婚した妻との間にできた子や認知した子など)は、相続人の特定をしっかりしておかないとトラブルの原因になります。いいわいいわで現在生活している親子だけで相続をしてしまうと、後からそれらの相続人が現れた場合には相続のやり直しになってしまいますので注意が必要です。もっとも登記や払い戻しの際もすべての戸籍謄本も求められますので、相続人の確定は必須になります。「遺産分割協議書」と併せ、過去ブログやホームページで確認下さい。あとは後編に記載します。
READ MORE
今日は贈与というものについて書いていきます。
贈与は遺言相続の場面でも多く出てくる言葉であり、私のホームページでも説明を記載していますが、今回はそのもとになる民法の規定について見ていきます。
「贈与」とは、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方がこれを受諾することによってその効力が生じるものです。贈与も民法の定める典型契約(贈与契約)になりますが、契約と言っても贈与者が受贈者に無償で財産的利益を与えるという合意のみで成立する契約になります。
これは書面でなく口頭ですることもできますし、契約締結時に目的物を交付する必要もありません。また無償であげるのですから、贈与者はこれに瑕疵があっても担保責任を負うことはありません。最も瑕疵があることを知っていながらこれを受贈者に教えずに贈与した場合には、担保責任を負うことになります。
贈与は書面ですることを要しませんが、書面によらない贈与の場合は各当事者が自由に撤回することができます。書面によらないものならば、それほど重要な契約ではないでしょうということです。裏を返せば贈与も契約であるのだから軽々に口約束にせず、書面によって権利移転の意思を明確にし、トラブルを防止する措置が必要ですよということです。
しかし自由に撤回できると言っても、既に動産の引渡しが完了していたり不動産の引渡しや登記が完了しているといった、履行の完了している部分については撤回することはできません。
これは遺言の記事でも書いていますが、贈与には次の特殊なものもあります。
①負担付き贈与
②死因贈与
③定期贈与
です。
「負担付き贈与」とは、受贈者に贈与の条件として一定の義務を負担させる贈与契約になります。例えば、私が生きているあいだは私の看護をする、ことを条件に贈与を行なう場合などです。贈与者は受贈者の負担の限度において担保責任を負うとされていますので、負担が履行された場合には必ずその贈与が行われることとなります。
「死因贈与」とは、贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約になります。似たようなものに「遺贈」がありますが、遺贈は被相続人の一方的な単独の意思表示となりますので、贈与契約とは趣旨が異なります。
しかし性質自体は似ているものになりますので、遺贈に関する規定は準用され、贈与者はいつでも一方的に贈与契約を撤回することができます。対して受贈者はこれを放棄することはできません。
「定期贈与」とは、一定期間ごとに無償で財産を与えるという契約になります。定期贈与は当事者同士の個人間の関係性によるものですので相続はされず、当事者の一方の死亡によって効力が失われることとなります。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry65.html
READ MORE
遺言書がない相続が発生した場合、相続関係を確定させるために関係するすべての戸籍謄本を取得しなければなりません。
被相続人に存命の配偶者とお子さんがいらっしゃれば、1/2の遺産は配偶者の方に権利がありますが、残りの1/2はお子さんで等分します。お子さんといっても現在の配偶者の方のお子様だけではなく、離婚歴がある場合はその方との間にできたお子さん、また非嫡出子でも認知しているお子さんがあればその方、また離縁されていない養子の方も同権利になります。
相続が発生した時点ですでに亡くなられているお子さんがいらっしゃれば、そのまたお子さん(孫)が代襲相続しますので、その方々の戸籍や住民票が必要になります。戸籍を取得する際に併せて「戸籍の附票」というものも取得し、その方が引っ越された履歴を追い、現在ご存命で相続の権利があることを証明していきます。
さて、相続人が被相続人のご兄弟のみの場合は、難易度が一段上がっていきます。前述の場合同様、ご兄弟に知れていない兄弟が存命か確認していく作業が必要になります。これは被相続人のご両親の出生時に遡った(銀行等によっては出産一定年齢等の場合があります)戸籍謄本を取得し、知れていないご兄弟が存命か確認しなければなりません。
その方を含めたご兄弟が亡くなられていた場合は、同様に代襲相続が発生します。ただしお子さんの相続の場合は、代襲者の死亡による再代襲制度がありますが、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められていませんので、それ以下の方は調べる必要はありません。
戸籍取得は場合によっては数10枚に及び、またご兄弟の場合は戸籍を取得し追跡していく権限はありませんので、行政書士にご依頼をいただければと存じます。
READ MORE
今日は認知について書いていきます。認知は相続にも関係してくる分野になります。
配偶者を除き、相続人の第一順位は子になります。だんなさんが亡くなられていざ相続だという場合に、奥様と同居している成人のお子さんが3人いた場合には、通常はこの4人が相続人ということで相続の手続きを済ませることでしょう。
しかし相続を終えた後に、認知された非嫡出子が現れ、相続がやり直しになる場合があります。「嫡出子」とは法律上婚姻している夫婦間に生まれた子供を言い、「非嫡出子」とは法律上婚姻関係にない者の間で生まれた子になります。
この非嫡出子ですが、相続に際しては関わりを持ってくる場合があります。お子様たちとは血縁関係があることでしょうが、相続においては認知されているかいないかが重要な意味を持ってきます。認知されていなければ相続に関わりをもちませんが、「認知された非嫡出子」の場合は、相続権のある子になります。
「認知された非嫡出子」も他の子と同等の立場になりますので、遺言書のない相続の場合には、必ず戸籍をたどって相続関係を明らかにしておくことが重要になります。
では認知について見ていきましょう。前述した通り、「非嫡出子」とは婚姻関係にない男女間に生まれた子(婚外子)を言います。法的には婚姻関係にない内縁の妻との間に生まれた子も、家族が知らないいわゆる愛人との間に生まれた子もともに「非嫡出子」となります。
通常の婚姻関係にある男女間に生まれた子は「嫡出子」と言います。「非嫡出子」はその親との間に法律上の親子関係はありませんが、「認知」されると法律上の親子関係が生じます。
「認知」とは、非嫡出子の親が、その非嫡出子を自分の子として認める行為を言います。認知は生前に行うこともできますし、遺言で行うことも認められています(遺言認知)。また認知とは通常は父子関係における行為であり、母子関係においては分娩の事実により親子関係が当然に発生しますので、認知は不要になります。
認知により認知された非嫡出子は、父親との相続関係が認められることになります。法的に血族関係が認められ法定相続人になります。
たまにドラマなどで、愛人との間に生まれた子を、子供のない自分たちの実の子、非嫡出子として届け出るストーリーがあります。この場合はどうなるのでしょうか。
養子以外の子には血縁関係が必要となりますので、血縁関係のない戸籍上の妻の嫡出子となることはありません。不正の届出となり、事実が判明すれば嫡出子であることは否定されます。ただし判例からは「認知」の効果が認められ、認知された非嫡出子となります。
認知について話を戻します。「認知」には次のものがあります。
①任意認知
②強制認知
です。
では「任意認知」とはどのようなものを言うのでしょうか。
「任意認知」とは、父が自ら役所に「認知届」を提出して行う方法になり、遺言による方法も認められます。また認知は身分行為になりますので、未成年者や成年被後見人であっても、法定代理人の同意なしにすることができます。
なお任意認知は自らの意思ですることが必要になりますので、認知者の意思に基づかない認知届けは無効になります。
認知には次の例外を除き、子の承諾は不要です。認知に子の承諾を必要とする場合は次のとおりです。
①成年の子を認知する場合は、本人の承諾が必要になります
②胎児を認知する場合は、その母親の承諾が必要になります
③成年者の直系卑属(孫等)がいる、死亡した子を認知する場合は、その成年である直系卑属の承諾が必要になります
「強制認知」とは、父または母が認知をしないときに、その子や直系卑属が裁判により求めるものになります。ただしこれは父または母の死亡から3年以内にする必要があります。
任意認知も強制認知も、その効果は子の出生時にさかのぼって親子関係が生じます。この際も、第三者が既に何らかの権利を取得している場合には、その権利を害することはできません。
最後に「準正」について付け加えておきます。
「準正」とは、非嫡出子を嫡出子にする制度を言います。準正の要件は、「認知」+「婚姻」になります。認知により相続権が発生しますが、あくまでも「認知された非嫡出子」であることには変わりありません。これを嫡出子に変える制度になります。
「準正」には認知と婚姻の順序によって2つのパターンがあります。
①婚姻準正
②認知準正
です。
「婚姻準正」とは、認知が確定した後に父母が婚姻した場合で、婚姻の時から準正が発生します。
「認知準正」は婚姻をした父母が認知をした場合で、認知の時から準正が生じます(この場合も実務上は婚姻の時からとされています)。
順番はどちらであっても、準正が生じた子(準正子)は、嫡出子の身分を取得します。なお現在の民法では、相続においても嫡出子と認知された非嫡出子の相続分は変わりませんが、改正前は差がありましたので、この準正の手続きはより重要なものでした。
READ MORE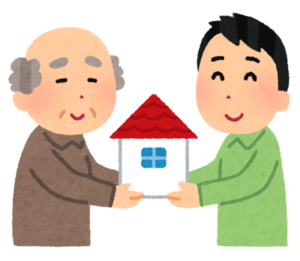
今日は遺贈と死因贈与について書いていきます。
相続は相続人にしかすることができません。そもそも相続とは、被相続人が亡くなった場合に、法律で決まっている者に財産を承継させる制度です。相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のみと民法で決まっており、これらが決められた順位で相続できるのみです。
もしこれらの者が一人もいない場合は、相続財産を管理する者として家庭裁判所から弁護士等が選任されることとなります。そこで本当に相続人がいないかの調査がなされ、それでも見つからない場合には家庭裁判所に認められた場合に限り、被相続人の世話を相当程度した者が一部の財産を譲受けることができます。それらが完了すると、最終的には財産はすべて国庫に帰属することとなります。
さて、相続人がいるいないにかかわらず、あなたがとても世話になった方がいるとします。その方の恩に報いるにはどうしたらよいでしょうか。ここからの話は相続人についてもすることができますが、相続人の場合は「寄与分」ということで、相続人間の協議において相続分の上乗せをすることができますので、ここでは除いて話を進めます。
あなたがもし遺言書を残さないで亡くなった場合には、相続人全員で相続財産の分配についての協議を行うことになります。この場合は参加できる相続人は当然法律によって定められた者のみ(あとで述べる包括受贈者を除いて)となりますので、たとえあなたがとてもお世話になり、心情的に財産を分け与えたい方でもそこには加わることはできません。
たとえば同居しているお子さんのお嫁さんなどがこれに当たります。ですのでもし相続以外で財産をあげたい場合は、あなたのその意思を明確に残す必要があります。当然法的効果のあるものでないと、他の相続人から否定された場合には、その者も権利を主張することができなくなってしまいます。ここで効果を発揮するものが一般的には遺言書ということになります。
遺言書によって相続人以外の者(相続人にもすることができますが)に財産を与える場合には、「遺贈」という形をとります。これはあなたがその方に対してする、一方的な単独行為になります。自分が死んだらその者に財産をあげるという内容になります。一方的な行為ですので、遺贈する者に事前に伝える必要はありません。
遺贈とは別にもうひとつ、相続によらずに死亡を契機として財産を与える行為に、「死因贈与」があります。これは財産をあげる者とあらかじめ契約を交わしておき、自分が死んだらあげるというものです。契約といってもこれには特に方式はなく、契約書等も必要ありません。口約束だけでも効果を発揮します。しかし、証拠がない場合はトラブルのもとになる場合もあります。もし死因贈与をする場合には、文書等に記しておくことも考えたほうが良さそうです。
死因贈与は遺贈と異なり、あなたの亡くなる前から相手の方もその内容を承知していることになります。ここで別に遺言書が残されており、そこに書かれていた内容がその死因贈与契約と異なっていた場合はどうなるのでしょうか。
この場合は遺言書の効果と同様に、後からされたものが有効となります。遺言書の書かれた日付が後であれば、遺言書によって前の死因贈与契約が破棄されたこととなりますので、死因贈与契約は無効となります。逆も然りです。このように日付等の証拠の裏付けが必要になる場合もありますので、本当に必要な死因贈与の場合は、口頭ではなく文書で日付等を明記しましょう。この2つについて次回詳しくみていきます。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry65.html
READ MORE
コメントはまだありません
