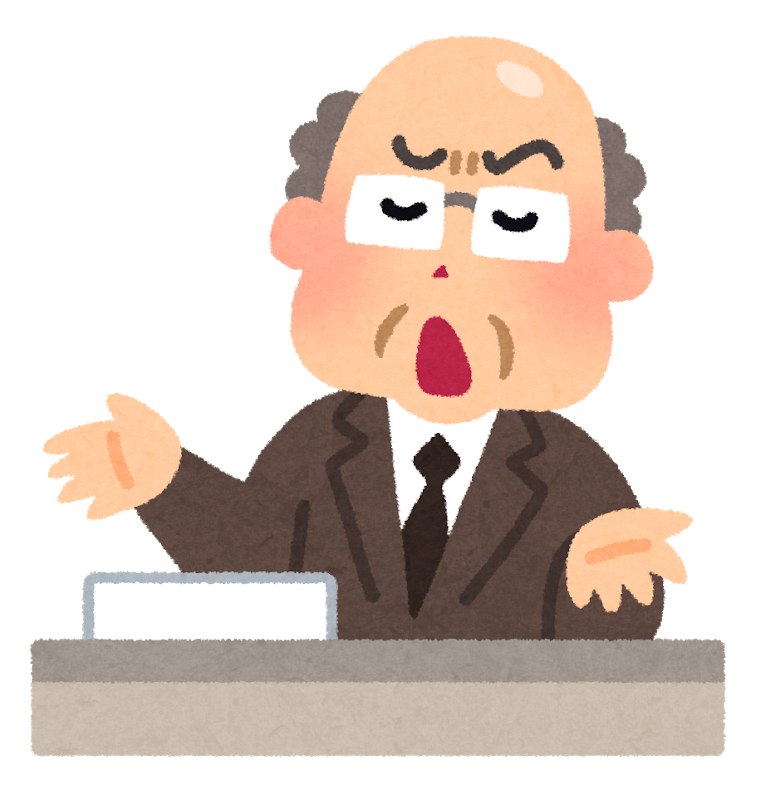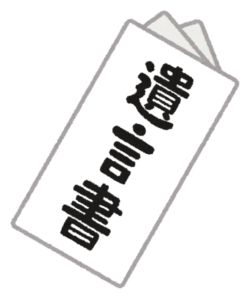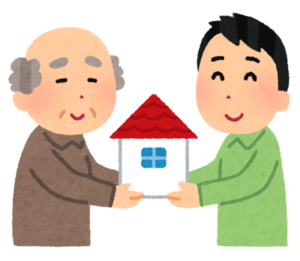今日は自筆証書遺言のメリット・デメリットについて書いていきます。
自筆証書遺言については手軽に書く事ができますので、一般的な遺言書としてまず思い浮かぶのは自筆証書遺言になると思います。この手軽さこそが諸刃の剣として、メリット・デメリットを生むことになります。
まずメリットについて見ていきましょう。自筆証書遺言のメリットは、
①自分ひとりで手軽に作成できる
②作成に費用がかからない
③遺言書の内容を秘密にしておける
シンプルですが、これらのメリットに尽きます。逆に言うと十分な知識があって、保管や亡くなった後の手続き等も万全な体制を取ることができれば、自筆証書遺言で作成することはメリットが大きいと思います。
デメリットはこれと裏腹になります。自分ひとりで作成することによるリスクが大きなものとなります。デメリットは、
①要件が厳格であり、書き方を間違えると法的効果を生じない
②遺言者の死後遺言書が発見されないおそれがある
③遺言書を一部相続人により破棄、改ざんされるおそれがある
④遺産分割協議後に発見され、協議がやり直しとなる
⑤相続人が必ず家庭裁判所に「検認」手続きを行わなくてはならない
⑥本人が作成したことの証明がむつかしく、遺言書の内容の信ぴょう性が疑われる
⑦自筆である証明がむつかしい
⑧遺言書の内容が曖昧であったり、法律的な疑義が生じるおそれがある
⑨遺言書の内容が偏ったものになるおそれがある
等です。
これらはあくまでトラブルを起こす可能性を秘めていることであり、必ずしも起こるものばかりではありません。しかし発生した場合には遺言書が無効となるばかりではなく、遺言書の存在自体が相続人にとってとんでもない迷惑を掛けることになります。
基本的には、遺言者がひとりで書く事によるリスクになります。ひとつひとつ見ていきましょう。
①については要件が極めて厳格であり、方式を間違えると遺言書自体が法的に無効になります。この場合は相続人全員が遺言者の意思を汲んでくれれば良いですが、相続人がひとりでも反対すれば、遺言書は無効とされます。遺言者の意思は反映されず、相続は遺言書がなかった場合の遺産分割協議が行われることになります。加除訂正の際の方式不備についても前回記事に書いたとおりになります。
次の②ですが、自筆遺言書は現状は保管制度がないため、基本ご自分が保管することになります。一般的にはご自宅や銀行の貸金庫等に保管されますが、これが発見されない場合があります。遺言書のない相続の場合は、相続人の方がまず遺言書を探しますが、見つからない場合は遺言書がなかったものとされます。相続人側から見れば当然そう考えます。
③では遺言書が見つかった場合でも、その見つけた者によっては、悪意で破棄したり改ざんしたりする可能性も否定できません(破棄や改ざん等が判明した場合は、その者は欠格者として相続人の地位を失います)。
④では、探しても見つからなかった場合は相続人全員で速やかに遺産分割協議を行い、各相続人の相続分を決めます。これには相続人全員の合意が必要ですのでやっかいなものになりますが、万が一後から法律効果のある遺言書が出てきた場合には、これまた厄介なことになります。遺言書によって有利な相続をされる者がいた場合は、その者の請求によって相続がやり直しになる可能性があります。
なお平成30年7月に相続遺言に関する改正民法が成立し、平成30年7月13日に交付されました。これによって新たに、法務局での自筆証書遺言書の保管制度が設けられ、公布の日から2年以内に施行されることになります。
詳細な内容は現時点では詰められていませんが、自筆証書が法務局に保管される制度であり、「検認」手続きも不要になります。これによって前述の②③④の問題解消が期待されます。⑤についても同様で、保管された自筆証書遺言については、相続人に負担の大きい「検認」制度が適用されないこととなりました。
では⑦についてはどうでしょう。自筆である限りついてまわる内容ですが、実際に筆跡鑑定には専門家が鑑定しても困難があるようです。疑義を持つ者がいた場合には裁判で争われることもあり、近年では有名な事件で本人直筆であることが覆されたこともあるようです。
⑧および⑨については、本人がひとりで書く事によるトラブルです。法律を知らなかったり、感情が偏ったりしていた場合に起こり得る問題です。これらは専門家に作成を協力してもらうことで解決することはできます。
以上、自筆証書遺言についてはメリット以上にデメリットが大きく、トラブルが起こった際には、良かれと思って遺言書を書かれたこと自体が迷惑になってしまう場合もあります。
自筆証書遺言のメリットは大きなものですので、作成を否定するものではありませんが、作成する場合はくれぐれも慎重を期すことをアドバイスするとともに、できれば専門家の手を借りることが賢明であると付け加えておきます。
Related Posts
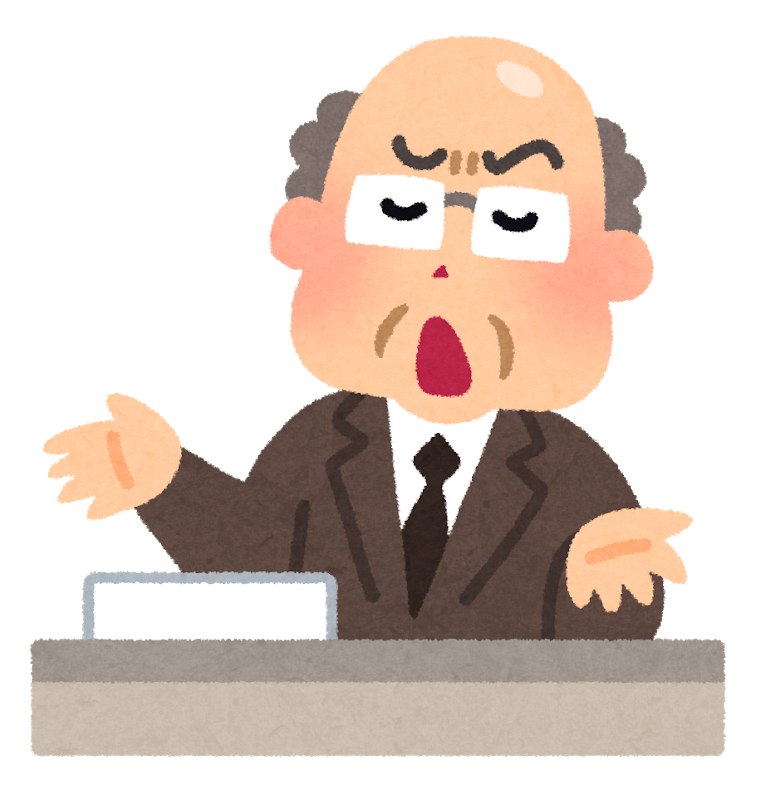
前回は遺産分割協議について触れましたが、相続人が少人数で関係も良好な場合は大きな問題になることはそれほど多くはありません。各自がそれぞれの立場も理解できており、またその後に直系の相続も発生することも想定できるからです。
しかし相続人同士が仲が良くなかったり、金銭関係が良好でない方が居る場合は途端に状況が変わってきます。また相続人が多かったり、相続人が兄弟のみで代襲相続が発生している場合などは特に問題がある場合が多くなります。よく「相続」は「争族」だとも言われますが、くれぐれも「争族」にならないように気をつけなければなりません。
多くの方は「うちに限って心配はない」と言われますが、そんな場面ばかりではないようです。親子関係、兄弟姉妹の関係は悪くはなくても、その方々の身内や関係者による口出しがある場合があります。またちょっとした言葉がきっかけで、一気にかたくなになってしまわれる方もいらっしゃいます。
相続というものは場面も場面でありますし、金額の多い少ないにかかわらず無条件でお金がもらえる機会になります。人情として気にならないはずはありません。通常は相続人が複数いらっしゃる場合は、相続分の一番多い方(配偶者など)や、一番しっかりされている方が代表相続人になられます。この方がしっかり方向性を決め、意見をまとめていきませんととんでもないことになります。協議がまとまらず、事案が法定にもちこまれることになりかねません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないとまとまりません。たとえ相続分の少ない方であっても、その方が合意しない限りは協議は成立しません。ですので代表相続人の方は仲の良い方だけをまとめるのではなく、対応しにくいとんでもない共同相続人にも事前にしっかり皆さんの意向を説明し、協議前に大方の合意にこぎ着けていく必要があります。
そのためにも事前にしっかりとした遺産分割協議書案を作成し、当日は全員の実印をもらえるような段取りで協議に臨みましょう。トラブルメーカーはどこにでもいます。そういう方も直視して、期限内に円満な相続を終えましょう。
READ MORE
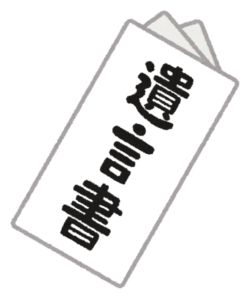
相続分野の民法の一部改正が7月1日に施行されます。
それに先立ち、本年1月13日に自筆証書遺言書の方式緩和(自書以外の財産目録可)の改正民法が施行されました。これは、財産目録について、従来は手書きでないと認められていなかった要件を、銀行通帳等を添付すればパソコンや自分以外の他者の作成によるものでも認めるという内容になります。
ニュースでも流れたのでしょうか、当職のホームページの当該ページへのアクセスも、2-3ヶ月にわたって通常月の1.5倍ほどに上がっています。相続に比べると遺言ページへのアクセスは多くないのですが、普段意識していなくてもニュースになると興味がわくのでしょうか。そのままご依頼いただけると、なおありがたいのですが。。いつかご依頼いただけることをお待ちしております。
さて要件緩和によって自筆証書遺言の作成については多少ハードルは下がりましたが(財産の多い方はなおさら)、そのほかの自筆遺言の要件についての知識はまだまだ低いようです。もちろんご自身で時間をかけて勉強し、ご自分で書かれる方もいらっしゃると思いますが(最大のメリットは費用面ですが)、要件不備で遺言書としての法的効果がなかったり、相続人にかえって迷惑を掛ける自筆証書遺言の多いことも確かです。
もちろんご自身はよかれと思って書かれている訳ですが、中途半端な知識で書かれるため、法律要件を満たしている遺言書は必ずしも多くはないと思われます。日付間違いや誤記などのケアレスミスの場合、あるいは署名の不備等の場合は相続人の方々の合意があれば大きな問題はないと思いますが、これとて訴訟になった場合は認められない場合も多くなります。
一番困るのは、相続人や相続財産の特定が曖昧な場合です。例えば、「預貯金を子供3人に等分に」という記述であれば、単純に分割することは可能ですし、銀行もその記述をもって払い戻しに応じてくれると思います。しかし、「不動産を子供3人に平等に」という文言であれば、どの不動産をどのように分割するのか特定できませんので、不動産登記は難しくなります。この場合は遺産分割協議によって具体的に不動産を分割し(あるいは特定の相続人に単独に)、分割協議書に明記する必要が出てきます。
この遺言書の場合も相続人の皆さんが不仲でなく、遺言者に寛容であれば遺言書の文言に則した形で協議は行われるのでしょうが、えてしてその遺言によって利益を受ける者は拡大解釈でその文言を了とし、利益を害する者は断固反対する。そのような事態も決して少なくはないでしょう。
このような遺言書があった場合は意見が分かれる、あるいは協議の前段部分で時間を取られる弊害が大きくなります。また協議が成立しても後々までの遺恨の原因になります。
自筆証書遺言を書かれる場合でも必ず専門家に指導を仰ぐ、あるいは公正証書遺言にする。費用はかかりますが、本来の目的を達成するためには必要なことです。行政書士のような専門家は時間を掛けて勉強し、また数々の事例からベストのアドバイスを行っていきます。
READ MORE

遺言書がない相続が発生した場合、相続関係を確定させるために関係するすべての戸籍謄本を取得しなければなりません。
被相続人に存命の配偶者とお子さんがいらっしゃれば、1/2の遺産は配偶者の方に権利がありますが、残りの1/2はお子さんで等分します。お子さんといっても現在の配偶者の方のお子様だけではなく、離婚歴がある場合はその方との間にできたお子さん、また非嫡出子でも認知しているお子さんがあればその方、また離縁されていない養子の方も同権利になります。
相続が発生した時点ですでに亡くなられているお子さんがいらっしゃれば、そのまたお子さん(孫)が代襲相続しますので、その方々の戸籍や住民票が必要になります。戸籍を取得する際に併せて「戸籍の附票」というものも取得し、その方が引っ越された履歴を追い、現在ご存命で相続の権利があることを証明していきます。
さて、相続人が被相続人のご兄弟のみの場合は、難易度が一段上がっていきます。前述の場合同様、ご兄弟に知れていない兄弟が存命か確認していく作業が必要になります。これは被相続人のご両親の出生時に遡った(銀行等によっては出産一定年齢等の場合があります)戸籍謄本を取得し、知れていないご兄弟が存命か確認しなければなりません。
その方を含めたご兄弟が亡くなられていた場合は、同様に代襲相続が発生します。ただしお子さんの相続の場合は、代襲者の死亡による再代襲制度がありますが、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められていませんので、それ以下の方は調べる必要はありません。
戸籍取得は場合によっては数10枚に及び、またご兄弟の場合は戸籍を取得し追跡していく権限はありませんので、行政書士にご依頼をいただければと存じます。
READ MORE
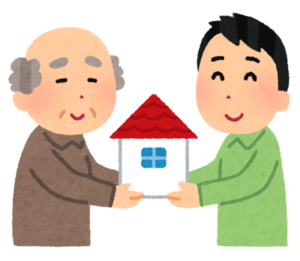
今日は遺贈と死因贈与について書いていきます。
相続は相続人にしかすることができません。そもそも相続とは、被相続人が亡くなった場合に、法律で決まっている者に財産を承継させる制度です。相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のみと民法で決まっており、これらが決められた順位で相続できるのみです。
もしこれらの者が一人もいない場合は、相続財産を管理する者として家庭裁判所から弁護士等が選任されることとなります。そこで本当に相続人がいないかの調査がなされ、それでも見つからない場合には家庭裁判所に認められた場合に限り、被相続人の世話を相当程度した者が一部の財産を譲受けることができます。それらが完了すると、最終的には財産はすべて国庫に帰属することとなります。
さて、相続人がいるいないにかかわらず、あなたがとても世話になった方がいるとします。その方の恩に報いるにはどうしたらよいでしょうか。ここからの話は相続人についてもすることができますが、相続人の場合は「寄与分」ということで、相続人間の協議において相続分の上乗せをすることができますので、ここでは除いて話を進めます。
あなたがもし遺言書を残さないで亡くなった場合には、相続人全員で相続財産の分配についての協議を行うことになります。この場合は参加できる相続人は当然法律によって定められた者のみ(あとで述べる包括受贈者を除いて)となりますので、たとえあなたがとてもお世話になり、心情的に財産を分け与えたい方でもそこには加わることはできません。
たとえば同居しているお子さんのお嫁さんなどがこれに当たります。ですのでもし相続以外で財産をあげたい場合は、あなたのその意思を明確に残す必要があります。当然法的効果のあるものでないと、他の相続人から否定された場合には、その者も権利を主張することができなくなってしまいます。ここで効果を発揮するものが一般的には遺言書ということになります。
遺言書によって相続人以外の者(相続人にもすることができますが)に財産を与える場合には、「遺贈」という形をとります。これはあなたがその方に対してする、一方的な単独行為になります。自分が死んだらその者に財産をあげるという内容になります。一方的な行為ですので、遺贈する者に事前に伝える必要はありません。
遺贈とは別にもうひとつ、相続によらずに死亡を契機として財産を与える行為に、「死因贈与」があります。これは財産をあげる者とあらかじめ契約を交わしておき、自分が死んだらあげるというものです。契約といってもこれには特に方式はなく、契約書等も必要ありません。口約束だけでも効果を発揮します。しかし、証拠がない場合はトラブルのもとになる場合もあります。もし死因贈与をする場合には、文書等に記しておくことも考えたほうが良さそうです。
死因贈与は遺贈と異なり、あなたの亡くなる前から相手の方もその内容を承知していることになります。ここで別に遺言書が残されており、そこに書かれていた内容がその死因贈与契約と異なっていた場合はどうなるのでしょうか。
この場合は遺言書の効果と同様に、後からされたものが有効となります。遺言書の書かれた日付が後であれば、遺言書によって前の死因贈与契約が破棄されたこととなりますので、死因贈与契約は無効となります。逆も然りです。このように日付等の証拠の裏付けが必要になる場合もありますので、本当に必要な死因贈与の場合は、口頭ではなく文書で日付等を明記しましょう。この2つについて次回詳しくみていきます。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry65.html
READ MORE

今日は遺産分割協議について書いていきます。
「遺産分割協議」とは、相続人全員で相続財産の配分や分割方法を決める協議をいいます。通常は遺言書がなかった場合に行われますが、遺言書があってもその相続分を変えるために行う場合もあります。
相続財産は分けることが容易である現金預貯金等だけでなく、通常は分けることが困難な家などの不動産である場合が多く見られます。そのような財産も相続税を納める等の都合もあり、定められた期限内にはその配分を決める必要が出てきます。
遺産分割協議は通常、相続人の代表者が中心となって進めていきます。代表者は多くの場合は一番たくさん財産を相続する者がなりますが、行政書士等の代理人の場合もあります。
協議の進め方は、概ね次のとおりになります。
①まず遺言書を探します。
②相続人を確定し、「相続人関係図」を作成します。
③相続財産を確定し、「財産目録」を作成します。
④相続人全員に連絡を取ります。
⑤遺産分割協議案を作成します。
⑥遺産分割協議開催の段取りをつけます。
⑦遺産分割協議書の案をもとに相続人全員参加の遺産分割協議を行います。
⑧相続人全員の合意により相続分を決めます。
⑨遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成します。
⑩遺産分割協議書をもとに、金融機関の手続きや不動産の相続登記等を行います。
以上の段取となりますが、遺言書があれば基本はそれに従って相続を行うこととなります。協議を行ったあとで遺言書が発見された場合は、相続人の主張によっては相続のやり直しとなる場合もありますので、まずは遺言書を探します。
探すのは可能性の高いところから当たりますが、親しい知り合いに士業の方などがいた場合は、そちらに相談がなかったかの確認をとります。それから公証役場に行き、公正証書遺言の存在を確認します。そこでもない場合は銀行の貸金庫や自宅を探します。
遺言書があった場合は、基本的にはそれに従いますが、自筆遺言の場合は家庭裁判所に検認の手続きをとり、その後は遺言書の真偽や合法性を確認します。最初に相続人全員での協議が整えば、遺言書があってもその合意が優先すると書きましたが、遺言執行人がいる場合はその者の執行義務との兼ね合いもありますので、必ず遺言執行人と事前に打ち合わせを行ないます。また被相続人の意思を尊重するという意味からも、出来る限りは遺言書に沿う形の執行が望まれます。
次は相続人および相続財産を確定します。相続人については通常はわかっている範囲での協議になりますが、前妻の子や認知している非嫡出子も相続人となりますので、戸籍をたどって相続人関係図を作成します。相続手続きで必要となる場合がありますので、一般的には作成することをおすすめします。
財産については心当たりのある金融機関に問い合わせを行い、また不動産等の登記簿を確認します。こちらも財産目録を作成します。そしてこれらをもとに遺産分割の案を作成します。基本的には法定相続分をもとに、相続人の寄与分や不動産の実態(配偶者が自宅に居住している等)を鑑み配分を行います。
それからその案をもとに協議を行うことになりますので、まずは相続人全員に連絡をとり、遺産分割協議を開催します。ここで注意することは、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要となることです。海外等に居住し参加できない者も原則は参加するものとなりますので、もし参加できない場合には事前に、他の意見に従う等の同意書を取得する必要があります。
やっかいなのは行方不明者がいた場合の措置であり、この場合は家庭裁判所に「失踪申告の申し立て」等を行うこととなります。また成年被後見人等の制限行為能力者がいる場合は後見人等の代理が必要となり、未成年がいる場合は「特別代理人」による代理が必要となります。
未成年は基本的に法律行為は行えませんので、その場合は代理人が必要になります。通常の代理人はその親がなることが一般的ですが、相続の場合はその親と子で同じ相続人という利益相反の立場となるため、代理人となることができません。そのため家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行うこととなります。
それらの者が整いましたら遺産分割協議を行い、原案をもとに協議を整います。協議が成立した場合は、その内容で遺産分割協議書を作成することとなります。金融機関等の相続において必要となるため、協議書はたとえ親子2人での協議の場合であっても作成します。協議が成立しなかった場合は家庭裁判所への調停の申し立てを行い、それでも整わなければ裁判ということになります。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry62.html
READ MORE

今日は相続にも大きく関係してくる、親族というものについて書いていきます。
相続を受けることのできる者(相続人)は「相続人」である「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」になりますので、親族の範囲を見た上で、これらの者がどの位置にいるのかを見てみます。
また今回成立した相続関係の民法改正において、「相続人以外の親族の貢献を考慮する方策」が加えられましたので、今まで以上に「親族」という言葉が使われる機会が多くなると思います。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry69.html
「親族」とはどのようなものを言うのでしょうか。民法における「親族」とは、次の者を言います。
①6親等以内の血族
②配偶者
③3親等以内の姻族
です。
まず「血族」とは、血縁関係のある者相互間(誰から見てもお互いに)および、法的に血縁があると制度上みなされる(擬制)者相互間を言います。前者を「自然血族」、後者を「法定血族」と言います。
「自然血族関係」は出生によって生じ、死亡によって終了します。「法定血族関係」は養子縁組によって生じ、離縁や縁組みの取り消しによって終了します。
次の「配偶者」は、婚姻によって戸籍上の地位を得た者になりますが、配偶者は血族にも姻族にも属さず親等もありません。
「姻族」とは「配偶者側の血族あるいは血族の配偶者相互間」を言います。例えば配偶者の父や、本人の父の兄弟(叔父)の配偶者は姻族になります。「姻族関係」は配偶者を通じての関係になりますので、配偶者の一方の血族と他方の血族は姻族にはなりません。具体的に言うと、本人の父と配偶者の父は姻族関係には当たりません。
また姻族関係は婚姻によって生じ、離婚によって終了することになります。離婚した元配偶者の親とは知り合いではあっても、法的つながりはなくなるということです。これは離婚の場合であり、死別の場合は届出を行わない限りは姻族関係は当然には消滅しません。
では先に出てきた「親等」とはどのようなものでしょうか。
「親等」とは親族間の遠近度を比較する尺度であり、親族間の「世代」によって決まります。本人から見て「世代」がひとつ変われば1親等という数え方をします。
相続人に当てはめて見ますと、配偶者に親等はありません。子と直系尊属(父母)が1親等、孫や祖父母は2親等になります。兄弟姉妹は親を経由して下がりますので、これも2親等と数えます。本人の叔父や叔母は祖父母を経由しますので3親等、その子であるいとこは4親等になります。
親族については世代をまたがる垂直の広がりと、直系から枝分かれをした横への広がりがあります。
縦への広がりで見てみますと、本人から世代が上の者たちを「尊属」、世代が下の者たちを「卑属」と言います。ですので父は尊属、子は卑属になります。兄弟姉妹やいとこは世代が同じですので、尊属にも卑属にも当たりません。
横への広がりで見てみますと、本人から垂直に遡ることのできる父母や祖父母や曽祖父母、あるいは垂直に下がることのできる子や孫やひ孫などは「直系」になります。
縦横併せてマトリックスで見ますと、上の世代を「直系尊属」、下の世代を「直系卑属」と言います。垂直から枝分かれをした叔父叔母などは「傍系」と言います。これも上の世代を「傍系尊属」、下の世代を「傍系卑属」と言います。
整理してみますと、血族には直系血族と傍系血族があり、直系血族には直系尊属と直系卑属があります。また傍系血族にも傍系存続と傍系卑属があることになります。姻族にも同様の、直系傍系、尊属卑属の関係があります。
改正民法の特別寄与に関しては、具体的に権利の範囲にあるかは事案ごとに確認を要するとことになります。
READ MORE
今日は普通養子縁組の解消について書いていきます。
縁組も婚姻同様、他人同士の意思の合致による行為になりますので、お互いの意思が合致しなくなった場合も、婚姻同様にその関係が解消されることとなります。
婚姻の場合の離婚に当たるものが、「離縁」になります。「離縁」には
①協議離縁
②裁判離縁
があります。
「協議離縁」とは、当事者同士の協議によってするものを言います。離縁の成立要件は縁組の時と同様に、形式的要件と実質的要件になります。形式的要件はこれも届出になります。実質的要件は当事者間の、養親子関係を終了させる意思の合致になります。
未成年や成年被後見人の場合は通常単独で協議を行うことはできませんが、未成年であっても15才以上の者は単独で離縁をすることができ、成年被後見人の場合も本心に復している場合は単独ですることができます。
配偶者のある者が未成年者と縁組をするには、夫婦揃っての縁組が必要でしたが、離縁についても夫婦がともにしなければなりません。
縁組の当事者の一方が死亡した場合はどうでしょうか。この場合の一方の生存者は、家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。これを「死後離縁」と言います。養親子関係自体は当事者の一方または双方が死亡すれば消滅しますが、法定関係は存続しますので、相続も発生します。
また配偶者死亡の時同様、縁組によって生じた法定血族関係は当然には消滅しませんので、これらの関係を消滅させるには、家庭裁判所の許可が必要になります。
離縁の無効や取り消しの場合も、婚姻の場合と同じです。離縁意思の合致を欠いたり、代諾権のない者が代諾した場合は無効になります。
また詐欺や強迫によって行われた離縁は取り消しをすることができます。この場合は詐欺を発見し、または脅迫から免れた時から6ヶ月以内に、家庭裁判所に請求をします。取り消しの効果は離縁の時点に遡及することとなり、離縁はなかったものとなります。
「裁判離縁」は、協議離縁が成立しなかった場合に、家庭裁判所への請求によってなされます。裁判離縁の成立する要件としては、
①他の一方から悪意で遺棄されたとき
②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
③縁組を継続し難い重大な事由があるとき
になります。
離縁の効果によって、養親子関係および法定親族関係が、離縁の日から消滅することになります。
また養子は離縁前の氏に戻ることになり、原則として離縁前の戸籍に入ることになります。離婚の場合の氏については婚氏続称という制度がありますが、離縁にもあります。
離縁の場合に離縁前の氏を継続する時は離婚よりも要件は厳しいものとなり、縁組が7年以上継続されている必要があり、離縁の日から3ヶ月以内に届出を行う必要があります。
READ MORE
本日は私のホームページ上に載せている遺言書についてのQ&Aについて書いてみます。といってもQ&Aページのものではなく、遺言を書かれる動機固めのイントロダクションになります。では順番に。Q:遺言書などを書いたら、子供たちにあらぬ詮索をされるかもしれない。今現在円満に暮らしているし、相続の話しで家族の中に波風を立てたくない。A:今現在ご円満だからこそ、円満なまま仲良く暮らしていって欲しいのではないですか。遺言書のことは皆さんに表立ってお伝えする必要はありません。行政書士と相談しながら、最善の方法で作成していきましょう。Q:自分の家族に対する愛情は平等だ。でも今の子供たちの暮らしぶりを考えて、財産の分け方を決めても良いのではないか。いやいや私が決めるよりも子供たちが決めれば良いことではないか。A:相続人当事者同士で、遺産分割が円満に成立する場合ばかりではないようです。お子様にもご家族や関係者が大勢いらっしゃり、お子様ご自身の意思だけで決められるとは限りません。そうなった時には行事役のあなたはその場にはいらっしゃいません。今現在の状況を客観的に判断されて、みなさんを円満にまとめられるのは、あなたを置いて他にはいらっしゃいません。Q:遺言書を書こうとは考えているが、どこから手をつけて良いかわからない。具体的に想いを形にしたいが。A:遺言書は「だれに、何を、どのように」になります。まず遺言書を残されようと思い立った動機をご自身が再確認し、その目的を達成する方法を考えれば良いと思います。Q:健康に不安はないし遺言や相続のことなどまだ当分先のことだから、今考える必要はないかもしれない。A:みなさんそうおっしゃいます。遺言書は別に今書く必要はないものです。ただ、いざという時には遺言を残せないかもしれません。法的効果のある遺言には要件があります。そうならないためにも、もし相続に多少なりともご不安があるのであれば、「思い立ったが吉日」ではありませんか。Q:誰に相談したらよいかわからないし、自分の思いを口に出すのは恥ずかしい。A:遺言書には皆さん、今まで言えなかったご家族への感謝の言葉を残されます。普段は気恥ずかしくて、面と向かってはなかなか言えないものです。でもこれは最後のメッセージになります。形にした時点でご自身の心のつかえもとれるでしょうし、そこから新たなものも見つかるかも知れません。ご遠慮なくお話しいただき、その想いを形にしていきましょう。Q:誰かに依頼すると費用が発生すると思い、ふんぎりがつかない。A:行政書士の報酬や、公証役場の手数料は決して安価なものではありません。むしろ普段の生活の中では高額なものになります。しかし見返りに得られる価値は、決してお金に変えられるものではありません。ご負担になるようでしたらそれはご自分で書かれるのも良し、あくまで判断されるのはお客様ご自身になります。Q:自分で書こうと思ったが、書き方がわからない。自分で書いた場合のデメリットはあるのだろうか。A:このホームページに自筆遺言の書き方も載せてありますのでご一読ください。自筆遺言の最大のメリットは、もちろん費用がかからないことです。簡単に書く事も、書き直しもできます。今回の民法改正によって、自筆遺言のハードルも多少下がりました。デメリットは自筆遺言書自体がトラブルの原因になることです。簡単に書く事ができるために内容の裏付けがなかったり、保管が不十分であったり。ご予算等に合わせれば良いことですが、行政書士へのご依頼のほとんどが公正証書遺言であることもまた事実ですQ:遺言書を書いても保管方法がわからないし、もし相続が終わったあとに出てきたらトラブルのもとになってしまうかも知れない。A:上のご質問同様、自筆遺言の記載を確認ください。民法改正によって自筆遺言の保管や検認手続きなどについては使い勝手が良くなりましたが、多くのトラブルの原因が解消されるわけではありません。Q:遺言書を書いたあとに気が変わるかも知れない。気安く書かない方が良いのではないか。A:もちろん遺言書は気安く書かれるべきものではありません。慎重にご家族の将来を見据えて書かれるものですが、状況が変わることもありえます。そのような場合でも、遺言書は撤回することもできますし、それを破棄して新たなものを作成することもできます。遺言書は常に日付の新しいものが有効となります。Q:遺言書を書いてしまうと、自分の財産を自由に使えなくなるのではないか。A:ご自身の財産は、当然ご自身で自由に処分することができます。遺言書に縛られることはありませんし、日々の生活を見据えて書かれることだと思います。万が一状況が変わって大きな財産を処分することになっても、その際に考えれば良いことになります。ご心配はごもっともです。でもそのご心配を解きほぐし、一歩前にすすんでみませんか。
READ MORE

相続は突然にやってくる場合もあります。相続人の方にとっては亡くなられた方の財産を受けられるものですから、概ねメリットがあるものです。しかし一方では、ご家族や身内の方を失ったという、心身ともに非常に辛い時期になります。
そんな中にあって、相続は嫌でもやってきます。遺言書がなく、相続人が複数おられる場合には、決められた期限内に遺産分割協議というものを開き、相続人全員でそれぞれの相続分を決めなくてはなりません。
財産の多くを現金預金が占めれば良いのですが、不動産が多くを占める場合など、皆さんの不満なく分割するにはやっかいな問題が生じることも多いものです。また財産や相続人を調べ、いくつもの書類を作成する必要もあります。
普段は考えることもない遺言書ですが、そのような際は身にしみてその重要さがわかります。遺言書作成をお悩みの際は是非とも当事務所にご相談下さい。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/
READ MORE

今日は遺贈と死因贈与についてもう少し詳しく書いてきます。
まず「遺贈」についてですが、遺贈される者を「受遺者」といいます。相続と同様、遺贈も被相続人の死亡によって開始されます。
受遺者になる要件はひとつ、遺言によって遺贈をする旨の内容が残されていることですが、被相続人の死亡時に遺贈をされる者が既に死亡していた場合は、受遺者となることはできません。また受遺者については代襲の定めはありませんので、この場合はその子等に権利が移ることもありません。遺贈はなかったことになります。
一方、被相続人の死亡時には遺贈をされる者がまだ生存しており、その後すぐに死亡した場合については、遺贈の効果は有効となります。ですのでその財産は受遺者の子等に相続されることとなります。
遺贈には2つのものがあります。ひとつは「包括遺贈」とよばれるもので、財産の全部または一定の割合を指定してする遺贈です。この場合は具体的な財産は決められていないことになりますので、他の相続人がいる場合は、これらの者と一緒に遺産分割協議に参加しなくてはなりません。
また包括遺贈の特徴は、相続同様プラスの財産のみならずマイナスの財産も含むことです。マイナスの財産が多い場合もありますので、これも相続同様、受遺者に受ける受けないの選択権が設けられており、3ヶ月の期間内に放棄することも認められています。放棄する場合は、家庭裁判所に申請をする必要があります。
もうひとつは「特定遺贈」とよばれ、特定の財産を指定してなされる遺贈です。特にマイナスの財産を指定して行われない限りは、プラスの財産のみの遺贈となります。特定遺贈では遺産分割協議への参加もする必要はなく、また遺贈の承認や放棄の意思表示の期間も特に定められてはいません。しかし他の相続人が協議をすすめる必要性もあるため、これらの者から早期に意思表示を求められる場合が多くなります。
遺贈の場合の税金については、贈与税ではなく相続税として申告する必要があります。また相続人ほどの権利は認められていませんので、不動産の場合は登記をしなければ第三者に対抗できず、農地であった場合は農地転用が必要となります。
遺贈には「負担付き遺贈」と呼ばれるものがあります。これは、与えた条件(負担)を履行した場合のみ遺贈が行われるという性質のものです。たとえば、被相続人の配偶者の面倒を見ることを条件に遺贈を行う、といった場合がこれに当たります。
では負担が履行されなかった場合はどうなるのでしょうか。
負担を履行しなかった場合には、多くは遺言執行者や相続人から、遺贈の取り消しを請求されることとなります。この場合の遺贈する予定だった財産は負担付き遺贈者には渡されず、他の相続人に渡ることとなります。相続人が複数いる場合は、この部分について再度分割協議が行われます。
では負担の大部分は履行したが、全部の履行は行われなかった場合はどうでしょうか。判例では遺贈が認められた場合があります。当然負担を行った程度だけではなく、様々な状況も異なると思いますので、個別具体的に判断する必要があるということでしょう。
「死因贈与」とはどのようなものでしょうか。財産を与える者を「贈与者」、受ける者を「受贈者」とよびますが、これはお互いの契約になりますので、受贈者が一方的に放棄することはできません。死因贈与の際に納める税金も遺贈同様、贈与税ではなく相続税になります。
なお死因贈与の場合も条件付きの贈与があり、これを「負担付き死因贈与」とよびます。負担付き贈与の場合は、受贈者が亡くなる前であれば一方的に破棄することができますが、負担が履行され始めた場合には撤回することはできません。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry65.html
READ MORE