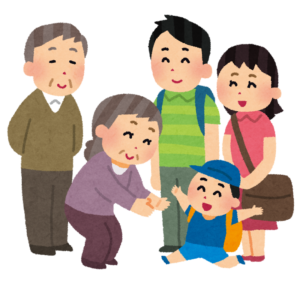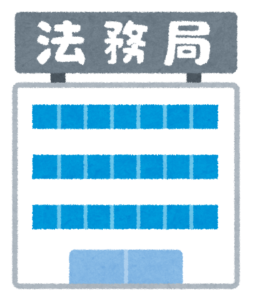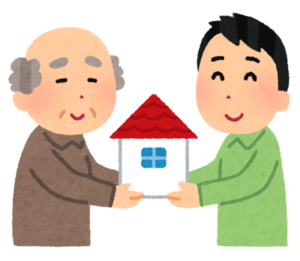今日は遺産分割協議について書いていきます。
「遺産分割協議」とは、相続人全員で相続財産の配分や分割方法を決める協議をいいます。通常は遺言書がなかった場合に行われますが、遺言書があってもその相続分を変えるために行う場合もあります。
相続財産は分けることが容易である現金預貯金等だけでなく、通常は分けることが困難な家などの不動産である場合が多く見られます。そのような財産も相続税を納める等の都合もあり、定められた期限内にはその配分を決める必要が出てきます。
遺産分割協議は通常、相続人の代表者が中心となって進めていきます。代表者は多くの場合は一番たくさん財産を相続する者がなりますが、行政書士等の代理人の場合もあります。
協議の進め方は、概ね次のとおりになります。
①まず遺言書を探します。
②相続人を確定し、「相続人関係図」を作成します。
③相続財産を確定し、「財産目録」を作成します。
④相続人全員に連絡を取ります。
⑤遺産分割協議案を作成します。
⑥遺産分割協議開催の段取りをつけます。
⑦遺産分割協議書の案をもとに相続人全員参加の遺産分割協議を行います。
⑧相続人全員の合意により相続分を決めます。
⑨遺産分割協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成します。
⑩遺産分割協議書をもとに、金融機関の手続きや不動産の相続登記等を行います。
以上の段取となりますが、遺言書があれば基本はそれに従って相続を行うこととなります。協議を行ったあとで遺言書が発見された場合は、相続人の主張によっては相続のやり直しとなる場合もありますので、まずは遺言書を探します。
探すのは可能性の高いところから当たりますが、親しい知り合いに士業の方などがいた場合は、そちらに相談がなかったかの確認をとります。それから公証役場に行き、公正証書遺言の存在を確認します。そこでもない場合は銀行の貸金庫や自宅を探します。
遺言書があった場合は、基本的にはそれに従いますが、自筆遺言の場合は家庭裁判所に検認の手続きをとり、その後は遺言書の真偽や合法性を確認します。最初に相続人全員での協議が整えば、遺言書があってもその合意が優先すると書きましたが、遺言執行人がいる場合はその者の執行義務との兼ね合いもありますので、必ず遺言執行人と事前に打ち合わせを行ないます。また被相続人の意思を尊重するという意味からも、出来る限りは遺言書に沿う形の執行が望まれます。
次は相続人および相続財産を確定します。相続人については通常はわかっている範囲での協議になりますが、前妻の子や認知している非嫡出子も相続人となりますので、戸籍をたどって相続人関係図を作成します。相続手続きで必要となる場合がありますので、一般的には作成することをおすすめします。
財産については心当たりのある金融機関に問い合わせを行い、また不動産等の登記簿を確認します。こちらも財産目録を作成します。そしてこれらをもとに遺産分割の案を作成します。基本的には法定相続分をもとに、相続人の寄与分や不動産の実態(配偶者が自宅に居住している等)を鑑み配分を行います。
それからその案をもとに協議を行うことになりますので、まずは相続人全員に連絡をとり、遺産分割協議を開催します。ここで注意することは、遺産分割協議は相続人全員の参加が必要となることです。海外等に居住し参加できない者も原則は参加するものとなりますので、もし参加できない場合には事前に、他の意見に従う等の同意書を取得する必要があります。
やっかいなのは行方不明者がいた場合の措置であり、この場合は家庭裁判所に「失踪申告の申し立て」等を行うこととなります。また成年被後見人等の制限行為能力者がいる場合は後見人等の代理が必要となり、未成年がいる場合は「特別代理人」による代理が必要となります。
未成年は基本的に法律行為は行えませんので、その場合は代理人が必要になります。通常の代理人はその親がなることが一般的ですが、相続の場合はその親と子で同じ相続人という利益相反の立場となるため、代理人となることができません。そのため家庭裁判所に特別代理人選任の申し立てを行うこととなります。
それらの者が整いましたら遺産分割協議を行い、原案をもとに協議を整います。協議が成立した場合は、その内容で遺産分割協議書を作成することとなります。金融機関等の相続において必要となるため、協議書はたとえ親子2人での協議の場合であっても作成します。協議が成立しなかった場合は家庭裁判所への調停の申し立てを行い、それでも整わなければ裁判ということになります。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry62.html
Related Posts
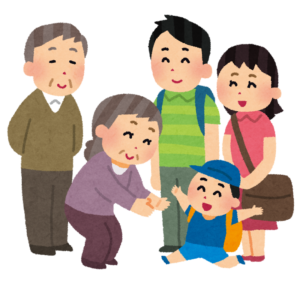
今日は民法家族法の、親権について書いていきます。
「親権」とは、父母である者の、「養育者としての地位」に由来する権利義務のことを言います。その親権に服する者は子供全般ではなく、「未成年の子」になります。子供が未成年であれば、親権が発生するということです。
親権を行うものは子の父母になります。原則父母が共同して親権を行いますが、一方が共同名義で代理行為をした場合は、仮に他方が反対していたとしても効力を生じます。しかしこの場合に相手方が悪意であった場合には効力は認められません。
次の場合は例外として父母の一方が単独で行うことができます。
①父母の一方が親権を行使できないとき
②父母が離婚したとき
③非嫡出子の親権を原則として母が行使するとき
です。
なお、子の利益のために必要と認められるときは、子の親族が家庭裁判所に請求することによって、親権者を他の一方に変更することができます。
では具体的に、「親権者」にはどのような権利義務があるのでしょうか。
「親権者」は子の利益のために、子の監護および教育をする権利を有し義務を負い、必要な範囲で居所指定権や懲戒権を有し、子が職業を営むことができるとされています。
身分上の行為においては、親権者はその子に代わって親権を行うことができます。これは民法上個別に規定されており、これは、
①嫡出否認の訴えの相手方
②認知の訴え
③子の氏の変更
④縁組の代諾
⑤未成年者の養子縁組取り消し請求
⑥相続の承認放棄
になります。
また財産上の行為の代理権もあり、親権者は法定代理人として、財産上の行為について一般的に代理権を有します。
この場合に親権者は、子の財産を管理しその財産に関する法律行為について代理することができますが、その子の何らかの行為を伴う時は、本人の同意が必要になります。
また民法の規定上、親権者に利益があって子に不利益が生じる場合や、子の一方に利益があって他方に不利益があるというような「利益相反行為」については、親権者は子に対する代理権も同意権も有しません。この場合は家庭裁判所に、「特別代理人」の選任を請求します。
これは相続の場合にもよくありますが、被相続人の子が未成年である場合には配偶者は法定代理人とはなれず、必ず特別代理人を請求することになります。
次に親権を喪失する場合について見てみましょう。
特別養子縁組(この場合は一定の年齢制限がありましたが)の記事にもありましたが、父母による虐待や悪意の遺棄があるとき、あるいは父母による親権の行使が著しく困難であったり不適当であることによって子の利益を著しく害する時は、2年以内にその原因が消滅する見込みがある時を除き、家庭裁判所は「親権喪失の審判」をすることができます。
この親権喪失の請求者は、子やその親族、未成年後見人、検察官等になります。また親権喪失には至りませんが、同様に2年以内の期間を定めて親権停止の審判を行う、「親権停止の審判」も創設されています。
親権とは別に、もう一つ相続にも関連する内容についても触れておきます。「扶養」についてです。「扶養」とはもちろん親権者が子に対する義務でもありますが、民法では「親族間の扶養」についても規定しています。
「扶養」とは自力で生活できない者に対して、一定の親族関係にある者が行う経済的給付とされています。扶養の内容については次のとおりになります。
①要扶養者(扶養される必要のある者)は、自分の財力等で生活できない者である必要があります。
②直系血族および兄弟姉妹は互いに扶養義務を負担します。
③3親等以内の親族については、特別の事情があるときに家庭裁判所が扶養の義務を負わせることができます。
④扶養の内容等について当事者間で整わない場合は、家庭裁判所の判断に委ねることができます。
「扶養」については負担付き遺贈であったり、今回改正された相続における特別の貢献にも関係してくる事柄になります。
READ MORE

今日は共有について見てみます。
これも相続分野で頻出する言葉となりますが、「共有」とは、数人の者が共同所有の割合である「持分」を併せて1つの物を所有することを言います。単純に言えば、数人で1つの物を所有することですね。
「持分」とは今述べたように、共有物に対する所有権の割合のことです。持分の割合はそれぞれの意思表示や法律の規定(法定相続分等)により決まりますが、その割合が不明な場合は各共有者平等の持分であると推定されることになります。
持分は各共有者が原則自由に処分できます。共有目的物の利用については各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。
例えば1台の自動車を3人で共有しているとしますと、3人それぞれがその自動車を自由に使用することができます。しかし異なる目的を同時に行うことはできませんので、必要な場合は各自の持分に応じた使用時間配分を決められるということです。自動車を購入するのにAさんがその代金50%、BさんとCさんが25%を出資していたとすると、その割合で使用時間を決められるということになります。
相続に当てはめると、配偶者と子供が2人いる場合は配偶者が50%の持分であり、2人の子供はそれぞれ25%ずつの持分ということになりますね。
また持分は、使用する共有者の1人がその持分を放棄した場合や、共有者が死亡した際に相続人がいない場合はその持分は他の者に帰属することとなります。
共有物には日々の利用についても制約がありますので、それらについても見ていきましょう。
共有物の利用については、その内容や利用状況から次の3つに区分されています。
①保存行為
②管理行為
③変更行為
になります。「保存行為」とは修理や修繕など、共有物の現状を維持する行為であり、各自が単独で行うことができます。なお現状維持という観点からの妨害排除請求や消滅時効の中断なども共同で行われる必要はなく、各自が単独で行うことができます。
次の「管理行為」とは、共有物の性質を変えることなく利用したり改良する行為とされています。これには共有物の賃貸やそれに関する解除や取り消し行為などがありますが、この場合は単独で行うことはできず、共有の過半数の合意が必要になります。
過半数とは人数が基準になるものではなく、持分の価格を基準にしての過半数になります。Aが10でBが20の持分価格を有していても、Cが50を有する場合には必ずCの承諾が必要になります。
「変更行為」とは共有物の性質や形状を変更することを言います。具体的には共有物を売却したりその全部に抵当権等を設定する場合がこれに当たりますが、この場合は共有者全員の同意が必要になります。
最後に「共有物の分割」について見てみましょう。共有物については、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができます。分割の方法は現物分割、代金分割、価格賠償の3つがあります。
ここでの「現物分割」とは現物そのものを分割すること、「代金分割」とは共有物を売却してその代金を分割する方法です。「価格賠償」とは共有物を分割した際に持分に満たない者に、超過した者からその金額を補填することを言います。
共有分割の協議が整わない場合は遺産分割協議同様、裁判所に分割を請求することになります。なお遺言書による場合が多いですが、共有物を5年を超えない期間で分割を禁止する特約を付けることもできます。
READ MORE
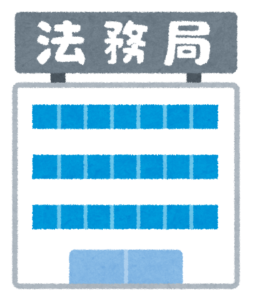
今日は相続に関して、法定相続情報証明制度について書いていきます。平成29年5月29日から開始された制度です。
相続は被相続人の死亡によって開始しますが、遺言書があった場合は基本それに基づいて相続が執行されます。遺言書がなかった場合は相続人全員で遺産分割協議を行ない、それぞれの配分財産を決めます。相続財産はだいたい現金預貯金や不動産といった形をとりますので、当然管理も預貯金であれば金融機関、不動産であれば法務局が行うこととなります。
契約者や名義人は亡くなったとはいっても被相続人ですので、仮に相続人であるからといって、簡単に払い戻しや手続きには応じてくれません。金融機関であれば被相続人の死亡したことを通知した時点をもって口座が凍結され、たとえ相続人である子が葬儀費用が必要だといった場合でも払い戻しには応じてくれません。
この場合は葬儀費用はとりあえず自分たちで別途捻出し、相続関係を確認できるすべての者の戸籍謄本(被相続人の出生からさかのぼったものが必要です。相続関係一覧表にしてあることが望ましいです)や財産目録等を提出し、種々の手続きを行って初めて相続の払い戻しに応じてもらえます。
法務局においても、相続後の土地や家屋についての名義変更を行うためには、同様の戸籍すべてが必要になります。また戸籍が必要である金融機関等が複数ある場合には、戸籍謄本をその数分取得するか、あるいは1機関ごとに提出と返還を繰り返すことになります。
これらの作業を相続人が行うことは非常に煩雑で手間のかかることになりますので、土地の名義変更や登録を行わない者が出てきます。相続後に登記をしないことについては法律で罰則が設けられていないことから、名義人の不明な土地や家屋が散在することとなり、いまや社会問題にもなっています。
法定相続情報証明制度とはそういう戸籍の提出をまとめて出せるようにし、提出と返還の作業を繰り返さなくても良いように設けられた制度です。具体的には、戸籍一式を揃えて法定情報一覧図を作成し、法務局からその一覧図の写をもらいます。法務局や他の金融機関でも、その一覧図の写の提出のみで手続きが行えるというものです。
相続人や代理人等が法務局に申請を行いますが、申請できる法務局は被相続人の本籍地か最後の住所地にある法務局、あるいは請求人の住所地にある法務局か被相続人名義の不動産がある場合はその所在地の法務局になります。
メリットは相続人本人が申請を行う場合には、それなりに手数が省けるということになります。しかしまだ開始後間もない制度であるため、現時点では使い勝手が悪い点もあります。たとえば再交付が必要になった場合では、申請人本人によって申請をした法務局に申請を行わなくてはならない点です。
他の相続人が行う場合には、都度申請者の委任状が必要になります。またこの制度は戸籍謄本の情報をまとめる目的だけであるため、相続放棄や欠格等の情報は網羅されていません。それらの情報が必要な場合は、結局別の資料を用意することになります。
もっとも前述の提出と返却の件ですが、基本的に行政書士が銀行に代理で手続きを行っても、提出した書類はその場でコピーし返却されますので、実務上はあえてこの制度を使うメリットは少ないと考えます。大元の目的が相続不動産の登記促進であるならば、いずれにしても法律面での規制等、抜本的な方策が必要なんでしょう。
READ MORE

前回は遺産分割協議について触れましたが、相続人が少人数で関係も良好な場合は大きな問題になることはそれほど多くはありません。各自がそれぞれの立場も理解できており、またその後に直系の相続も発生することも想定できるからです。
しかし相続人同士が仲が良くなかったり、金銭関係が良好でない方が居る場合は途端に状況が変わってきます。また相続人が多かったり、相続人が兄弟のみで代襲相続が発生している場合などは特に問題がある場合が多くなります。よく「相続」は「争族」だとも言われますが、くれぐれも「争族」にならないように気をつけなければなりません。
多くの方は「うちに限って心配はない」と言われますが、そんな場面ばかりではないようです。親子関係、兄弟姉妹の関係は悪くはなくても、その方々の身内や関係者による口出しがある場合があります。またちょっとした言葉がきっかけで、一気にかたくなになってしまわれる方もいらっしゃいます。
相続というものは場面も場面でありますし、金額の多い少ないにかかわらず無条件でお金がもらえる機会になります。人情として気にならないはずはありません。通常は相続人が複数いらっしゃる場合は、相続分の一番多い方(配偶者など)や、一番しっかりされている方が代表相続人になられます。この方がしっかり方向性を決め、意見をまとめていきませんととんでもないことになります。協議がまとまらず、事案が法定にもちこまれることになりかねません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないとまとまりません。たとえ相続分の少ない方であっても、その方が合意しない限りは協議は成立しません。ですので代表相続人の方は仲の良い方だけをまとめるのではなく、対応しにくいとんでもない共同相続人にも事前にしっかり皆さんの意向を説明し、協議前に大方の合意にこぎ着けていく必要があります。
そのためにも事前にしっかりとした遺産分割協議書案を作成し、当日は全員の実印をもらえるような段取りで協議に臨みましょう。トラブルメーカーはどこにでもいます。そういう方も直視して、期限内に円満な相続を終えましょう。
READ MORE

今日は付言について書いてみます。
「付言」は「ふげん」と読みます。付言とは遺言書に自分のメッセージとして付け加える言葉です。付言自体には法的効果はありませんので、遺言書の方式を満たす要件にはなっていません。しかし多くの方が文面に残されているようですし、行政書士としても基本的にはおすすめをすることにしています。
また書面への付言という形ではなく、別途手紙という形で残される場合もあります。しかしこの場合は公正証書遺言のように公証役場で保管がなされず、またその真偽も定かではないため信ぴょう性が疑われることもあり、お勧めはできません。
付という文字がつくと、付記や追記という言葉が思い浮かんでしまいますが、もちろんこれらのように、後から付け加える(意図的な場合もあるでしょうが)という性質のものではありません。むしろその遺言書を書かれた本来の動機や目的から発する言葉だと考えます。
遺言を残す動機はいろいろあると思いますが、ひとつには自分が苦労して残した財産を、自分の意思で自分の思う通りに配分したいという考えです。これは自分がいなくなっても、その財産を有効に活用することのできる子を中心に相続させたいというような合理的な理由もあるでしょうし、今まで自分にしてくれた行為や与えてくれた愛情への論功行賞的な理由の場合もあるかも知れません。
また例えば子供ごとに異なるそれまでの支援状況も加味した上で、それらを差し引いてそれぞれ平等な相続額にという場合もあるでしょうし、それぞれの暮らしぶりから行く末を案じてということもあるかも知れません。
もうひとつの動機は、自分が亡くなったあとも、相続でもめることの無いようにとの家族への配慮や愛情から発せられるものです。遺言書を書こうか悩まれている方の多くは、むしろこちらの動機が強いのではないかと思います。
でもそのような愛情から発した遺言書も、内要によっては感情的なしこりを残す場合も出てきます。
多くの場合には相続財産は不動産など、簡単に分割できないものになります。また現に今どなたかが住まわれている家も相続財産(生前贈与されていても相続財産に加わります)になりますので、それを相続の段階で分割しようといってもなかなかできることではありません。
遺言書がなかった場合の相続では必ずおこる問題ですが、そもそもそういうゴタゴタでご家族の方に心身の負担をかけたくないという思いで遺言書を書かれたはずです。かといって実際にはその住まわれている家や不動産などの財産を均等に分けることは非常に困難なことですし、多少なりとも偏りが出てしまいます。そこにどなたかの不満がでないとも限りません。
遺言書というものは元来無味乾燥なものです。そこには相続人や相続財産などが淡々と記載されているだけで、ご本人の本来の意思など確認しようもありません。意思を読み取ったり推察することはできるでしょうが、誤解の生まれる余地も多分にあります。ましてや相続分に偏りがあった場合などは、相続分の少ない方からの不満はあって当然だと思います。
財産を偏りなく相続させることはとてもむつかしいことです。不動産が多い場合などはなおさらです。愛情の多い少ないで相続分を考えたのではなく、事情があってしたことであれば、その理由は伝えてあげた方が良いと思います。
付言はご自分の感情を伝える最後の方法であるとともに、ご遺族の方にとっても、あなたのご意思を知る最後の機会に違いありません。
最後にひとつ。くれぐれも愚痴や恨み言は残さないようにしましょう。
ご家族が円満に相続を終えていただくためにも、あなたが遺言書を書かれた動機や意図を伝えることが重要になります。付言とはそのときそこにいないあなたに代って、そのメッセージを伝える役割を担っています。
http://yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry21.html
READ MORE

今日は不法行為について書いていきます。
「不法行為」とは、故意または過失によって他人の権利または法律上保護される利益を侵害すること言い、これを侵害した者はこれによって生じた損害を賠償する責任を負います。交通事故も不法行為に当たります。
法学的には「不法行為」は、
①被害者の救済を図る損害補填的機能
②将来の不法行為を抑止する予防的機能
③加害者に制裁を加える制裁的機能
を有するとされています。
不法行為の成立要件は次のとおりです。
①加害者に故意または過失があること
②権利または法律上保護される利益の侵害があること
③損害が実際に発生していること
④権利や利益の侵害と損害との間に因果関係が存在すること
⑤加害者に責任能力があること
です。
①の「故意」とは、自分の行為によって権利や利益の侵害が発生することをわかっていながらすることであり、「過失」とは損害の発生を予測して、あらかじめ防止すべき義務を怠ることを言います。
②については加害行為の内容や程度を加味し、個別具体的な判断が必要になります。必ずしも法律上保護されていない利益であったとしても、救済の対象となる場合があります。
③の損害については、財産的な損害はもちろんですが、慰謝料などのような精神的な損害もあります。
④の因果関係については、先に記事にしました416条の「通常生ずべき損害」と「予見することができる特別の損害」の規定を類推適用して、「相当因果関係」が認められる範囲で損害賠償を請求することができます。
⑤の責任能力とは自己の行為の責任を弁識できる能力を言います。民法上の責任無能力者とは、12才未満の者や心神喪失者などを指します。ちなみに刑法上では14才未満の者や心神喪失者等を指します。
不法行為が成立した場合には、被害者に損害賠償請求権が発生します。相続との関係では、この損害賠償請求権は被害者の生前の意思表示にかかわらず相続の対象となります(判例)。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry44.html
賠償の方法は原則金銭賠償になります。例外として名誉毀損裁判の場合には、名誉回復措置となることもあります。
この損害賠償を請求する権利者についてですが、不法行為を受けた被害者は当然請求者になりますが、不法行為が生命を侵害した場合やそれに匹敵する内容の場合には、被害者の父母や配偶者および子は「慰謝料」を請求することができます。
なおこの不法行為に基づく請求権についても消滅時効があります。被害者等が損害及び加害者を知ってから3年で消滅時効にかかり、不法行為の時から20年で除斥期間とされ消滅します。
除斥期間とは時効のように中断や停止が認められず、期間の経過とともに当然に権利が消滅する期間を言います。なお2020年4月1日施行の債権関係の民法改正においては、20年は除斥期間ではなく時効期間であることが明記されました。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category8/category10/entry36.html
最後に不法行為における過失相殺について触れておきます。
過失相殺は債務不履行の記事でも書きましたが、債務不履行の相殺については発生すれば必ず必要的に行われる相殺であって、責任軽減だけでなく免責もすることができました。
一方不法行為における過失相殺については、損害賠償の額を減額できるだけであって不法行為の責任を免責することはできません。またその減額についても必ずなされるものではなく、過失の態様によって任意的に判断されます。
なお被害者の過失には、被害者本人と身分上、生活関係上一体をなすと見られる者の過失も含まれます。例えば子供が道路を飛び出して自動車にはねられた場合には、一緒にいた母親も監督不十分で過失責任も問われます。ここではあくまで身分上、生活関係上一体をなすことが要件になりますので、監督していた保母さんなどの責任は過失相殺されません。
READ MORE

今日は相続の承認について書いていきます。
相続は被相続人の死亡によって開始されますが、その時点で相続人が決まります。法定相続人は被相続人の配偶者や子、直系尊属および兄弟姉妹に限られますが、その中の配偶者と最優先順位の者が相続を受けることになります。
https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/412
相続人が決まれば次は相続する財産を確定させます。あらかじめ公正証書遺言などで財産目録を作成してあれば良いのですが、ない場合は不動産登記簿や金融機関への調査を行うことになります。どちらにしても不動産は名義を変えなければいけないですし故人の口座も閉鎖しなくてはなりませんので、相続人が複数いる場合は必要な書類を整えなくてはなりません。相続人関係図や遺産分割協議書と同様に、財産目録も作成しておきましょう。
不動産や現金預金を調べて、プラスの財産がマイナスの財産より多ければ普通は相続することになりますし、明らかに借金の方が多ければ相続についても考えなくてはならなくなります。そういう場合を想定して民法では相続を受ける方法を規定し、選択の余地を残しています。
ただ選択するのには3ヶ月という期間が定められており、その期間内に決定をしなければいけません。その期間を「熟慮期間」といいます。ではその選択内容について見ていきましょう。
相続を受ける承諾することを、「承認」といいます。「承認」には「単純承認」と「限定承認」があり、これに「相続放棄」を加えて、相続の方法には3種類が規定されています。
「単純承認」とは文字通り単純に相続を受けることをいいます。マイナスの財産も含めた相続財産を、相続人全員がそのまま受け入れるものです。ですので万が一マイナスの財産の方が多かった場合でも、単純承認を選択した場合にはその負債等も無限に負わなければいけません。
自ら選択した場合はもちろん、自ら単純承認を選択しない場合でも、承認の意思表示をしないまま3ヶ月を経過してしまった場合や、相続財産の全部または一部を処分してしまった場合も単純承認をしたとみなされてしまいます。これらは法定単純承認と呼ばれます。大きな債務等のあることがわかっている場合には、くれぐれも熟慮期間を意識し、早めに財産目録を作成しましょう。
「限定承認」とは、マイナスの財産が多かった場合でも相続財産の限度内において債務を弁済すればよいというものです。債務が相続したプラスの財産を超えた場合には、支払いの義務はありません。ただ限定承認の場合は手続きが非常に面倒なものとなります。
まず財産目録を用意し、これを家庭裁判所に提出して申請することになります。申請する場合には共同相続人全員一緒にしなければなりません。ひとりでも反対をしたり単純承認をしてしまった場合にはすることができません。ですので、一人が財産を処分してしまった場合には、残りの共同相続人も申請することはできなくなってしまいます。なお共同相続人のうちの誰かが相続放棄をした場合には、残りの相続人全員で限定承認を申請することができます。
「相続放棄」とはマイナス財産が超過している等の理由で、相続を受けない選択をすることです。相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。ですので欠格や廃除の場合と異なり、代襲相続も認められません。
ただ相続放棄がなされた場合でも、その債務等が当然になくなるわけではありません。他の相続人に相続されていきます。プラスの財産は遺言等によっては法定相続分通りには配分されませんが、マイナスの財産は法定相続分通りに配分されます。ですので残った債務や連帯保証人の立場などは、他の相続人間で法定相続分通りに相続されることとなります。
相続放棄をしても単純に債務から逃れられるという性質のものではありませんので、放棄する際には事前に他の相続人と相談をし、のちのちの関係を壊さないようにしたほうが賢明だと思われます。
http://yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry46.html
READ MORE

前回記事の、共同相続人に成年後見人がいる場合や、行方不明者に財産管理人が指名された場合の遺産分割協議です。
当然これらの者は共同相続人の代理人になりますので、遺産分割協議に参加し、これらの者も含めた全員の合意で協議が成立することになります。
しかしこの成年後見人や財産管理人は共同相続人の権利代弁者でありますので、職責上、決して不利な内容で合意することはありません。
協議の成立に有効な条件であっても、むやみな妥協は代理人の責任問題になりますので、必ず法定相続分以上のものを主張されます。不必要な上積みは要求されませんが、客観的に見て常識的な数万円程度の譲歩しかなされません。
ですので遺言がない相続の場合に、共同相続人間で生前の故人が口にしていた意思とおりに遺産分割が合意されつつある場合でも、このような代理人が介入した場合には、法定相続分を下回る額で合意に至ることは容易ではありません。
READ MORE

今日朝の天気予報でGW後半の天気について話していました。1週間前には後半は荒れる見込みだと行っていたので、一安心ですね。土日休みの方は羽を伸ばして、サービス業や小売業の方は書き入れ時。世間全般、天気の効果は大きいですね。
ここのところ天気予報がよく当たるなと感じていますが、1週間程度先の予報では、雨予報が晴れに変わるケースが多いかなとも感じています。天気予報の精度の問題ではなく天候が落ち着いている年ということなんでしょうが、ここ3ヶ月では群馬の雨量も平年を若干下回っていますね。夏も暑いようですし、また館林の話題も多くなるでしょう。
GW後半は実家の静岡に帰ります。昔は子供4人とワイワイ帰っていましたが、世代も引き継がれてしまいましたね。日曜日にお土産のハラダのラスクを買い込んできます。
今日は2月に法制審議会より法務大臣に答申された、相続分野に関する民法改正について書いてみます。
民法については昨年120年ぶりに契約や債権関係の改正法が国会で成立し、2020年4月1日に施行されます。相続分野についてはこれまでも社会情勢の変化に即して改正が行われ、配偶者や非嫡出子の法定相続分の割合等が改められてきましたが、今回改正案のポイントは次のとおりです。
①配偶者の居住権を保護するための方策
②遺産分割に関する見直し等
③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
まず配偶者(以下妻とします)の居住権を保護するための方策についてみてみます。
現行法では被相続人の死亡後に被相続人名義の自宅に妻のみが居住していた場合でも、子がいた場合には妻の法定相続分は2分の1であり、仮に現金預金等の相続分が少なかった場合には、2分の1を超えた分の自宅の評価額分を子に渡さなくてはならないケースが出てきます。
妻と子の折り合いが悪かったりして子から請求された場合には、現実に妻が自宅を処分して相当分を子に渡すというケースもあるようです。
例として妻と子がひとりいるケースです。自宅の評価額が2000万円で預貯金が1000万円、相続額の合計が3000万円とします。この場合は妻も子も法定相続分は1500万円となります。預貯金を子がすべて相続しても500万円足りませんので、この場合は残りの500万円を子が妻に主張することができます。妻としてはやむをえず自宅を処分して、その分を子に渡すこととなります。これでは被相続人の死亡により妻が困窮する事態に陥ってしまいます。
今回の改正案では超高齢社会を見据えて、高齢の妻の生活や住居を確保するための内容が盛り込まれています。
まず要項に明記されたのが「配偶者居住権」です。文字通り妻が自宅に住み続けることのできる権利であり、所有権とは異なって売買や譲渡はできません。居住権の評価額は住む期間によって決まり、居住期間は一定期間または亡くなるまでのいずれかの期間で、子との協議で決めます。
前述のケースで妻の居住権の評価額が1000万円だったとしますと、妻は法定相続分1500万円のうち1000万円分の居住権と残り500万円分の預貯金を相続することとなります。子は自宅の評価額2000万円から居住権を引いた1000万円分の所有権と、預貯金500万円を相続することとなります。妻が住んでいるあいだの必要経費は妻が負担しますが、固定資産等の税制についてはまだ決まっていません。
次の遺産分割に関する見直し等についてですが、現行法では妻が自宅等を生前贈与されていたとしても、自宅も遺産分割の対象となってしまいます。ですので前述のケース同様となります。
要綱では結婚から20年以上の夫婦に限り、自宅が遺産分割の対象から除外されることになります。前述のケースでは遺産分割の対象となるのは預貯金1000万円のみとなり、妻と子にそれぞれ2分の1づつが相続されます。これも長年連れ添った妻への配慮であり、高齢で再婚した場合等と区別するものです。期間は延期間であって離婚を挟んでも問題はありませんが、事実婚や同性婚は対象となりません。
3つめは遺言制度に関する見直しです。昨今は自筆証書遺言への関心も高まってきているようですが、現行民法ではすべての文言が自署である必要があります。改正案では自筆証書遺言に関しすべてが自署である必要はなく、財産目録等はパソコン作成のものを添付することでも可能となります。ただし各ページへの署名押印は必要となります。
また自筆証書遺言の保管制度が新たに創設され、遺言者は自筆証書遺言を各地の法務局に保管するよう申請することができ、死亡後は相続人等が保管先法務局に対して遺言書の閲覧請求等をすることができます。その際法務局は、他の相続人等に対しては通知をだすこととなります。
法務局が保管していた自筆証書遺言は検認を要しません。ただ公正証書遺言と異なり、法務局保管の自筆証書遺言が必ずしも最終最新のものではないおそれは残りますので、探索や確認は必要となります。
4つめは遺留分制度に関する見直しです。遺留分減殺請求権の効力については、受遺者等に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになり、権利行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するという考え方が採用されます。
また遺留分減殺請求の対象となる遺贈・贈与が複数存在する場合については現行法の規定に加えて、減殺の割合についてはこれまで解釈によっていたものが、今回案では明文化されています。遺留分の算定方法については現行法の相続開始の1年前にした贈与に加え、相続人贈与は相続開始前の10年間にされたものが算入対象となります。
5つめは相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直しについてです。これは遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産等は、登記をしなければ第三者に権利を主張できないというものです。
最後に相続人以外の者の貢献を考慮するための方策についてです。現行法では寄与分については相続人にのみ認められていましたが、改正案では相続人以外の被相続人の親族が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる こととなります。
被相続人の親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の血族の配偶者が対象となります。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/
READ MORE
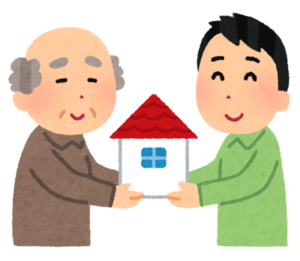
今日は遺贈と死因贈与について書いていきます。
相続は相続人にしかすることができません。そもそも相続とは、被相続人が亡くなった場合に、法律で決まっている者に財産を承継させる制度です。相続人は配偶者、子、直系尊属、兄弟姉妹のみと民法で決まっており、これらが決められた順位で相続できるのみです。
もしこれらの者が一人もいない場合は、相続財産を管理する者として家庭裁判所から弁護士等が選任されることとなります。そこで本当に相続人がいないかの調査がなされ、それでも見つからない場合には家庭裁判所に認められた場合に限り、被相続人の世話を相当程度した者が一部の財産を譲受けることができます。それらが完了すると、最終的には財産はすべて国庫に帰属することとなります。
さて、相続人がいるいないにかかわらず、あなたがとても世話になった方がいるとします。その方の恩に報いるにはどうしたらよいでしょうか。ここからの話は相続人についてもすることができますが、相続人の場合は「寄与分」ということで、相続人間の協議において相続分の上乗せをすることができますので、ここでは除いて話を進めます。
あなたがもし遺言書を残さないで亡くなった場合には、相続人全員で相続財産の分配についての協議を行うことになります。この場合は参加できる相続人は当然法律によって定められた者のみ(あとで述べる包括受贈者を除いて)となりますので、たとえあなたがとてもお世話になり、心情的に財産を分け与えたい方でもそこには加わることはできません。
たとえば同居しているお子さんのお嫁さんなどがこれに当たります。ですのでもし相続以外で財産をあげたい場合は、あなたのその意思を明確に残す必要があります。当然法的効果のあるものでないと、他の相続人から否定された場合には、その者も権利を主張することができなくなってしまいます。ここで効果を発揮するものが一般的には遺言書ということになります。
遺言書によって相続人以外の者(相続人にもすることができますが)に財産を与える場合には、「遺贈」という形をとります。これはあなたがその方に対してする、一方的な単独行為になります。自分が死んだらその者に財産をあげるという内容になります。一方的な行為ですので、遺贈する者に事前に伝える必要はありません。
遺贈とは別にもうひとつ、相続によらずに死亡を契機として財産を与える行為に、「死因贈与」があります。これは財産をあげる者とあらかじめ契約を交わしておき、自分が死んだらあげるというものです。契約といってもこれには特に方式はなく、契約書等も必要ありません。口約束だけでも効果を発揮します。しかし、証拠がない場合はトラブルのもとになる場合もあります。もし死因贈与をする場合には、文書等に記しておくことも考えたほうが良さそうです。
死因贈与は遺贈と異なり、あなたの亡くなる前から相手の方もその内容を承知していることになります。ここで別に遺言書が残されており、そこに書かれていた内容がその死因贈与契約と異なっていた場合はどうなるのでしょうか。
この場合は遺言書の効果と同様に、後からされたものが有効となります。遺言書の書かれた日付が後であれば、遺言書によって前の死因贈与契約が破棄されたこととなりますので、死因贈与契約は無効となります。逆も然りです。このように日付等の証拠の裏付けが必要になる場合もありますので、本当に必要な死因贈与の場合は、口頭ではなく文書で日付等を明記しましょう。この2つについて次回詳しくみていきます。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry65.html
READ MORE