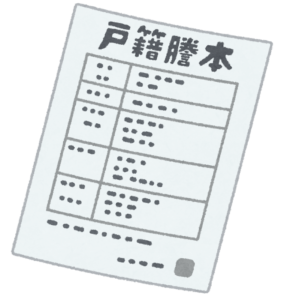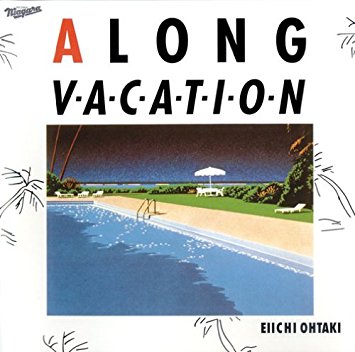戸籍を取得し相続人を確定していく中で、袋小路に出くわす場面があります。それは疎遠な共同相続人がいる場合に、その方を戸籍で法定相続人であることを確認し、存命かどうかの住所追跡をしていく中で、足取りが途絶えてしまうことです。
関係性が確認できた際はその方に遺産分割協議の旨をお伝えする文書なりを発送していくわけですが、最終住所地に文書を発送しても戻ってきてしまう場合があります。書留と通常郵便2パターンで送ったりもしますが、返送されるということは最終住所地に住んでいない、地番変更等で番地自体が現在は存在しない。あるいは建物自体がないどこにいるかわからないと言うことです。
この場合はその土地の登記確認をし、土地の現在の所有者や建物の存在等を確認します。そこから次の状況を推測していくわけですが、こちら側の血縁者から情報を得られない以上、次の手立てはその方のもう一方の血縁者から事情を聞くしか手立てはありません。この場合はさらに難易度が上がります。例えば兄弟相続の代襲者(妹等の代襲者)で、甥の父方の存命の血縁者をたどる場合などです。
行政書士にご依頼をいただいた場合は、職務上戸籍を取得することができますが、もう一方の血縁者は被相続人や依頼者からの縁が薄くなるので、個人情報保護の観点から、戸籍を役所からいただけない場合が出てきます。理由を説明してもいただけない役所もあります。そうなったら相続人の追跡は終わってしまいますが、複数の関係者がいる場合は、どこかの役所で戸籍や住民票を取得でき、その血縁者から相続人の消息を聞ける場合があります。ですので、ご依頼をいただいた場合は、手段がなくなるまで手を尽くすことになります。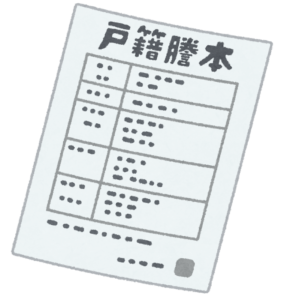
ここでその相続人の行方をたどることができなかったり、行方不明であることがわかった場合は、手間はかかりますが、裁判所に財産管理人の申し立てをしたり失踪宣告を行うことによって相続を完了させていきます。
建物の滅失登記がなされ(取り壊し)て足取りがわからなくなっても、前述のとおり関係者に連絡が付くことによって消息がわかることがあります。具体的には認知症などによって長期に入院し、住居に戻る見込みがないので建物を取り壊してしまった場合などです。このような場合は成年被後見人等が付いている場合も多いので、その方の後見人などと遺産分割協議を進めていくことになります。
Related Posts
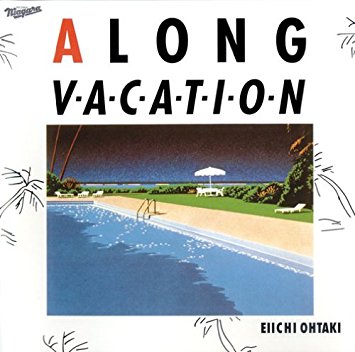
大瀧詠一さんはご存知でしょうか。ええもちろんあの大瀧詠一さんです。ちょっと古い話になるので年齢が分かってしまいますが。
子供の頃三ツ矢サイダーのCMの歌が新鮮でしたが、手塚さとみさんの記憶が強かったんですね。でも調べたら大瀧さんの歌が使われていた年は、風吹ジュンさんと秋吉久美子さんのようですね。どちらもとても可愛くて記憶に残っています。
大瀧詠一さんを本格的に好きになったのはやはり1981年3月21日発売の「A LONG VACATION」からですが、今でもよく聞いています。その時々の思い出もよみがえり、今でも新鮮ですしとても甘酸っぱい(古いですが)アルバムです。
2年前に「DEBUT AGAIN」が発売されたときはアマゾンで予約して買いましたが、この中の「風立ちぬ」も想い出深く、今でもカラオケでは歌います。言うまでもなく松田聖子さんの歌ですが(一番好きな歌です)、「DEBUT AGAIN」の音源は、大瀧さんが一度だけコンサートで歌ったライブでのものですね。YouTubeでは聞いていた幻の音源ですが、1981年12月3日に渋谷公会堂で行われたあの伝説の「ヘッドフォン・コンサート」からのライブ音源です。
実はこのコンサートは見に行きましたので、今でも記憶に残っています。大学1年の暮れでしたか。全体の記憶はあいまいなんですが、この曲のファンだったこともありよく覚えています。かなり照れながらのMCでした。
席はステージをやや右手に見る2階席でした。と、このあといろいろ書こうと思って何気なしに検索したら、私の記憶より詳しく書いてあるブログがありましので、そちらを貼っておきます。
https://blogs.yahoo.co.jp/tsus_h/55958754.html?__ysp=5aSn54Cn6Kmg5LiAIOODmOODg%2BODieODleOCqeODsw%3D%3D
前振りが長くなりましたが、今日は遺言書の「後継ぎ遺贈」について書きます。
後継ぎ遺贈とは、「ある資産をAさんに遺贈するが、Aさんがもし亡くなった場合はAさんの相続人ではなく、第二次的に他のBさんに遺贈させる」というものです。
心情的にも実務的にもありがちだと思いますが、例えば、Aさんは普段からとても親しい間柄だし優秀なので資産を引き継がせたいが、もしもの場合にはその息子には引き継がせず、その資産を活かせる別のBさんに贈りたいという趣旨のものです。
この種の遺言の効力については諸説ありますが、結論からいうとその有効性をめぐって争いになる可能性が高く、できれば避けたほうが良いと思われます。理由として後継ぎ遺贈については、民法には法定相続のような規定がなく、是非の判断はその解釈に委ねられるからです。
どうしてもご自分で筋道を付けておきたい場合には、後継ぎ遺贈によって不確実なものやトラブルの種を残すより、信託等の別の方法を検討されることをアドバイスいたします。
READ MORE

今日は遺贈と死因贈与についてもう少し詳しく書いてきます。
まず「遺贈」についてですが、遺贈される者を「受遺者」といいます。相続と同様、遺贈も被相続人の死亡によって開始されます。
受遺者になる要件はひとつ、遺言によって遺贈をする旨の内容が残されていることですが、被相続人の死亡時に遺贈をされる者が既に死亡していた場合は、受遺者となることはできません。また受遺者については代襲の定めはありませんので、この場合はその子等に権利が移ることもありません。遺贈はなかったことになります。
一方、被相続人の死亡時には遺贈をされる者がまだ生存しており、その後すぐに死亡した場合については、遺贈の効果は有効となります。ですのでその財産は受遺者の子等に相続されることとなります。
遺贈には2つのものがあります。ひとつは「包括遺贈」とよばれるもので、財産の全部または一定の割合を指定してする遺贈です。この場合は具体的な財産は決められていないことになりますので、他の相続人がいる場合は、これらの者と一緒に遺産分割協議に参加しなくてはなりません。
また包括遺贈の特徴は、相続同様プラスの財産のみならずマイナスの財産も含むことです。マイナスの財産が多い場合もありますので、これも相続同様、受遺者に受ける受けないの選択権が設けられており、3ヶ月の期間内に放棄することも認められています。放棄する場合は、家庭裁判所に申請をする必要があります。
もうひとつは「特定遺贈」とよばれ、特定の財産を指定してなされる遺贈です。特にマイナスの財産を指定して行われない限りは、プラスの財産のみの遺贈となります。特定遺贈では遺産分割協議への参加もする必要はなく、また遺贈の承認や放棄の意思表示の期間も特に定められてはいません。しかし他の相続人が協議をすすめる必要性もあるため、これらの者から早期に意思表示を求められる場合が多くなります。
遺贈の場合の税金については、贈与税ではなく相続税として申告する必要があります。また相続人ほどの権利は認められていませんので、不動産の場合は登記をしなければ第三者に対抗できず、農地であった場合は農地転用が必要となります。
遺贈には「負担付き遺贈」と呼ばれるものがあります。これは、与えた条件(負担)を履行した場合のみ遺贈が行われるという性質のものです。たとえば、被相続人の配偶者の面倒を見ることを条件に遺贈を行う、といった場合がこれに当たります。
では負担が履行されなかった場合はどうなるのでしょうか。
負担を履行しなかった場合には、多くは遺言執行者や相続人から、遺贈の取り消しを請求されることとなります。この場合の遺贈する予定だった財産は負担付き遺贈者には渡されず、他の相続人に渡ることとなります。相続人が複数いる場合は、この部分について再度分割協議が行われます。
では負担の大部分は履行したが、全部の履行は行われなかった場合はどうでしょうか。判例では遺贈が認められた場合があります。当然負担を行った程度だけではなく、様々な状況も異なると思いますので、個別具体的に判断する必要があるということでしょう。
「死因贈与」とはどのようなものでしょうか。財産を与える者を「贈与者」、受ける者を「受贈者」とよびますが、これはお互いの契約になりますので、受贈者が一方的に放棄することはできません。死因贈与の際に納める税金も遺贈同様、贈与税ではなく相続税になります。
なお死因贈与の場合も条件付きの贈与があり、これを「負担付き死因贈与」とよびます。負担付き贈与の場合は、受贈者が亡くなる前であれば一方的に破棄することができますが、負担が履行され始めた場合には撤回することはできません。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry65.html
READ MORE

相続分野の改正民法が、本年7月1日に施行となります。
すでに施行された「自筆遺言書の方式緩和」、2020年4月1日施行の「配偶者の居住権を保護するための方策(短期、長期)」、2020年7月10日施行の「自筆証書遺言の保管制度」を除き、2019年7月1日より施行されます。
あと1月ほどとなりましたが、これには「遺留分制度」や「相続人以外の者の貢献」に関する改正が含まれますので、下記リンクより一度ご確認下さい。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry69.html
READ MORE

今日は共有について見てみます。
これも相続分野で頻出する言葉となりますが、「共有」とは、数人の者が共同所有の割合である「持分」を併せて1つの物を所有することを言います。単純に言えば、数人で1つの物を所有することですね。
「持分」とは今述べたように、共有物に対する所有権の割合のことです。持分の割合はそれぞれの意思表示や法律の規定(法定相続分等)により決まりますが、その割合が不明な場合は各共有者平等の持分であると推定されることになります。
持分は各共有者が原則自由に処分できます。共有目的物の利用については各共有者は共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができます。
例えば1台の自動車を3人で共有しているとしますと、3人それぞれがその自動車を自由に使用することができます。しかし異なる目的を同時に行うことはできませんので、必要な場合は各自の持分に応じた使用時間配分を決められるということです。自動車を購入するのにAさんがその代金50%、BさんとCさんが25%を出資していたとすると、その割合で使用時間を決められるということになります。
相続に当てはめると、配偶者と子供が2人いる場合は配偶者が50%の持分であり、2人の子供はそれぞれ25%ずつの持分ということになりますね。
また持分は、使用する共有者の1人がその持分を放棄した場合や、共有者が死亡した際に相続人がいない場合はその持分は他の者に帰属することとなります。
共有物には日々の利用についても制約がありますので、それらについても見ていきましょう。
共有物の利用については、その内容や利用状況から次の3つに区分されています。
①保存行為
②管理行為
③変更行為
になります。「保存行為」とは修理や修繕など、共有物の現状を維持する行為であり、各自が単独で行うことができます。なお現状維持という観点からの妨害排除請求や消滅時効の中断なども共同で行われる必要はなく、各自が単独で行うことができます。
次の「管理行為」とは、共有物の性質を変えることなく利用したり改良する行為とされています。これには共有物の賃貸やそれに関する解除や取り消し行為などがありますが、この場合は単独で行うことはできず、共有の過半数の合意が必要になります。
過半数とは人数が基準になるものではなく、持分の価格を基準にしての過半数になります。Aが10でBが20の持分価格を有していても、Cが50を有する場合には必ずCの承諾が必要になります。
「変更行為」とは共有物の性質や形状を変更することを言います。具体的には共有物を売却したりその全部に抵当権等を設定する場合がこれに当たりますが、この場合は共有者全員の同意が必要になります。
最後に「共有物の分割」について見てみましょう。共有物については、各共有者はいつでも共有物の分割を請求することができます。分割の方法は現物分割、代金分割、価格賠償の3つがあります。
ここでの「現物分割」とは現物そのものを分割すること、「代金分割」とは共有物を売却してその代金を分割する方法です。「価格賠償」とは共有物を分割した際に持分に満たない者に、超過した者からその金額を補填することを言います。
共有分割の協議が整わない場合は遺産分割協議同様、裁判所に分割を請求することになります。なお遺言書による場合が多いですが、共有物を5年を超えない期間で分割を禁止する特約を付けることもできます。
READ MORE

本年平成30年7月6日の参院本会議で、相続分野に関する改正民法が可決成立しました。約40年ぶりの大幅見直しとなりますが、一部の条項を除き、1年を経過しない来年の7月までに施行される予定です。
今回の見直しについてはかねてより問題化されていた、超高齢社会における配偶者への居住権の確保等が主軸になっています。主な改正点は次のとおりです。
①配偶者の居住権を保護するための方策
②遺産分割等に関する見直し
③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続の効力に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
になります。
では具体的に各内容について見ていきましょう。
第1の配偶者の居住権保護については、短期的な保護と長期的な保護の両面から確保されることとなりました。
まず短期的な方策について見てみましょう。現行法における配偶者の居住権については判例から、相続開始時に被相続人所有の建物に居住していれば、原則被相続人と相続人の間で使用貸借契約が成立していたと推認され、そのまま居住することができます。しかし第三者にその建物が遺贈されてしまったり、配偶者が居住することに被相続人が反対の意思表示をしていた場合には、使用貸借が推認されずに居住が保護されないことになってしまいます。
その事態を回避すべく、「配偶者短期居住権」というものが設けられました。これは配偶者が相続開始時に被相続人の建物に無償で住んでいた場合について、
①配偶者が居住建物の遺産分割に関与する場合は、居住建物の帰属が確定するまでの間の期間。ただし帰属が6ヶ月以内に確定した場合でも、最低6ヶ月は保障される
②居住建物が第三者に遺贈された場合や配偶者が相続放棄をした場合には、居住建物の所有者から消滅請求を受けてから6ヶ月間、配偶者は居住建物を無償で使用する「配偶者短期居住権」を取得する
というものです。
被相続人の建物に無償で住んでいなかった場合にはこの権利は取得できないことになりますが、権利を取得すれば必ず最低6ヶ月間は居住が保護されることになります。
長期的な方策では、「配偶者居住権」というものが新設されました。これは、配偶者が相続開始時に居住していた被相続人所有の建物を対象として、終身または一定期間の配偶者の建物使用権を認める内容となります。配偶者居住権は「物権」であり、「登記」することもできます。しかし売買することや譲渡をすることはできません。
現行制度では遺言書がない相続でその相続財産の多くが土地建物等の不動産だった場合など、法定相続分の規定によって、配偶者が建物以外の預貯金等を取得できなかったり、あるいは建物を売って共同相続人に金銭を渡さなければならないケースも出てきます。
配偶者とその子供が1人いた場合を例に挙げますと、法定相続分は配偶者1/2、子1/2(複数いる場合はその子らで等分します)になりますので、相続財産が自宅(土地建物)2000万円、預貯金が2000万円の場合では総額4000万円となり、配偶者が自宅を相続すると預貯金の2000万円はすべて子の相続分となります。
預貯金が1000万円だったとしますと相続合計は3,000万円になりますので、1/2ですと1500万円になり、配偶者が自宅を相続した場合で子から請求があった場合は、子に500万円を支払わなくてはなりません。これでは相続によって配偶者が住む自宅を失いかねません。
それを解決するために設けられた制度が「配偶者居住権」になります。これは相続された自宅を、「配偶者居住権」と「負担付き所有権」に分け、配偶者の自宅の相続額を低く設定する効果が生じます。
先の相続総額4000万円の例で言いますと、配偶者居住権が1000万円とされればその居住権をもって住み続けることが可能となり、残りの負担付き所有権を子が相続した場合には、配偶者の相続額は2000万円ですので、1000万円分の預貯金を相続できるという仕組みになります。子には負担付き所有権1000万円と預貯金1000万円が相続されることとなります。
どういうことかと言いますと、相続が開始した年齢にもよりますが、配偶者はその先何十年も生きることはないと仮定し、平均余命から割り出した住み続けられる間の価値が配偶者居住権になります。あるいは何年か後には老人ホームに移るので、自宅にはそれまでしか住まない、という選択肢もあるかもしれません。配偶者が亡くなった場合は自宅は子のものとなりますので、それが負担付き所有権となります。
この規定によって、現在の自宅の価値がまるまる配偶者の相続分になってしまい、その他の財産を相続する権利を失ってしまうことから回避されることになります。
とはいえこの改正内容については、負担付き所有権が付いている建物の資産価値の低下や売買する際の市場性の問題(買い手がいない)、配偶者居住権と抵当権の問題など権利関係が複雑になっており、実際の運用面では非常にやっかいな問題をはらんでいるようです。
相続人間でこのような制度を用いざるを得ない関係性があるようでしたら、遺言を残しておくことが最善策だと思われます。
これらの算出は個別具体的になされるものですが、単純に式で表すと、建物敷地の現在価値-負担付き所有権=配偶者居住権の価値ということになります。よろしいでしょうか。
では第2の遺産分割に関する見直しについて見てみます。これについては次の3つの内容が含まれています。
①配偶者保護のための持戻し免除の意思表示推定規定の新設
②仮払い制度等の創設・要件明確化
③遺産分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
です。
①については、婚姻期間が20年以上であれば、配偶者に居住用の不動産を生前贈与または遺贈した場合でも、原則として計算上「特別受益」(遺産の先渡し)を受けたものとして取り扱わなくてよいという内容になります。
現行制度では、被相続人が配偶者のためを思って自宅を生前贈与していた場合でも、「持戻し制度」というものによってその自宅は「特別受益」とされ、遺言による「持戻し免除」の表示がない限り、相続財産に合算されてしまいます。
どういうことかと言うと、先ほどの総額4000万円の例で見ますと、現行法では生前贈与された2000万円の自宅も相続総額に含まれることとなります。配偶者の相続分はこの自宅のみとなってしまい、残りの預貯金2000万円はすべて子に相続されることになります。
これでは生前贈与した意図が相続に反映されないこととなってしまいます。今回の見直しでは、20年以上法律上の婚姻期間がある者については、その貢献に報い、老後の生活を保障すべきものとして、「持戻し免除」の表示がなくても表示があったと推定して(被相続人の意思の推定規定)、遺産の先渡しとして扱わずに相続財産総額に含めないことになります。
先の例で言いますと、遺産総額は自宅を含まない預貯金2000万円となり、配偶者と子がそれぞれ1000万円ずつ相続することになります。
次に②の仮払い制度について、現行法では判例から、遺産分割が終了するまでの間は、相続人単独では預貯金の払い戻しをすることができません。相続される預貯金債権は相続人全員の共有債権になりますので、それぞれの相続分が確定するまでは生活費や葬儀費用、相続債務の弁済などの必要性があっても払い戻しができず、相続人が立替える必要がありました。
今回の見直しにおいてはこれが緩和され、2つの仮払い制度が設けられることとなりました。
ひとつは預貯金債権に限り、家庭裁判所の仮処分の要件が緩和されます。従来も訴えにより認められることはありましたが、見直しによって、仮払いの必要性があると認められる場合は他の共同相続人の利益を害しない限り、家庭裁判所の判断(手続き)で仮払いが認められるようになりました。
もうひとつは、家庭裁判所の判断を経なくても払い戻しが受けられる制度が新たに設けられました。これは相続人としての相続分であれば、そのうちの一定額について単独で払い戻しが認められるという制度です。具体的には、(相続開始時の預貯金総額×1/3×払い戻しを受ける共同相続人の法定相続分)まで、払い戻しが認められることとなります。
③の相続開始後の共同相続人による財産処分についてですが、現行法では特別受益のある相続人が遺産分割前に遺産を処分してしまった場合には、他の共同相続人に不公平な結果が生じてしまいます。
例を挙げますと、配偶者がなく子が兄弟2人あったとします。相続される預貯金が2000万円で、長男に2000万円が生前贈与されていた場合には、この贈与分は持戻しとなり、相続総額は4000万円になります。長男にはすでに2000万円が渡されていますので、今回の預貯金2000万円はすべて次男に相続されることとなります。
しかしこの2000万円のうち1000万円分を長男がだまって引き出していた場合には、残りの預貯金が1000万円となってしまいます。すると相続預貯金総額はもち戻しを含めて3000万円となり、法定相続分にしたがって兄弟それぞれが1500万円ずつ相続します。ここでは長男はすでに2000万円を贈与されていますので相続分は0円となり、次男が預貯金総額の1000万円を相続することになります。
これでは長男が贈与分の2000万円と引き出し分の1000万円の合わせて3000万円を受け取ることになり、次男は1000万円しか受け取れず不公平な結果となってしまいます。この場合は裁判に訴えても、結論から言うと次男の受け取り分は本来の2000万円に届くことはありません。
その不公平を是正するために、遺産を処分した者以外の同意(この例では次男)があれば、処分したもの(長男)の同意を得なくても処分した預貯金(1000万円)を遺産分割の対象とすることができる、という法律上の規定が加えられることとなりました。
これによって、たとえ共同相続人の一人がこっそり分割前の預貯金を引き出してしまった場合でも不公平が起こらない制度となりました。今の例で言うと、相続財産の総額は4000万円とされ、次男は1/2の2000万円を相続することができます。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/
次に第3の遺言制度の見直しについて見てみましょう。これには次の3つの内容があります。
①自筆証書遺言の方式緩和
②遺言執行者の権限の明確化
③法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(民法ではなく遺言書保管法によります)
です。
①について、現行法で自筆遺言に法的効果を生じさせるには遺言書の全文を自書する必要があり、財産が多数ある場合には相当な負担が伴いました。
今回の見直しでは、自書によらないパソコンなどで作成した財産目録を添付することができ、合わせて銀行通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を添付することでも法的効果が生じることとなります。
②の遺言執行者の権限の明確化については、遺言執行者の一般的な権限として、遺言執行者がその権限内において遺言執行者であることを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずる、ということが明文化され、また特定遺贈又は特定財産承継遺言(遺産分割方法の指定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における、遺言執行者の権限等が明確化されました。
③について、現行法では自筆証書遺言の管理は遺言者に任されていましたが、見直しによって法務局という公的機関に保管できる制度が創設されました。
この制度では相続開始後に相続人が遺言書の写しの請求や閲覧をすることが可能となり(その場合は他の相続人にも遺言書の保管の事実が通知されます)、紛失や改ざんの恐れがなくなることになります。
保管については申請者が撤回することもできます。なおこの制度では現行自筆証書遺言で負担になっている、「検認」の規定は適用されません。
第4の遺留分制度に関する見直しについて見てみましょう。これも2つの内容からなります。
①遺留分減殺請求権から生じる権利を金銭債権化する
②減殺請求がなされた場合に、請求された側が金銭を直ちに用意できないときは、請求された側である受遺者などが裁判所に請求することによって、金銭債務の全部または一部の支払いについて、相当の期限を与えられる
というものになります。
①の遺留分減殺請求の金銭債権化とは、現行法では請求がなされた際にその財産が金銭でなかった場合には、共有状態が生じてしまい事業承継などの支障になってしまいます。その状況を回避するために、減殺請求された債権は金銭で支払われることを明文化したものです。
②については遺贈などされた財産の額が大きい場合であっても、実際に別途金銭を用意できるとは限りませんので、この内容も加えられています。
第5の相続の効力等に関する見直しですが、これは"相続させる旨の遺言等により承継された財産については、登記なくして第三者に対抗することができる"、ことについての見直しとなります。
どういうことかと言いますと、登記なくして第三者に対抗できるという内容自体は問題ないのですが、相続人の債権者において債務回収の差し押さえなどが発生する場合は、通常法定相続分を想定して計算することになります。ここで遺言によって法定相続分を下回る内容でしか相続されなかった場合は、債権者等の第三者の取引の安全が確保されないことになります。
この観点から今回の見直しにおいては、法定相続分を超える部分の承継については、登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないと改正されました。登記されれば債権者もその内容について知ることができますので、取引の安全性が確保されることになります。
法定相続分までは現行法とおり、登記なくして第三者に対抗することができます。
第6の相続人以外の者の貢献を考慮する方策ですが、相続は相続人にしかすることができません。相続人以外の者には、例えば親身になって世話をしてくれた長男の妻にも相続はなされません。これらの者に財産を贈りたい場合には贈与によるか、遺言書による遺贈や死因贈与の方法をとります。
しかしこの遺言書がなかった場合には、どんなに被相続人に尽くした者であっても、遺産分割協議に加わることはできません。この不公平を見直すべく、特別の寄与の規定が設けられました。
これは相続人以外の親族が、被相続人の療養看護等を行った場合に、一定の要件のもとで、相続人に対して金銭の支払いを請求することができるという制度になります。請求できる親族とは6親等以内の血族および配偶者、3親等以内の姻族を言います。
遺産分割は現行とおり相続人だけで行われ、それとは別に特別の寄与があった者が相続人に請求を行ないます。これには算出式などありませんので、当事者同士の話し合いになります。
以上が改正の内容となりますが、現時点では改正法全体の具体的な施行日は決まっていませんが(公布の日から1年以内)、自筆証書遺言の方式緩和(自書以外の目録可)は平成31年1月13日に施行されます。また自筆証書遺言の保管制度は、公布の日から2年を超えない範囲内での施行とされました。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/
READ MORE
今日は普通養子縁組の解消について書いていきます。
縁組も婚姻同様、他人同士の意思の合致による行為になりますので、お互いの意思が合致しなくなった場合も、婚姻同様にその関係が解消されることとなります。
婚姻の場合の離婚に当たるものが、「離縁」になります。「離縁」には
①協議離縁
②裁判離縁
があります。
「協議離縁」とは、当事者同士の協議によってするものを言います。離縁の成立要件は縁組の時と同様に、形式的要件と実質的要件になります。形式的要件はこれも届出になります。実質的要件は当事者間の、養親子関係を終了させる意思の合致になります。
未成年や成年被後見人の場合は通常単独で協議を行うことはできませんが、未成年であっても15才以上の者は単独で離縁をすることができ、成年被後見人の場合も本心に復している場合は単独ですることができます。
配偶者のある者が未成年者と縁組をするには、夫婦揃っての縁組が必要でしたが、離縁についても夫婦がともにしなければなりません。
縁組の当事者の一方が死亡した場合はどうでしょうか。この場合の一方の生存者は、家庭裁判所の許可を得て離縁することができます。これを「死後離縁」と言います。養親子関係自体は当事者の一方または双方が死亡すれば消滅しますが、法定関係は存続しますので、相続も発生します。
また配偶者死亡の時同様、縁組によって生じた法定血族関係は当然には消滅しませんので、これらの関係を消滅させるには、家庭裁判所の許可が必要になります。
離縁の無効や取り消しの場合も、婚姻の場合と同じです。離縁意思の合致を欠いたり、代諾権のない者が代諾した場合は無効になります。
また詐欺や強迫によって行われた離縁は取り消しをすることができます。この場合は詐欺を発見し、または脅迫から免れた時から6ヶ月以内に、家庭裁判所に請求をします。取り消しの効果は離縁の時点に遡及することとなり、離縁はなかったものとなります。
「裁判離縁」は、協議離縁が成立しなかった場合に、家庭裁判所への請求によってなされます。裁判離縁の成立する要件としては、
①他の一方から悪意で遺棄されたとき
②他の一方の生死が3年以上明らかでないとき
③縁組を継続し難い重大な事由があるとき
になります。
離縁の効果によって、養親子関係および法定親族関係が、離縁の日から消滅することになります。
また養子は離縁前の氏に戻ることになり、原則として離縁前の戸籍に入ることになります。離婚の場合の氏については婚氏続称という制度がありますが、離縁にもあります。
離縁の場合に離縁前の氏を継続する時は離婚よりも要件は厳しいものとなり、縁組が7年以上継続されている必要があり、離縁の日から3ヶ月以内に届出を行う必要があります。
READ MORE

今日は相続にも大きく関係してくる、親族というものについて書いていきます。
相続を受けることのできる者(相続人)は「相続人」である「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」になりますので、親族の範囲を見た上で、これらの者がどの位置にいるのかを見てみます。
また今回成立した相続関係の民法改正において、「相続人以外の親族の貢献を考慮する方策」が加えられましたので、今まで以上に「親族」という言葉が使われる機会が多くなると思います。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry69.html
「親族」とはどのようなものを言うのでしょうか。民法における「親族」とは、次の者を言います。
①6親等以内の血族
②配偶者
③3親等以内の姻族
です。
まず「血族」とは、血縁関係のある者相互間(誰から見てもお互いに)および、法的に血縁があると制度上みなされる(擬制)者相互間を言います。前者を「自然血族」、後者を「法定血族」と言います。
「自然血族関係」は出生によって生じ、死亡によって終了します。「法定血族関係」は養子縁組によって生じ、離縁や縁組みの取り消しによって終了します。
次の「配偶者」は、婚姻によって戸籍上の地位を得た者になりますが、配偶者は血族にも姻族にも属さず親等もありません。
「姻族」とは「配偶者側の血族あるいは血族の配偶者相互間」を言います。例えば配偶者の父や、本人の父の兄弟(叔父)の配偶者は姻族になります。「姻族関係」は配偶者を通じての関係になりますので、配偶者の一方の血族と他方の血族は姻族にはなりません。具体的に言うと、本人の父と配偶者の父は姻族関係には当たりません。
また姻族関係は婚姻によって生じ、離婚によって終了することになります。離婚した元配偶者の親とは知り合いではあっても、法的つながりはなくなるということです。これは離婚の場合であり、死別の場合は届出を行わない限りは姻族関係は当然には消滅しません。
では先に出てきた「親等」とはどのようなものでしょうか。
「親等」とは親族間の遠近度を比較する尺度であり、親族間の「世代」によって決まります。本人から見て「世代」がひとつ変われば1親等という数え方をします。
相続人に当てはめて見ますと、配偶者に親等はありません。子と直系尊属(父母)が1親等、孫や祖父母は2親等になります。兄弟姉妹は親を経由して下がりますので、これも2親等と数えます。本人の叔父や叔母は祖父母を経由しますので3親等、その子であるいとこは4親等になります。
親族については世代をまたがる垂直の広がりと、直系から枝分かれをした横への広がりがあります。
縦への広がりで見てみますと、本人から世代が上の者たちを「尊属」、世代が下の者たちを「卑属」と言います。ですので父は尊属、子は卑属になります。兄弟姉妹やいとこは世代が同じですので、尊属にも卑属にも当たりません。
横への広がりで見てみますと、本人から垂直に遡ることのできる父母や祖父母や曽祖父母、あるいは垂直に下がることのできる子や孫やひ孫などは「直系」になります。
縦横併せてマトリックスで見ますと、上の世代を「直系尊属」、下の世代を「直系卑属」と言います。垂直から枝分かれをした叔父叔母などは「傍系」と言います。これも上の世代を「傍系尊属」、下の世代を「傍系卑属」と言います。
整理してみますと、血族には直系血族と傍系血族があり、直系血族には直系尊属と直系卑属があります。また傍系血族にも傍系存続と傍系卑属があることになります。姻族にも同様の、直系傍系、尊属卑属の関係があります。
改正民法の特別寄与に関しては、具体的に権利の範囲にあるかは事案ごとに確認を要するとことになります。
READ MORE

今日朝の天気予報でGW後半の天気について話していました。1週間前には後半は荒れる見込みだと行っていたので、一安心ですね。土日休みの方は羽を伸ばして、サービス業や小売業の方は書き入れ時。世間全般、天気の効果は大きいですね。
ここのところ天気予報がよく当たるなと感じていますが、1週間程度先の予報では、雨予報が晴れに変わるケースが多いかなとも感じています。天気予報の精度の問題ではなく天候が落ち着いている年ということなんでしょうが、ここ3ヶ月では群馬の雨量も平年を若干下回っていますね。夏も暑いようですし、また館林の話題も多くなるでしょう。
GW後半は実家の静岡に帰ります。昔は子供4人とワイワイ帰っていましたが、世代も引き継がれてしまいましたね。日曜日にお土産のハラダのラスクを買い込んできます。
今日は2月に法制審議会より法務大臣に答申された、相続分野に関する民法改正について書いてみます。
民法については昨年120年ぶりに契約や債権関係の改正法が国会で成立し、2020年4月1日に施行されます。相続分野についてはこれまでも社会情勢の変化に即して改正が行われ、配偶者や非嫡出子の法定相続分の割合等が改められてきましたが、今回改正案のポイントは次のとおりです。
①配偶者の居住権を保護するための方策
②遺産分割に関する見直し等
③遺言制度に関する見直し
④遺留分制度に関する見直し
⑤相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直し
⑥相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
まず配偶者(以下妻とします)の居住権を保護するための方策についてみてみます。
現行法では被相続人の死亡後に被相続人名義の自宅に妻のみが居住していた場合でも、子がいた場合には妻の法定相続分は2分の1であり、仮に現金預金等の相続分が少なかった場合には、2分の1を超えた分の自宅の評価額分を子に渡さなくてはならないケースが出てきます。
妻と子の折り合いが悪かったりして子から請求された場合には、現実に妻が自宅を処分して相当分を子に渡すというケースもあるようです。
例として妻と子がひとりいるケースです。自宅の評価額が2000万円で預貯金が1000万円、相続額の合計が3000万円とします。この場合は妻も子も法定相続分は1500万円となります。預貯金を子がすべて相続しても500万円足りませんので、この場合は残りの500万円を子が妻に主張することができます。妻としてはやむをえず自宅を処分して、その分を子に渡すこととなります。これでは被相続人の死亡により妻が困窮する事態に陥ってしまいます。
今回の改正案では超高齢社会を見据えて、高齢の妻の生活や住居を確保するための内容が盛り込まれています。
まず要項に明記されたのが「配偶者居住権」です。文字通り妻が自宅に住み続けることのできる権利であり、所有権とは異なって売買や譲渡はできません。居住権の評価額は住む期間によって決まり、居住期間は一定期間または亡くなるまでのいずれかの期間で、子との協議で決めます。
前述のケースで妻の居住権の評価額が1000万円だったとしますと、妻は法定相続分1500万円のうち1000万円分の居住権と残り500万円分の預貯金を相続することとなります。子は自宅の評価額2000万円から居住権を引いた1000万円分の所有権と、預貯金500万円を相続することとなります。妻が住んでいるあいだの必要経費は妻が負担しますが、固定資産等の税制についてはまだ決まっていません。
次の遺産分割に関する見直し等についてですが、現行法では妻が自宅等を生前贈与されていたとしても、自宅も遺産分割の対象となってしまいます。ですので前述のケース同様となります。
要綱では結婚から20年以上の夫婦に限り、自宅が遺産分割の対象から除外されることになります。前述のケースでは遺産分割の対象となるのは預貯金1000万円のみとなり、妻と子にそれぞれ2分の1づつが相続されます。これも長年連れ添った妻への配慮であり、高齢で再婚した場合等と区別するものです。期間は延期間であって離婚を挟んでも問題はありませんが、事実婚や同性婚は対象となりません。
3つめは遺言制度に関する見直しです。昨今は自筆証書遺言への関心も高まってきているようですが、現行民法ではすべての文言が自署である必要があります。改正案では自筆証書遺言に関しすべてが自署である必要はなく、財産目録等はパソコン作成のものを添付することでも可能となります。ただし各ページへの署名押印は必要となります。
また自筆証書遺言の保管制度が新たに創設され、遺言者は自筆証書遺言を各地の法務局に保管するよう申請することができ、死亡後は相続人等が保管先法務局に対して遺言書の閲覧請求等をすることができます。その際法務局は、他の相続人等に対しては通知をだすこととなります。
法務局が保管していた自筆証書遺言は検認を要しません。ただ公正証書遺言と異なり、法務局保管の自筆証書遺言が必ずしも最終最新のものではないおそれは残りますので、探索や確認は必要となります。
4つめは遺留分制度に関する見直しです。遺留分減殺請求権の効力については、受遺者等に対して遺留分侵害額に相当する金銭の支払いを請求することができるようになり、権利行使により遺留分侵害額に相当する金銭債権が発生するという考え方が採用されます。
また遺留分減殺請求の対象となる遺贈・贈与が複数存在する場合については現行法の規定に加えて、減殺の割合についてはこれまで解釈によっていたものが、今回案では明文化されています。遺留分の算定方法については現行法の相続開始の1年前にした贈与に加え、相続人贈与は相続開始前の10年間にされたものが算入対象となります。
5つめは相続の効力等(権利及び義務の承継等)に関する見直しについてです。これは遺言などで法定相続分を超えて相続した不動産等は、登記をしなければ第三者に権利を主張できないというものです。
最後に相続人以外の者の貢献を考慮するための方策についてです。現行法では寄与分については相続人にのみ認められていましたが、改正案では相続人以外の被相続人の親族が被相続人の介護をしていた場合、一定の要件を満たせば相続人に金銭請求できる こととなります。
被相続人の親族とは、6親等以内の血族および3親等以内の血族の配偶者が対象となります。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/
READ MORE
本日は私のホームページ上に載せている遺言書についてのQ&Aについて書いてみます。といってもQ&Aページのものではなく、遺言を書かれる動機固めのイントロダクションになります。では順番に。Q:遺言書などを書いたら、子供たちにあらぬ詮索をされるかもしれない。今現在円満に暮らしているし、相続の話しで家族の中に波風を立てたくない。A:今現在ご円満だからこそ、円満なまま仲良く暮らしていって欲しいのではないですか。遺言書のことは皆さんに表立ってお伝えする必要はありません。行政書士と相談しながら、最善の方法で作成していきましょう。Q:自分の家族に対する愛情は平等だ。でも今の子供たちの暮らしぶりを考えて、財産の分け方を決めても良いのではないか。いやいや私が決めるよりも子供たちが決めれば良いことではないか。A:相続人当事者同士で、遺産分割が円満に成立する場合ばかりではないようです。お子様にもご家族や関係者が大勢いらっしゃり、お子様ご自身の意思だけで決められるとは限りません。そうなった時には行事役のあなたはその場にはいらっしゃいません。今現在の状況を客観的に判断されて、みなさんを円満にまとめられるのは、あなたを置いて他にはいらっしゃいません。Q:遺言書を書こうとは考えているが、どこから手をつけて良いかわからない。具体的に想いを形にしたいが。A:遺言書は「だれに、何を、どのように」になります。まず遺言書を残されようと思い立った動機をご自身が再確認し、その目的を達成する方法を考えれば良いと思います。Q:健康に不安はないし遺言や相続のことなどまだ当分先のことだから、今考える必要はないかもしれない。A:みなさんそうおっしゃいます。遺言書は別に今書く必要はないものです。ただ、いざという時には遺言を残せないかもしれません。法的効果のある遺言には要件があります。そうならないためにも、もし相続に多少なりともご不安があるのであれば、「思い立ったが吉日」ではありませんか。Q:誰に相談したらよいかわからないし、自分の思いを口に出すのは恥ずかしい。A:遺言書には皆さん、今まで言えなかったご家族への感謝の言葉を残されます。普段は気恥ずかしくて、面と向かってはなかなか言えないものです。でもこれは最後のメッセージになります。形にした時点でご自身の心のつかえもとれるでしょうし、そこから新たなものも見つかるかも知れません。ご遠慮なくお話しいただき、その想いを形にしていきましょう。Q:誰かに依頼すると費用が発生すると思い、ふんぎりがつかない。A:行政書士の報酬や、公証役場の手数料は決して安価なものではありません。むしろ普段の生活の中では高額なものになります。しかし見返りに得られる価値は、決してお金に変えられるものではありません。ご負担になるようでしたらそれはご自分で書かれるのも良し、あくまで判断されるのはお客様ご自身になります。Q:自分で書こうと思ったが、書き方がわからない。自分で書いた場合のデメリットはあるのだろうか。A:このホームページに自筆遺言の書き方も載せてありますのでご一読ください。自筆遺言の最大のメリットは、もちろん費用がかからないことです。簡単に書く事も、書き直しもできます。今回の民法改正によって、自筆遺言のハードルも多少下がりました。デメリットは自筆遺言書自体がトラブルの原因になることです。簡単に書く事ができるために内容の裏付けがなかったり、保管が不十分であったり。ご予算等に合わせれば良いことですが、行政書士へのご依頼のほとんどが公正証書遺言であることもまた事実ですQ:遺言書を書いても保管方法がわからないし、もし相続が終わったあとに出てきたらトラブルのもとになってしまうかも知れない。A:上のご質問同様、自筆遺言の記載を確認ください。民法改正によって自筆遺言の保管や検認手続きなどについては使い勝手が良くなりましたが、多くのトラブルの原因が解消されるわけではありません。Q:遺言書を書いたあとに気が変わるかも知れない。気安く書かない方が良いのではないか。A:もちろん遺言書は気安く書かれるべきものではありません。慎重にご家族の将来を見据えて書かれるものですが、状況が変わることもありえます。そのような場合でも、遺言書は撤回することもできますし、それを破棄して新たなものを作成することもできます。遺言書は常に日付の新しいものが有効となります。Q:遺言書を書いてしまうと、自分の財産を自由に使えなくなるのではないか。A:ご自身の財産は、当然ご自身で自由に処分することができます。遺言書に縛られることはありませんし、日々の生活を見据えて書かれることだと思います。万が一状況が変わって大きな財産を処分することになっても、その際に考えれば良いことになります。ご心配はごもっともです。でもそのご心配を解きほぐし、一歩前にすすんでみませんか。
READ MORE

遺言書がない相続が発生した場合、相続関係を確定させるために関係するすべての戸籍謄本を取得しなければなりません。
被相続人に存命の配偶者とお子さんがいらっしゃれば、1/2の遺産は配偶者の方に権利がありますが、残りの1/2はお子さんで等分します。お子さんといっても現在の配偶者の方のお子様だけではなく、離婚歴がある場合はその方との間にできたお子さん、また非嫡出子でも認知しているお子さんがあればその方、また離縁されていない養子の方も同権利になります。
相続が発生した時点ですでに亡くなられているお子さんがいらっしゃれば、そのまたお子さん(孫)が代襲相続しますので、その方々の戸籍や住民票が必要になります。戸籍を取得する際に併せて「戸籍の附票」というものも取得し、その方が引っ越された履歴を追い、現在ご存命で相続の権利があることを証明していきます。
さて、相続人が被相続人のご兄弟のみの場合は、難易度が一段上がっていきます。前述の場合同様、ご兄弟に知れていない兄弟が存命か確認していく作業が必要になります。これは被相続人のご両親の出生時に遡った(銀行等によっては出産一定年齢等の場合があります)戸籍謄本を取得し、知れていないご兄弟が存命か確認しなければなりません。
その方を含めたご兄弟が亡くなられていた場合は、同様に代襲相続が発生します。ただしお子さんの相続の場合は、代襲者の死亡による再代襲制度がありますが、兄弟姉妹の場合は再代襲は認められていませんので、それ以下の方は調べる必要はありません。
戸籍取得は場合によっては数10枚に及び、またご兄弟の場合は戸籍を取得し追跡していく権限はありませんので、行政書士にご依頼をいただければと存じます。
READ MORE