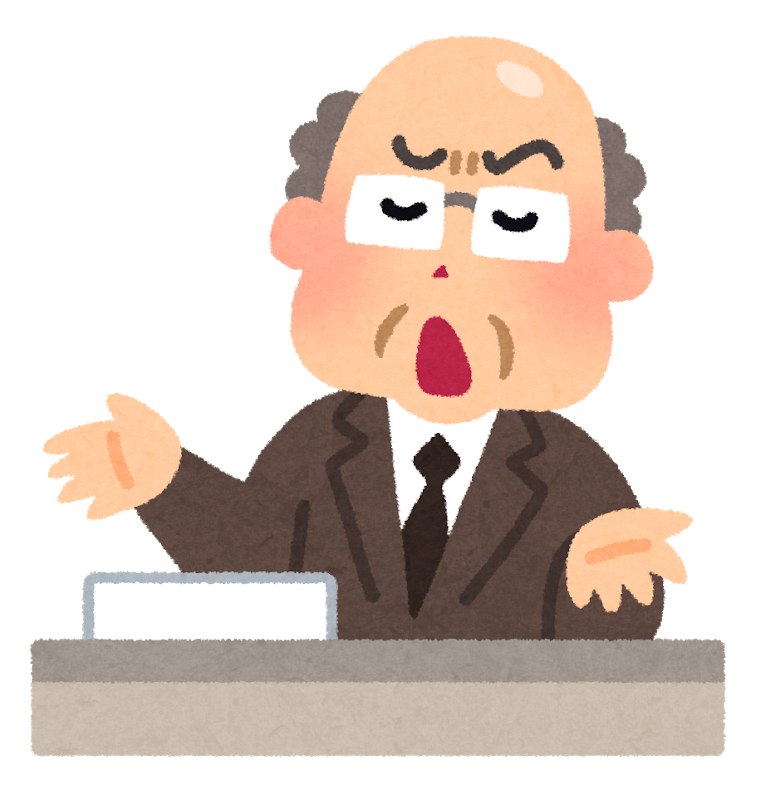今回は失踪宣告について書いてみます。
失踪は婚姻関係の整理や相続の分野にも関わってくる事柄です。失踪の宣告はその者の行方が不明になった場合に、利害関係人が家庭裁判所に申請することによって行ないます。家族の者でなくても構いません。
失踪宣告の請求はいつでもできますが、失踪宣告がなされた場合は、最後に生存が確認された時点から7年間の期間満了後に死亡したとみなされます。行方不明になってから8年後に請求をした場合は、1年前の期間満了時にさかのぼって死亡したとみなされます。これを普通失踪といいます。
一方飛行機や船の事故などで行方不明になった場合には、その危難が去ってから1年を経たあとに失踪宣告がなされますが、この場合は危難が去った時点にさかのぼって死亡したものとみなされます。これを特別失踪といいます。
しかし失踪宣告されたからといって失踪者本人の権利能力まで否定されるものではなく、本人が生きていた場合は他で法律行為を行うこともできます。その場合には失踪宣告の取り消しが行われますが、死亡時が異なる場合もその日付での宣告は取り消されることとなります。
では取り消しが行われた場合はどのようになるのでしょうか。失踪宣告の取り消しが行われた場合には、宣告によって財産を得た者はその権利を失うこととなり、現存利益の限度で返還義務を負うこととなります。民法では現存利益の限度(範囲)という言葉がよく出てきますが、手元に残ったお金があれば返還するということです。
手元に残ったお金が返還すべき額を下回っていたとしても、その使ったお金が家計費などの自分の利益になるものに使った場合は、その分は補填しなければいけないということです。一方ギャンブルなどで浪費してしまった場合は利益として残っていないのですから、その分は返還する必要はないですというものです。一見理不尽に思えますが、そういう内容です。
宣告によって財産を得た者が、第三者と既に取引を行っていた場合はどのようになるのでしょうか。この場合は、取引の当事者双方が善意であれば取引行為は有効となります。ちなみに善意という言葉が法律用語として使われる場合は、「その事実について知らない」ということを意味し、対義語である悪意は「その事実について知っている」ことを意味します。
夫の失踪宣告後に別の男性と結婚していた場合はどうなるのでしょうか。この場合は、妻と現在の夫の一方または双方が悪意(失踪した夫が生存していることを知っている)であれば、前婚が復活し重婚関係となります。重婚は認められませんので、現在の結婚を生かす場合には前婚の離婚届けを出し、前婚を生かす場合には現在の婚姻を取り消します。妻と現在の夫の双方が善意であれば、前婚は復活しません。
相続で行方不明の方が問題となる場面は、共同相続の場合です。共同相続に際しては、必ず相続人全員参加の遺産分割協議が必要になりますので、行方不明者がいる場合は失踪宣告を請求する必要も出てきます。この場合も協議との兼ね合いで時間的猶予のないこともありますので、実際はまず不在者財産管理人選任を請求することとなります。この請求は、行方不明者が最後にいたであろう場所を管轄する家庭裁判所に行ないます。
不在者財産管理人の立場としては、遺産分割で不在者に不利な配分を求めることもできませんので、実際は法定相続分での決着が多いようです。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category2/entry68.html
Related Posts

今日は婚姻の無効や解消について書いていきます。
まず婚姻の解消についてです。「婚姻の解消」理由には、
①離婚
②死亡・失踪宣告による解消
があります。
「離婚」については「協議上の離婚」と「裁判上の離婚」がありますが、まず協議上の離婚について見てみましょう。
「協議上の離婚」とは、夫婦お互いの協議によって成立する離婚になります。この場合には夫婦ともに離婚する意思があること(離婚意思の合致)と、離婚の届出を行うことが必要とされています。なお判例ではこの離婚意思の合致について、離婚そのものをする意思は必要とせず、届出をする意思のみで足りるとしています。
また離婚の際に未成年の子がいる場合は、必ず一方を「親権者」にしなければなりません。
離婚そのものをする意思であれ、届出をする意思のみであれ、それらを含む離婚意思のない者の離婚は当然に無効となります。「意思のない離婚」とは、詐欺または強迫によって協議離婚がなされる場合であり、この場合は取り消しを請求することができます。この取消権は、詐欺を見つけた時または強迫から免れた時点から3ヶ月で消滅します。また追認によっても消滅することになります。
協議上の離婚が成立しなかった場合は「裁判上の離婚」になります。離婚の場合は原則、訴訟を起こす前に家庭裁判所に調停の申し立てを行い、調停離婚が成立しない場合に裁判上の離婚に向かいます。
離婚の訴えを提起する場合には、次の理由が必要になります。
①配偶者の不貞行為
②悪意の遺棄
③3年以上の生死不明
④回復の見込みのない強度の精神病
⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由
です。
裁判所はそれらの事情を考慮して、離婚の訴えを認めるか棄却します。なお②の悪意の遺棄とは、理由もないのに同居を拒んだり家計費を差し入れないなど、積極的な意思で夫婦関係を行わないことを言います。
以上、協議上であれ裁判上であれ、離婚が成立した場合には次の効果がもたらされます。
①身分上の効果
②子の処遇
③財産上の効果
です。
「身分上の効果」により、婚姻関係とそれに伴う姻族関係が消滅します。また姓(氏)を改めた者については、「婚氏続称の届出」をしない場合は、結婚前の姓に戻ります。
「子の処遇」についてはまず、その子の嫡出子たる身分には影響は及ぼしません。また未成年の子の場合は親権者が決められます。
「財産上の効果」としては、一方が他方に財産分与を請求することができます。その額や方法は当事者の協議によりますが、協議が成立しない場合は離婚から2年以内であれば家庭裁判所にも処分を請求できます。
次は婚姻の無効と取り消しについて見てみましょう。無効と取り消しはその効果や影響が異なりますので、婚姻の瑕疵の程度に応じて規定がなされています。
まず、より影響の大きい無効について見てみましょう。
「無効」とされた場合は、婚姻が最初から無効であるとされ、夫婦としての効果は何ら生じません。婚姻の無効は、次の場合に限りなされます。
①婚姻意思を欠く場合
②届出を欠く場合
です。
無効は請求がなされて成立しますが、無効を請求することができる者は当事者だけでなく、利害関係者は誰でも主張することができます。これは当事者が死亡していても主張することができます。
次の「取り消し」ですが、これは無効よりも限定的な効果であり、取り消しの効果は婚姻成立時までは遡及しません。取り消しまでの期間は婚姻が有効とされ、その期間は財産分与などの財産関係も適用されます。
婚姻の取り消しを請求できる者は、当事者およびその親族、また検察官になります。
無効は当事者の死亡後も請求できますが、取り消しでは当事者の死亡後の請求は当事者や親族のみが行え、検察官は請求をすることはできません。また重婚違反の場合は当事者の配偶者および前配偶者も請求できます。これも失踪宣告の記事で確認ください。
再婚禁止期間の違反については親子関係の証明も関わりますので、前夫についても取り消しを請求することができます。詐欺・強迫の場合は当事者のみの請求となります。
READ MORE

今日は民法のうち「家族法」の分野に定められた、「婚姻」について書いていきます。ここも相続の際には非常に大きく関わってきます。
民法では現行法や改正法においても「法律婚主義」を採用しています。ですので相続される権利のある配偶者は、「婚姻関係にある者」のみになります。どんなに長く一緒に生活をし事実上は夫婦の関係にあるにしても、婚姻の届出をしない限りは婚姻は成立せず、法律上は夫婦と認められないことになります。
「婚姻」が成立した場合は、基本的には離婚をしない限りは配偶者としての権利は保障されます。
なお「婚姻」は私法上の契約であり本人の意思が最大限尊重されますので、成年被後見人であっても「単独で」することができます。
婚姻の成立要件としては次の3つがあります。
1.婚姻意思の合致(実質的要件)
2.婚姻障害に該当しないこと(実質的要件)
3.婚姻の届出(形式的要件)
です。
一つ目の要件である「婚姻の意思の合致」には、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思が必要である、とされています。つまり当事者お互いが自ら、夫婦の関係になることを望んでいることが要件になります。
本当に婚姻する意思があるわけではなく、相続などのためだけに形式的に婚姻届を出した場合はその届出は無効になります。
次の「婚姻障害」には、次のようなものが該当します。
①婚姻適齢
②重婚禁止
③再婚禁止期間
④近親婚の禁止
⑤直系姻族間の婚姻禁止
⑥養親子関係者間の婚姻禁止
⑦未成年者の婚姻
になります。
「婚姻適齢」とは、男性は18歳、女性は16歳にならないと婚姻できないというものです。これに違反した場合は婚姻が取り消されます。なお女性が男性と異なるのは合理性を欠くとして、女性も18歳に引き上げる方向で民法改正が進められています。
「重婚禁止」とは、配偶者のある者は重ねて婚姻することができないというものです。日本においては「一夫一婦制度」が維持されています。
なお重婚については、行方不明者であった配偶者が現れた場合の対応に問題が残ります。これについては先に「失踪宣告」で記事に載せましたので、ご確認ください。
https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/786
「再婚禁止期間」とは、女性が再婚するには、婚姻の解消又は取消しの日から起算して100日経過後でなければすることができないというものです。なおこの期間の例外として、女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合、または女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間の規定を適用されません。
以前はこの期間が6ヶ月経過後とされていましたが、平成28年6月1日施行の改正民法により見直しが図られました。なおこの規定は、父親の特定を法律上可能にするために設けられています。
次の「近親婚の禁止」では、優生学上の理由から、直系血族または3親等以内の傍系血族の間では婚姻することはできないというものになります。前回の親族の記事で確認しますと、3親等の血族である叔母とは結婚できませんが、その子であるいとことは結婚できることになります。菅元首相の奥さんもいとこでしたっけ。
「直系姻族間の婚姻禁止」については優生学上の理由はありませんが、同義上の理由から設けられています。これについては姻族関係が終了した後も禁止が解除されません。
「養親子関係者間の婚姻禁止」についても直系姻族間と同様の取り扱いになります。
以上挙げた規定については、違反した場合はすべて婚姻が取り消しとなります。
最後の「未成年者の婚姻」については、最初の項の婚姻適齢に述べましたが、婚姻適齢に達しても未成年者である限りは、婚姻するためには父母の同意が必要になります(父母の一方が反対等しても、一方の同意で足ります)。これについては18歳成人の改正民法が2022年4月1日より施行されますので、規定が変わることになります。
なお実際は父母の反対があったとしても、婚姻自体は有効になります。
READ MORE

今日は相続の承認について書いていきます。
相続は被相続人の死亡によって開始されますが、その時点で相続人が決まります。法定相続人は被相続人の配偶者や子、直系尊属および兄弟姉妹に限られますが、その中の配偶者と最優先順位の者が相続を受けることになります。
https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/412
相続人が決まれば次は相続する財産を確定させます。あらかじめ公正証書遺言などで財産目録を作成してあれば良いのですが、ない場合は不動産登記簿や金融機関への調査を行うことになります。どちらにしても不動産は名義を変えなければいけないですし故人の口座も閉鎖しなくてはなりませんので、相続人が複数いる場合は必要な書類を整えなくてはなりません。相続人関係図や遺産分割協議書と同様に、財産目録も作成しておきましょう。
不動産や現金預金を調べて、プラスの財産がマイナスの財産より多ければ普通は相続することになりますし、明らかに借金の方が多ければ相続についても考えなくてはならなくなります。そういう場合を想定して民法では相続を受ける方法を規定し、選択の余地を残しています。
ただ選択するのには3ヶ月という期間が定められており、その期間内に決定をしなければいけません。その期間を「熟慮期間」といいます。ではその選択内容について見ていきましょう。
相続を受ける承諾することを、「承認」といいます。「承認」には「単純承認」と「限定承認」があり、これに「相続放棄」を加えて、相続の方法には3種類が規定されています。
「単純承認」とは文字通り単純に相続を受けることをいいます。マイナスの財産も含めた相続財産を、相続人全員がそのまま受け入れるものです。ですので万が一マイナスの財産の方が多かった場合でも、単純承認を選択した場合にはその負債等も無限に負わなければいけません。
自ら選択した場合はもちろん、自ら単純承認を選択しない場合でも、承認の意思表示をしないまま3ヶ月を経過してしまった場合や、相続財産の全部または一部を処分してしまった場合も単純承認をしたとみなされてしまいます。これらは法定単純承認と呼ばれます。大きな債務等のあることがわかっている場合には、くれぐれも熟慮期間を意識し、早めに財産目録を作成しましょう。
「限定承認」とは、マイナスの財産が多かった場合でも相続財産の限度内において債務を弁済すればよいというものです。債務が相続したプラスの財産を超えた場合には、支払いの義務はありません。ただ限定承認の場合は手続きが非常に面倒なものとなります。
まず財産目録を用意し、これを家庭裁判所に提出して申請することになります。申請する場合には共同相続人全員一緒にしなければなりません。ひとりでも反対をしたり単純承認をしてしまった場合にはすることができません。ですので、一人が財産を処分してしまった場合には、残りの共同相続人も申請することはできなくなってしまいます。なお共同相続人のうちの誰かが相続放棄をした場合には、残りの相続人全員で限定承認を申請することができます。
「相続放棄」とはマイナス財産が超過している等の理由で、相続を受けない選択をすることです。相続放棄をした場合は、最初から相続人ではなかったものとみなされます。ですので欠格や廃除の場合と異なり、代襲相続も認められません。
ただ相続放棄がなされた場合でも、その債務等が当然になくなるわけではありません。他の相続人に相続されていきます。プラスの財産は遺言等によっては法定相続分通りには配分されませんが、マイナスの財産は法定相続分通りに配分されます。ですので残った債務や連帯保証人の立場などは、他の相続人間で法定相続分通りに相続されることとなります。
相続放棄をしても単純に債務から逃れられるという性質のものではありませんので、放棄する際には事前に他の相続人と相談をし、のちのちの関係を壊さないようにしたほうが賢明だと思われます。
http://yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry46.html
READ MORE

今日は相続にも大きく関係してくる、親族というものについて書いていきます。
相続を受けることのできる者(相続人)は「相続人」である「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」になりますので、親族の範囲を見た上で、これらの者がどの位置にいるのかを見てみます。
また今回成立した相続関係の民法改正において、「相続人以外の親族の貢献を考慮する方策」が加えられましたので、今まで以上に「親族」という言葉が使われる機会が多くなると思います。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry69.html
「親族」とはどのようなものを言うのでしょうか。民法における「親族」とは、次の者を言います。
①6親等以内の血族
②配偶者
③3親等以内の姻族
です。
まず「血族」とは、血縁関係のある者相互間(誰から見てもお互いに)および、法的に血縁があると制度上みなされる(擬制)者相互間を言います。前者を「自然血族」、後者を「法定血族」と言います。
「自然血族関係」は出生によって生じ、死亡によって終了します。「法定血族関係」は養子縁組によって生じ、離縁や縁組みの取り消しによって終了します。
次の「配偶者」は、婚姻によって戸籍上の地位を得た者になりますが、配偶者は血族にも姻族にも属さず親等もありません。
「姻族」とは「配偶者側の血族あるいは血族の配偶者相互間」を言います。例えば配偶者の父や、本人の父の兄弟(叔父)の配偶者は姻族になります。「姻族関係」は配偶者を通じての関係になりますので、配偶者の一方の血族と他方の血族は姻族にはなりません。具体的に言うと、本人の父と配偶者の父は姻族関係には当たりません。
また姻族関係は婚姻によって生じ、離婚によって終了することになります。離婚した元配偶者の親とは知り合いではあっても、法的つながりはなくなるということです。これは離婚の場合であり、死別の場合は届出を行わない限りは姻族関係は当然には消滅しません。
では先に出てきた「親等」とはどのようなものでしょうか。
「親等」とは親族間の遠近度を比較する尺度であり、親族間の「世代」によって決まります。本人から見て「世代」がひとつ変われば1親等という数え方をします。
相続人に当てはめて見ますと、配偶者に親等はありません。子と直系尊属(父母)が1親等、孫や祖父母は2親等になります。兄弟姉妹は親を経由して下がりますので、これも2親等と数えます。本人の叔父や叔母は祖父母を経由しますので3親等、その子であるいとこは4親等になります。
親族については世代をまたがる垂直の広がりと、直系から枝分かれをした横への広がりがあります。
縦への広がりで見てみますと、本人から世代が上の者たちを「尊属」、世代が下の者たちを「卑属」と言います。ですので父は尊属、子は卑属になります。兄弟姉妹やいとこは世代が同じですので、尊属にも卑属にも当たりません。
横への広がりで見てみますと、本人から垂直に遡ることのできる父母や祖父母や曽祖父母、あるいは垂直に下がることのできる子や孫やひ孫などは「直系」になります。
縦横併せてマトリックスで見ますと、上の世代を「直系尊属」、下の世代を「直系卑属」と言います。垂直から枝分かれをした叔父叔母などは「傍系」と言います。これも上の世代を「傍系尊属」、下の世代を「傍系卑属」と言います。
整理してみますと、血族には直系血族と傍系血族があり、直系血族には直系尊属と直系卑属があります。また傍系血族にも傍系存続と傍系卑属があることになります。姻族にも同様の、直系傍系、尊属卑属の関係があります。
改正民法の特別寄与に関しては、具体的に権利の範囲にあるかは事案ごとに確認を要するとことになります。
READ MORE

今日は遺言について書いていきます。遺言については以前にも書きましたが、相続遺言に関する民法がこの7月に約40年ぶりに大幅改正されましたので、それも含めて見てみましょう。
遺言を残そうとされる目的の多くは、ご自分の作られた財産をきちんとご自分の手で、ご自分の意思で配分したいというところにあると思います。考えられるきっかけはちょっとしたことからかもしれませんが、その動機の多くは遺されるご家族のことを考え、円満でスムーズに相続を終えてもらいたいという気持ちから発せられるようです。
中には家族親族がいがみあっていたり、複雑な関係性であったり、また相続人がいないなどの理由からトラブル防止のための遺言を書かれる場合もあると思います。また事業承継にあっては、自ら思い描く将来のために、きちんと整理した形で財産を相続させる場合もあろうかと思います。
いずれにせよ遺言を残される以上、法的に効果のある遺言にしなければなりません。では法的に効果のある遺言とはどのようなものでしょうか。
遺言自体はどのような形でも残すことができます。口頭で伝える場合もあれば、録音やビデオで伝える場合もあります。また通常は皆さん考えられるところの書面で残すことが多くなります。しかし法的に効果のある遺言は、きちんと法律に従った形式で、書面として残さなくてはいけないものになります。
きちんとビデオに撮っていても、それがそれぞれの相続人が納得するものであれば問題ありませんが、争いになった場合は法的に根拠がないものとして認められないものになります。
昨日たまたまビデオで「激動の1750日」という映画を見ていて、三代目姐が「先代が言い残した」という一言で後継が決まってしまいました。実際に言い残してはいないので争いになった場合は法的根拠のないものとなりますが、特殊な世界であれ、「故人が言っていた」の一言で相続が決まってしまってはたまりません。そこかしこでトラブルが頻発するでしょう。そんなトラブルを起こさないためにも、法律が遺言の形式を定めています。
ここでの法律は「民法」になります。民法は、私人間の生活関係を規律する「私法」の一般法(国家等の公権力と私人の関係を規律する法である法律を「公法」といい、これには憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法があります)であり、その内容は「財産法」(ここには物件法と債権法があります)と「家族法」に分かれます。
「家族法」には家族や親族の範囲や関係性について規定する「親族法」の部分と、相続や遺言について規定している「相続法」の部分があり、ここで遺言についても明確に規定してます。
では民法に規定する遺言について見ていきましょう。遺言の方式について、民法では「普通方式」と「特別方式」を定めています。我々が一般的に理解している遺言とは普通方式のものになりますが、簡単に特別方式の遺言について見てみます。
「特別方式」の遺言については滅多にお目にはかかれませんし、またそういう立場になっては困るのですが、緊急時に発する遺言になります。ここでは詳細は省きますが、災難がまさに降りかかっている際に発する「危急時遺言」と、世間から隔絶された場所にあるときに発する「隔絶地遺言」があります。
「危急時遺言」には「死亡危急者遺言」と「船舶避難者遺言」がありますが、前者は病気やけが、あるいは災害が差し迫っている際に発っするものであり、後者は船舶が遭難にあっている際に発するものになります。
また「隔絶地遺言」には、「伝染病隔離者遺言」と「在船者遺言」があります。前者は伝染病隔離施設や刑務所服役中などの場合、後者は遭難していない船舶の中で作成されます。
いずれも危難は迫ってはいませんので、本人が書く事になります。以上4種類が特別方式になりますが、それぞれ証人であったり検認であったり、その手続きは詳細に決められています。民法は約120年前に制定されましたので、情報の発達していない時代を背景としています。
READ MORE

今日は遺贈と死因贈与についてもう少し詳しく書いてきます。
まず「遺贈」についてですが、遺贈される者を「受遺者」といいます。相続と同様、遺贈も被相続人の死亡によって開始されます。
受遺者になる要件はひとつ、遺言によって遺贈をする旨の内容が残されていることですが、被相続人の死亡時に遺贈をされる者が既に死亡していた場合は、受遺者となることはできません。また受遺者については代襲の定めはありませんので、この場合はその子等に権利が移ることもありません。遺贈はなかったことになります。
一方、被相続人の死亡時には遺贈をされる者がまだ生存しており、その後すぐに死亡した場合については、遺贈の効果は有効となります。ですのでその財産は受遺者の子等に相続されることとなります。
遺贈には2つのものがあります。ひとつは「包括遺贈」とよばれるもので、財産の全部または一定の割合を指定してする遺贈です。この場合は具体的な財産は決められていないことになりますので、他の相続人がいる場合は、これらの者と一緒に遺産分割協議に参加しなくてはなりません。
また包括遺贈の特徴は、相続同様プラスの財産のみならずマイナスの財産も含むことです。マイナスの財産が多い場合もありますので、これも相続同様、受遺者に受ける受けないの選択権が設けられており、3ヶ月の期間内に放棄することも認められています。放棄する場合は、家庭裁判所に申請をする必要があります。
もうひとつは「特定遺贈」とよばれ、特定の財産を指定してなされる遺贈です。特にマイナスの財産を指定して行われない限りは、プラスの財産のみの遺贈となります。特定遺贈では遺産分割協議への参加もする必要はなく、また遺贈の承認や放棄の意思表示の期間も特に定められてはいません。しかし他の相続人が協議をすすめる必要性もあるため、これらの者から早期に意思表示を求められる場合が多くなります。
遺贈の場合の税金については、贈与税ではなく相続税として申告する必要があります。また相続人ほどの権利は認められていませんので、不動産の場合は登記をしなければ第三者に対抗できず、農地であった場合は農地転用が必要となります。
遺贈には「負担付き遺贈」と呼ばれるものがあります。これは、与えた条件(負担)を履行した場合のみ遺贈が行われるという性質のものです。たとえば、被相続人の配偶者の面倒を見ることを条件に遺贈を行う、といった場合がこれに当たります。
では負担が履行されなかった場合はどうなるのでしょうか。
負担を履行しなかった場合には、多くは遺言執行者や相続人から、遺贈の取り消しを請求されることとなります。この場合の遺贈する予定だった財産は負担付き遺贈者には渡されず、他の相続人に渡ることとなります。相続人が複数いる場合は、この部分について再度分割協議が行われます。
では負担の大部分は履行したが、全部の履行は行われなかった場合はどうでしょうか。判例では遺贈が認められた場合があります。当然負担を行った程度だけではなく、様々な状況も異なると思いますので、個別具体的に判断する必要があるということでしょう。
「死因贈与」とはどのようなものでしょうか。財産を与える者を「贈与者」、受ける者を「受贈者」とよびますが、これはお互いの契約になりますので、受贈者が一方的に放棄することはできません。死因贈与の際に納める税金も遺贈同様、贈与税ではなく相続税になります。
なお死因贈与の場合も条件付きの贈与があり、これを「負担付き死因贈与」とよびます。負担付き贈与の場合は、受贈者が亡くなる前であれば一方的に破棄することができますが、負担が履行され始めた場合には撤回することはできません。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category2/entry65.html
READ MORE
今日は遺産分割協議について書いていきます。5月の記事で記載しなかった部分の補足になります。
「遺産分割協議」は相続人全員の合意によって成立します。ですのでその前提として相続人全員が参加する、あるいは欠席する者の同意を、文書をもって確認(実印、印鑑証明)することが必要になります。
行方不明者がいた場合などは、リンクの前回記事を確認ください。遺産分割が成立した場合は、各自に配分される財産は相続開始時にさかのぼって効力を生じます。
https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/520
遺産分割会議が相続人全員の合意で成立すると、協議成立前までは共有財産とされていた財産が、相続時にさかのぼって、成立した配分の相続分を各相続人が単独で有していたこととされます。もともとそのそれらの財産は共有ではなく、各相続人がそれぞれ単独で相続したことになります。
しかしこの場合でも、遺産分割前に「登記を有した第三者」が既に介在していた場合には、その第三者の権利を害することはできませんので、注意が必要になります。また遺産分割によって法定相続分を超えた権利を取得した相続人は、登記をしなければ遺産分割後に権利を取得した第三者に対抗することはできません。
次に「相続分の譲渡」について見ていきましょう。前述した通り、協議成立後はそれぞれの分割財産は単独財産となりますが、分割前は共有財産ですので単独で処分することはできません。しかし法定相続分を他の者に譲渡することができます。これもホームページで確認ください。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry52.html
ここで他の相続人は相続分を譲り受けた者に対し、相続分の価格をもって取り戻す権利を有します。これは「取戻権」と言いますが、一方的な意思表示のみで行うことができます。この権利は譲渡の通知があったあと、1ヶ月以内に行わなければなりません。
READ MORE
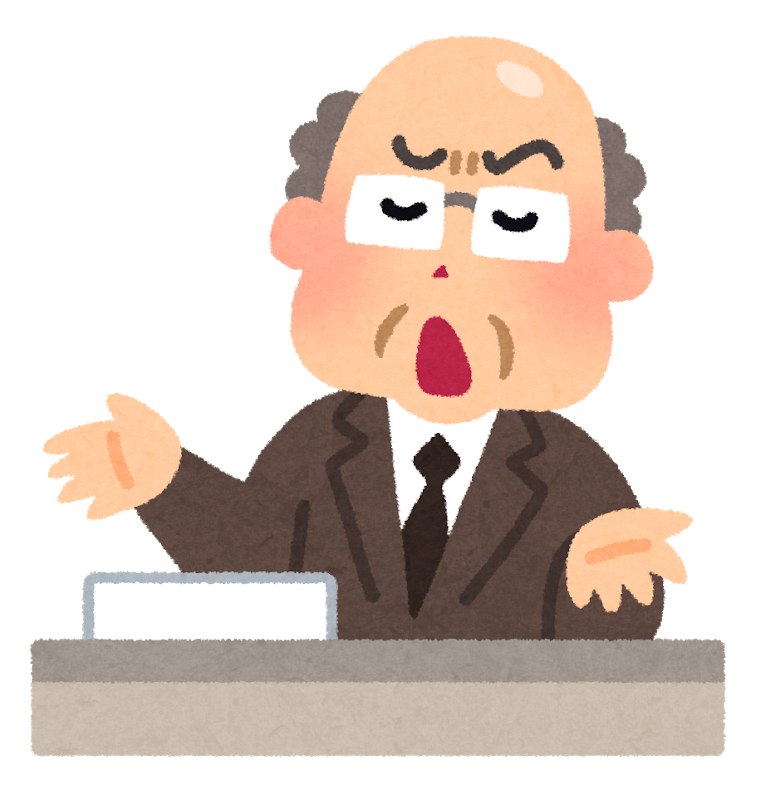
前回は遺産分割協議について触れましたが、相続人が少人数で関係も良好な場合は大きな問題になることはそれほど多くはありません。各自がそれぞれの立場も理解できており、またその後に直系の相続も発生することも想定できるからです。
しかし相続人同士が仲が良くなかったり、金銭関係が良好でない方が居る場合は途端に状況が変わってきます。また相続人が多かったり、相続人が兄弟のみで代襲相続が発生している場合などは特に問題がある場合が多くなります。よく「相続」は「争族」だとも言われますが、くれぐれも「争族」にならないように気をつけなければなりません。
多くの方は「うちに限って心配はない」と言われますが、そんな場面ばかりではないようです。親子関係、兄弟姉妹の関係は悪くはなくても、その方々の身内や関係者による口出しがある場合があります。またちょっとした言葉がきっかけで、一気にかたくなになってしまわれる方もいらっしゃいます。
相続というものは場面も場面でありますし、金額の多い少ないにかかわらず無条件でお金がもらえる機会になります。人情として気にならないはずはありません。通常は相続人が複数いらっしゃる場合は、相続分の一番多い方(配偶者など)や、一番しっかりされている方が代表相続人になられます。この方がしっかり方向性を決め、意見をまとめていきませんととんでもないことになります。協議がまとまらず、事案が法定にもちこまれることになりかねません。
遺産分割協議は、相続人全員の合意がないとまとまりません。たとえ相続分の少ない方であっても、その方が合意しない限りは協議は成立しません。ですので代表相続人の方は仲の良い方だけをまとめるのではなく、対応しにくいとんでもない共同相続人にも事前にしっかり皆さんの意向を説明し、協議前に大方の合意にこぎ着けていく必要があります。
そのためにも事前にしっかりとした遺産分割協議書案を作成し、当日は全員の実印をもらえるような段取りで協議に臨みましょう。トラブルメーカーはどこにでもいます。そういう方も直視して、期限内に円満な相続を終えましょう。
READ MORE

今日は特別養子縁組について書いていきます。
「特別養子縁組」とは「普通養子縁組」の場合とは異なり、養子とする子に特別な事情が存在する場合の縁組になります。
その子が一定年齢に達しておらず、かつ実親による保護が事実上困難な場合に、家庭裁判所の審判により行われる縁組になります。では具体的に特別養子縁組の成立要件や効果について見ていきましょう。要件は次の3つになります。
①養子の要件
②養親の要件
③父母の同意
です。
①について、特別養子となる子は原則、縁組の申し立て時に6才未満であることが必要です。ただし例外として、養親となる者に6才前から看護養育を受けていた子は、8才未満まで認められます。
②について、養親になるには配偶者がある必要があります。また夫婦の一方が他方の嫡出子(連れ子)の養親となる場合を除き、原則夫婦共同で養親となります。また養親となる者は原則として25才以上でなければなりません。この場合も夫婦の一方が25才以上であれば、他方は20才に達していれば認められます。
③については、原則特別養子となる子の父母が同意していることが必要となります。この場合も後述の一定の理由がある場合は同意も不要になります。
縁組の方式は、養親となる者の申し立てに基づいて行われ、家庭裁判所の審判によって成立します。この際の審判の基準は次の2つになります。
①父母の子に対する監護が著しく困難であり、あるいは不適当であること
②その他特別の事情がある場合において、子の利益のために特に必要があると認めるとき
です。
これらの場合に、養親となる者が養子となる者を6ヶ月以上試験養育した内容で認められることとなります。
特別養子縁組の効果は次のとおりになります。
①普通養子縁組同様、縁組の日から養親の嫡出子たる身分を取得し、その血族とも法定親族関係を有することとなります。
②実の父母およびその血族との親族関係は終了します。これによって普通養子縁組とは異なり、実の父母方の相続権は消滅します。
③特別養子縁組の離縁については、原則認められません。ただし例外として、養子の利益のために特に必要であると認められる場合は、家庭裁判所の審判による方法を取ることができます。
READ MORE

今日は民法に規定される契約というものについて書いていきます。
まず契約とはどのようなものを言うのでしょうか。契約とは、一定の債権関係の発生を目的として、互いに対立する複数の意思表示が合致することによって成立する法律行為のことを言います。
Aさんがある物を"買いたい"という意思表示をし、Bさんがこれに対して"売ります"という意思表示をすれば、対立する意思表示が合致したことによって契約が成立することになります。先にしたAさんの意思表示を「申込」と言い、Bさんの意思表示を「承諾」と言います。仮に立場が逆で、Aさんが先に"売りたい"という意思表示をした場合でもこれは「申込」となり、Bさんがそれに応じて"買います"という意思表示をしたならば、これは「承諾」をしたことになり契約が成立します。
先にする意思表示を「申込」、「後」にする意思表示を「承諾」と言います。ここでいう「申込」とは、一定の契約を締結しようとする意思表示のことです。気をつけなければいけないのは、この申込は単に申込をした場合と、承諾期間を定めて申込をした場合では扱いが異なってくることです。
承諾期間を定めて(返答の期限を切って)申込をした場合には、その定めた期間中はその申込の撤回をすることはできません。一方、期間を定めないでした申込であっても、相手が即答できない離れた場所にいる場合(隔地者といいます)には、"承諾を受けるのに相当な期間"を経過するまでは撤回することができないと規定されています。
相当ってこれまた曖昧な表現ですが、"かなり長い"というような意味ではなく、それをするのに通常要する期間とでも言いましょうか。また「承諾」とは申込を受けて、これに同意することによって契約を成立させるという意思表示になります。ではもう少し「承諾」というものについて見ていきましょう。
「承諾」をすると契約が成立するといいましたが、相手が目の前にいる場合は返事をしたときが契約の効力が発生する時点ですが、先ほどの隔地者間の場合ですと事情が変わってきます。電話で話をしている最中ならば寸分置かずに返答が帰ってきますが、例えば連絡がつかなかった場合はいつ返事が来るかわかりません。承諾期間をまたいだ場合などはトラブルのもとになりますので、法律で明確に効力の発生する時点を決めてあります。
隔地者間の意思表示は、原則論から言えば、その通知が相手方に到達した時に契約が成立するはずです。これを「到達主義」と言います。しかし取引においては、通知が到達していなくても契約の成立を認めることが迅速な取引に通じ取引界の要望にも合致するということで、民法では例外的に、隔地者間の契約については承諾の通知を発した時に成立すると規定されています。これを「発信主義」と言います。
なんだか余計に面倒な話になってきました。メールなどで発信すればすぐに到達しますよね。この話は最後にまたします。
ここでひとつ問題になるのは、申込に変更を加えた承諾をした場合です。例えばAさんがリンゴを3つ200円で買ってくださいと申込をしたとします。それにBさんが、1つおまけしてもらって4つ200円で買いますという承諾をしたとします。この場合は最初の申込と承諾と内容が変わってしまっているので、先の申し込みをBさんが拒絶をし、それとともに新たな申込をしたとみなされることになります。
本来承諾をすべきBさんが今度は新たに申込者となり、Aさんが承諾者になるというように立場が入れ替わります。到達主義と発信主義の違いは以上です。
次に承諾期間を定めてした申込に対して、その期間内に申込者に承諾の通知が届かなかった場合についてです。この場合の申込は抗力を失うとされ、契約は成立しないこととなります。しかし契約の場合は先ほどの「発信主義」となりますので、たとえ到達していなくても、その期間中に承諾の通知を発信をしていれば契約は成立することとなります。クイズなどでよく使われる、当日消印有効と同じようなものです。
この期間後に到達した承諾について民法では、申込者が新たな申し込みをおこなったとみなされます。なお民法では、遅れて承諾が届いた場合には、申込者は遅滞なくその旨を承諾者に対して通知しなければならないとされています。もしその旨の通知をしなかった場合には、遅れて届かなかったものとみなされ、契約は通常に成立することになります。
承諾期間を定めないでした申込の場合は特に効力消滅の規定はないため、相当な期間内に承諾の通知を発信すれば契約は成立します。この場合も発信主義をとります。
とここまで書いてきましたが、どんでん返し。実はこの民法は約120年前に制定されていますが、通信の発達した現代においては発信主義を取る合理性が失われたとし、2020年4月1日施行の改正民法においては、発信主義の条項は削除され、契約の成立時期は「発信主義」から「到達主義」に変わることとなります。
併せて、発信主義の条文に付随していた、遅れて届いた通知の条文も削除されることとなりました。以前から発信主義については議論があったようですので、やっとスッキリと見直されたということになります。
READ MORE