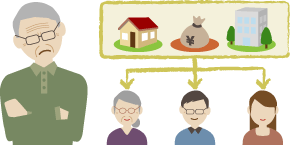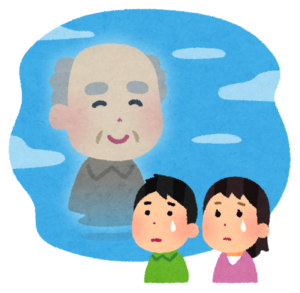今日は法定相続人の相続分について書きます。
相続分とは法定相続人の法定された取り分、請求できる権利のことです。順位は法定相続人の記事で書いた通りで、配偶者と最上位権者が相続します。では順にそれぞれの相続分を見てみましょう。
配偶者は必ず法定相続人となりますが、共同相続人が第何位の者かによって相続分が異なります。
まず法定相続人が第1順位である配偶者と子の場合は、配偶者が全相続分の2分の1を相続し、子が2分の1を相続します。子が複数いる場合は、その人数で2分の1を等分します。その子に代襲者がいる場合は、その子の相続分を代襲者が等分します。配偶者のみの場合は配偶者がすべてを相続し、子のみの場合は子がすべてを相続します。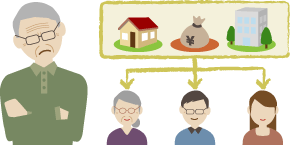
では共同相続人が第2順位である配偶者と直系尊属の場合はどうでしょうか。この場合は配偶者が全相続分の3分の2を相続し、直系尊属が3分の1を相続します。両親が相続人の場合は等分します。代襲者も子の場合と同様です。配偶者も子およびその代襲者もいない場合には、直系尊属がすべてを相続します。
第3順位である配偶者と兄弟姉妹の場合は、配偶者が全相続分の4分の3を相続し、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続します。代襲者も子の場合と同様ですが、兄弟姉妹には再代襲は認められません。配偶者も、被相続人の子や直系尊属およびそれらの代襲者もいない場合は、兄弟姉妹がすべてを相続します。
以上、民法では法定相続人および法定相続分が規定されています。しかし遺言書のない相続においては、法定相続人については特段問題がありませんが、法定相続分についてはすんなり決着の付く問題ではありません。
相続財産のうち現金預貯金が大半を占めれば良いのですが、不動産が多くを占める場合には単純には割り切れるものではありません。相続人同士の協議で決まれば問題ありませんが、協議が成立するには相続人全員の合意が必要になります。家族内でもめることも、意外に少なくないようです。
協議が成立しない場合には家庭裁判所に調停を申し立てることになります。そこでも調停が成立しない場合には、今度は家庭裁判所の審査を仰ぐことになってしまいます。
問題が法廷に持ち込まれる前に、第三者を立てて早期の遺産分割協議を行うことも一考かと存じます。遺産分割協議では事前に相続人や相続財産を調査した上で一覧にし、きちんと遺産分割協議案を作成しておかなければ、まとまる話もまとまりません。
相続分については遺留分制度というものもあります。遺留分とは一定の相続人に対して保証された、最低限の相続分の割合のことです。例えば被相続人の遺言書や生前贈与、遺贈等によって特定の相続人の相続分が不当に少なかった場合は、その相続人の生活を脅かすおそれも出てきます。そうならないように、取り分の最低限のラインを決めたものです。
言い換えると、いかに被相続人の意思であっても、一定の割合を侵してまで勝手に財産を処分することを許さない制度ということです。
遺留分を有する者は配偶者、子および直系尊属です。兄弟姉妹は遺留分を有しません。
遺留分算定の基礎となる財産は被相続人が相続開始時に有した財産に贈与した財産を加え、その中から債務の全額を控除して計算します。
遺留分権利者が配偶者や子を含む場合は法定相続分の2分の1が遺留分の割合となります。直系尊属の場合も、配偶者との共同相続である場合には遺留分は2分の1になります。具体的に数字に落とすと、配偶者または子のみの場合はそれぞれ総額1×2分の1=2分の1が保証され、配偶者と直系尊属の場合では配偶者は3分の2×2分の1=3分の1が保証され、直系尊属は3分の1×2分の1=6分の1が保証されます。
配偶者や子を含まない場合、言い換えると相続人が直系尊属のみの場合は遺留分は3分の1になります。ですので直系尊属のみの場合は、少なくても全相続額の3分の1は保証されるということになります。
遺留分を侵害された場合(相続分が遺留分に満たなかった場合)は、遺留分に満たない金額を、遺留分を侵害している者に請求することができます。これを「遺留分減殺請求権」といいます。
「遺留分減殺請求」は裁判所への請求を行わなくてもすることができ、相手方に対する意思表示をすることによって請求することができます(後々のトラブルを回避するためには、口頭ではなく内容証明を送付しておきましょう)。いったん減殺の意思表示がなされると、法律上当然にその所有権が相続権利者に復帰するので、その物が受遺者や遺贈者に引渡されていても、所有権に基づいて返還を請求することができます。
http://yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry52.html
Related Posts
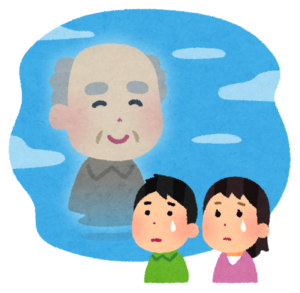
今日は遺言書のない相続について記載します。
■筆者の相続ホームページ
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/
相続は多かれ少なかれ突然発生します。亡くなられた方が長く病で伏せってらしても、そのような状態ではなかなか事前に相続のことまで気が回りません。その方ご自身が相続人の方の今後を考えられて遺言書を作成する場合もありますが、考えている内に遺言書自体を作成する認知能力などが失われてしまいます。
では突然やってきた相続の場合どうすれば良いでしょうか。当面は配偶者やお子さんなどの一番身近な方が死亡届や年金、税金関係など役所の手続きをすませたり、金融機関に連絡をされると思います。当面葬儀などの資金が必要になるでしょうから、必要額を事前に亡くなられた方の口座から引き出しておく必要もあります。
とりあえずの段取を終え落ち着かれたら、次は相続について考えなければなりません。一般的に被相続人(亡くなられた方)の財産には、現金や預貯金の他、不動産があります。その他有価証券等がある場合もあります。これらを相続人全員で協議し、それぞれの取り分を決めなくてはなりません。
まず配偶者の方やお子さんなどの一番身近な方が主導となり、相続人に当たりを付けます。そこから関連するすべての戸籍を取り、並行してすべての財産を探索してまとめ上げます。身近の方が亡くなられてそこまで気が回らないこともあるでしょうが、できる限り早く手を付けることが肝要です。お忙しければ当職のような行政書士などの代理人に依頼することもお勧めします。
なぜ急がなければならないかというと、相続には法律でいろいろな期限が決められているからです。例えば3ヶ月以内にしなければならないことは、財産を相続するか放棄するかの決断です。相続放棄は3ヶ月以内に手続きをしないと、以降は相続放棄ができなくなります。たとえ借金が残された財産より多くても、負債も含めて相続人に法定相続分だけ相続され、被相続人の借金を返済しなければならなくなります。多くの借金が想定される場合には、非常に重大な期限になります。
また逆に相続財産が多い場合も重要な期限があります。それは10ヶ月以内に相続税を納めなければならないことです。期限内でしたら住宅などの特例措置もあります。相続財産が多い方は、出来れば早めに行政書士などの専門家に依頼し、速やかに相続手続きに着手されることをお勧めします。
READ MORE

今日は公正証書遺言について書いていきます。
まず「公正証書遺言」ます。の作成方法です。最終的には公正証書遺言は「公証役場」で作成することになりそこに向かっての手順ということになります。もちろん行政書士を介せずご自分おひとりで原案を作成することもできます。その場合でも最終的には公証人が関与しますので、法的効果が欠如することはありませんし、内容的な不備も排除されます。保管の問題もクリアされます。
しかし公証人自体は書かれている内容自体に関与するものではありませんので、例えば「財産のすべてを愛人に与える」などという作成できないもの(この場合は公序良俗に反する)以外は作成されます。
また公証人によっては遺留分を考慮しない遺言、例えば長男に財産の3分の2をあげて次男には3分の1、長女には相続しないという内容の遺言書でも作成されてしまう場合があります。ですのでここでも作成にあたっては、行政書士に相談されて作成されることをお勧めします。
今回の記事においては、行政書士に依頼された場合の段取りにしたがって作成方法を書いていきます。
まず相談者様から作成代行の依頼があった場合は、遺言者様から契約書をいただくくとともに、署名捺印の委任状をいただきます。印は実印で捺印していただきます。また併せて印鑑登録証明書もいただきます。
公正証書遺言を作成するためには、相続人を調査し、相続財産を調査します。相続人については大方の場合は配偶者と子供などの知れている相続人になりますが、より確実な遺言書とするために、遺言者の出生から現在までの戸籍謄本および、推定相続人の戸籍謄本を取得して「相続関係説明図」を作成します。
なお公証役場には遺言者と相続人の続柄がわかる戸籍謄本があれば問題ありませんので、「相続関係説明図」を作成しない場合は、最低限これがあれば足ります。戸籍謄本は行政書士が「職務上請求書」というものを使用して、役所より取得します。
次は「財産目録」を作成します。遺言者から不動産や預貯金、証券類などの財産を申告してもらい作成します。遺留分の計算等でこの時点の財産額を知る必要がありますので、不動産の財産額について確認します。
この時点で「不動産の全部事項証明書」と念のために公図等も取得しておきます。併せて価格は路線価等で再確認します。預貯金については直近の通帳をコピーし、証券類は証書等を確認します。動産類は自動車の車検証の写や貴金属等の鑑定書なども用意します。
この際に忘れてならないのは、負債についてもきちんと確認することです。プラスの財産は遺言書とおりに相続されますが、負債については法定相続分とおりに相続されます。仮にプラスの財産よりマイナスの財産の方が多かった場合は相続放棄になりかねませんので、注意が必要です。以上から「財産目録」を作成します。
これらをもとに遺言書の文案を決めていきます。まず相続人を決め、遺贈等を決めます。それから各相続人の相続分を決めていきます。相続財産の配分については当然遺言者の判断になりますが、遺留分等についても配慮した方がトラブルは回避することができます。
不動産については明確に記載しますが、預貯金については特定の額を記載せず3分の1づつでも良いですし、1000万円を長男に、残りを次男に等の表現でも構いません。財産目録に記載されない細々とした動産等もありますので、遺言者所有のその他すべての財産を長男○○に相続させるの条項も記載します。
あとは墓や仏壇を管理していく「祭祀主催者」や「遺言執行者」等を記載していきます。祭祀主催者の条項を加えた場合は、公証人より別途手数料が加算されますので注意してください。
最後に「付言」を記します。文案が作成できたら依頼者と確認を取り、加筆修正の後文案を合意します。それから行政書士が公証人と文案の打ち合わせを行い、必要書類を提出します。公証人から文案と費用が提出されるので、依頼者と最終確認を行ないます。
合意ができたら公証役場へ出向く日を決め、当日は行政書士と遺言者本人、もうひとりの証人とともに公正証書遺言を作成します。当日は次の段取りで公正証書遺言が作成されていきます。
①公証人が遺言者本人と証人2名(当職ともう1名の証人)の氏名・生年月日・住所・職業を質問し、遺言者と証人が本人確認ができる書類を提示します。
②公証人が遺言者に遺言の内容を確認します。
③公証人が遺言者と証人に、遺言書を配布し口述します。
④遺言者と証人が遺言書の内容を確認し、公正証書遺言に各自が署名捺印をします。この際は遺言者は実印を用意します。証人は認印でも構いません。
⑤公証人が署名捺印をします。
以上で公正証書遺言の完成です。
⑥遺言者が公証役場に手数料を現金で支払います。
⑦公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、遺言執行者に「正本」が、遺言者に「謄本」が渡されます。
「正本」「謄本」の保管には注意が必要ですが、銀行の貸金庫に預けてしまうと開けるには相続人全員の署名捺印が必要になりますので、注意が必要です。
公正証書遺言であってもいつでも撤回をすることができます。
最後に作成する際の言語ですが、自筆証書遺言や秘密証書遺言は作成する言語は外国語でも構いませんが、公正証書遺言は日本語で作成しなければなりません。
READ MORE

今日は相続の承認や放棄について、前回の補足として書いていきます。5月にこの記事について書きましたので簡単におさらいをしてみます。
相続は被相続人の死亡によって開始することになりますが、遺言のない相続の場合は相続人全員参加で遺産分割協議を開催し、その協議によってそれぞれの相続配分を決めることになります。これは「法定相続」と言って、その配分は民法によって定められています。
基本的には各自の相続分はこの規定に基づいて決めていくことになるのですが、相続される財産は預貯金や不動産といったプラスの財産に限られるわけではなく、借金などのマイナスの財産もあります。
これらが不明の場合には、きちんと負債を含むすべての財産を調べ、財産目録を作成していくわけですが、マイナスの財産の方が多かった場合は相続を受ける意味がありません。相続によってわざわざ借金を背負う必要がないからです。
そのために相続を受ける(承認と言います)か受けないか(相続放棄と言います)を選択する権利が、相続人には与えられているのです。これは3ヶ月の熟慮期間中に裁判所に申請をしなければいけません。
申請をしないまま期間が過ぎてしまいますと、「単純承認」と言ってプラスの財産もマイナスの財産もすべて相続する判断をしたとみなされます。たとえ借金の方が多くても撤回することはできませんので、財産の調査は重要になってきます。
この「熟慮期間」は、財産の状態等を調査する期間として設けられています。詳しくは前回の記事で確認してください。
https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/427
相続放棄も含めて、一度決めてしまうと撤回することはできません。ただし承認や放棄を行ったとしても、例外として無効や取り消しになる場合があります。錯誤や詐欺・強迫といった場合です。
承認や放棄に際して、錯誤や詐欺・強迫の事実があれば、また制限行為能力者が単独でした行為であれば、それらは家庭裁判所への申し立てによって無効または取り消すことができます。これらの権利は、追認出来る時から6ヶ月、または行為の時点から10年で消滅します。他の権利と比較しても短期間となっていますので、相続はいかに早期に行われるべきものかがわかります。
もうひとつ、「行方不明者」の問題があります。承認のうちの限定承認や遺産分割協議においても、共同相続人全員で行う必要がありますので、相続人の中に安否が未確認の行方不明者がいた場合は厄介なものになります。
この者がいなければ相続人全員とはなりませんし、仮に協議等を行ったとしても後から現れた場合には協議もやり直しをしなければなりません。ですので、きちんと手続きを整えて臨むことが必要になります。「行方不明者」がいた場合には、遺産分割協議を行う前に次の手続きを行ないます。
①家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任を申し立てます
②家庭裁判所に「行方不明者の失踪宣告」の申し立てを行ないます
ともに申し立てを行う家庭裁判所は、行方不明者の住所地を管轄する家庭裁判所になります。
①の「不在者財産管理人」についてですが、この者は基本的には行方不明者の財産を管理する(相続財産を法人化します)ことが役割となります。しかしそれでは協議が進みませんので、申請をすることによって遺産分割協議に加わります。
利害関係のない者が選任されますが、多くは弁護士等が就任します。遺産分割協議においては行方不明者の利益を確保することを前提に、法定相続分を上回る主張をすることになります。協議が整った場合は、行方不明者が現れる期限までその相続財産を管理することになります。
②の失踪宣告については、家庭裁判所が官報などに「不在者捜索の公告」を行い、行方不明から7年(災害などで行方不明の場合は1年)で、法律上死亡したものとみなされます。
失踪宣告には通常1年以上かかるため、遺産分割協議には間に合いません。ですので、通常の段取りとしては、失踪宣告をした上で、不在者財産管理人を含めた分割協議を進めていきます。
期限内に失踪者が現れた場合にはその者は相続人に復帰しますし、そうでない場合はその者の相続分は共同相続人の財産になります。
被相続人の財産調査や相続関係の調査は、行政書士にお任せください。
READ MORE

相続分野の改正民法が、本年7月1日に施行となります。
すでに施行された「自筆遺言書の方式緩和」、2020年4月1日施行の「配偶者の居住権を保護するための方策(短期、長期)」、2020年7月10日施行の「自筆証書遺言の保管制度」を除き、2019年7月1日より施行されます。
あと1月ほどとなりましたが、これには「遺留分制度」や「相続人以外の者の貢献」に関する改正が含まれますので、下記リンクより一度ご確認下さい。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry69.html
READ MORE

今回は失踪宣告について書いてみます。
失踪は婚姻関係の整理や相続の分野にも関わってくる事柄です。失踪の宣告はその者の行方が不明になった場合に、利害関係人が家庭裁判所に申請することによって行ないます。家族の者でなくても構いません。
失踪宣告の請求はいつでもできますが、失踪宣告がなされた場合は、最後に生存が確認された時点から7年間の期間満了後に死亡したとみなされます。行方不明になってから8年後に請求をした場合は、1年前の期間満了時にさかのぼって死亡したとみなされます。これを普通失踪といいます。
一方飛行機や船の事故などで行方不明になった場合には、その危難が去ってから1年を経たあとに失踪宣告がなされますが、この場合は危難が去った時点にさかのぼって死亡したものとみなされます。これを特別失踪といいます。
しかし失踪宣告されたからといって失踪者本人の権利能力まで否定されるものではなく、本人が生きていた場合は他で法律行為を行うこともできます。その場合には失踪宣告の取り消しが行われますが、死亡時が異なる場合もその日付での宣告は取り消されることとなります。
では取り消しが行われた場合はどのようになるのでしょうか。失踪宣告の取り消しが行われた場合には、宣告によって財産を得た者はその権利を失うこととなり、現存利益の限度で返還義務を負うこととなります。民法では現存利益の限度(範囲)という言葉がよく出てきますが、手元に残ったお金があれば返還するということです。
手元に残ったお金が返還すべき額を下回っていたとしても、その使ったお金が家計費などの自分の利益になるものに使った場合は、その分は補填しなければいけないということです。一方ギャンブルなどで浪費してしまった場合は利益として残っていないのですから、その分は返還する必要はないですというものです。一見理不尽に思えますが、そういう内容です。
宣告によって財産を得た者が、第三者と既に取引を行っていた場合はどのようになるのでしょうか。この場合は、取引の当事者双方が善意であれば取引行為は有効となります。ちなみに善意という言葉が法律用語として使われる場合は、「その事実について知らない」ということを意味し、対義語である悪意は「その事実について知っている」ことを意味します。
夫の失踪宣告後に別の男性と結婚していた場合はどうなるのでしょうか。この場合は、妻と現在の夫の一方または双方が悪意(失踪した夫が生存していることを知っている)であれば、前婚が復活し重婚関係となります。重婚は認められませんので、現在の結婚を生かす場合には前婚の離婚届けを出し、前婚を生かす場合には現在の婚姻を取り消します。妻と現在の夫の双方が善意であれば、前婚は復活しません。
相続で行方不明の方が問題となる場面は、共同相続の場合です。共同相続に際しては、必ず相続人全員参加の遺産分割協議が必要になりますので、行方不明者がいる場合は失踪宣告を請求する必要も出てきます。この場合も協議との兼ね合いで時間的猶予のないこともありますので、実際はまず不在者財産管理人選任を請求することとなります。この請求は、行方不明者が最後にいたであろう場所を管轄する家庭裁判所に行ないます。
不在者財産管理人の立場としては、遺産分割で不在者に不利な配分を求めることもできませんので、実際は法定相続分での決着が多いようです。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category2/entry68.html
READ MORE
本日は私のホームページ上に載せている遺言書についてのQ&Aについて書いてみます。といってもQ&Aページのものではなく、遺言を書かれる動機固めのイントロダクションになります。では順番に。Q:遺言書などを書いたら、子供たちにあらぬ詮索をされるかもしれない。今現在円満に暮らしているし、相続の話しで家族の中に波風を立てたくない。A:今現在ご円満だからこそ、円満なまま仲良く暮らしていって欲しいのではないですか。遺言書のことは皆さんに表立ってお伝えする必要はありません。行政書士と相談しながら、最善の方法で作成していきましょう。Q:自分の家族に対する愛情は平等だ。でも今の子供たちの暮らしぶりを考えて、財産の分け方を決めても良いのではないか。いやいや私が決めるよりも子供たちが決めれば良いことではないか。A:相続人当事者同士で、遺産分割が円満に成立する場合ばかりではないようです。お子様にもご家族や関係者が大勢いらっしゃり、お子様ご自身の意思だけで決められるとは限りません。そうなった時には行事役のあなたはその場にはいらっしゃいません。今現在の状況を客観的に判断されて、みなさんを円満にまとめられるのは、あなたを置いて他にはいらっしゃいません。Q:遺言書を書こうとは考えているが、どこから手をつけて良いかわからない。具体的に想いを形にしたいが。A:遺言書は「だれに、何を、どのように」になります。まず遺言書を残されようと思い立った動機をご自身が再確認し、その目的を達成する方法を考えれば良いと思います。Q:健康に不安はないし遺言や相続のことなどまだ当分先のことだから、今考える必要はないかもしれない。A:みなさんそうおっしゃいます。遺言書は別に今書く必要はないものです。ただ、いざという時には遺言を残せないかもしれません。法的効果のある遺言には要件があります。そうならないためにも、もし相続に多少なりともご不安があるのであれば、「思い立ったが吉日」ではありませんか。Q:誰に相談したらよいかわからないし、自分の思いを口に出すのは恥ずかしい。A:遺言書には皆さん、今まで言えなかったご家族への感謝の言葉を残されます。普段は気恥ずかしくて、面と向かってはなかなか言えないものです。でもこれは最後のメッセージになります。形にした時点でご自身の心のつかえもとれるでしょうし、そこから新たなものも見つかるかも知れません。ご遠慮なくお話しいただき、その想いを形にしていきましょう。Q:誰かに依頼すると費用が発生すると思い、ふんぎりがつかない。A:行政書士の報酬や、公証役場の手数料は決して安価なものではありません。むしろ普段の生活の中では高額なものになります。しかし見返りに得られる価値は、決してお金に変えられるものではありません。ご負担になるようでしたらそれはご自分で書かれるのも良し、あくまで判断されるのはお客様ご自身になります。Q:自分で書こうと思ったが、書き方がわからない。自分で書いた場合のデメリットはあるのだろうか。A:このホームページに自筆遺言の書き方も載せてありますのでご一読ください。自筆遺言の最大のメリットは、もちろん費用がかからないことです。簡単に書く事も、書き直しもできます。今回の民法改正によって、自筆遺言のハードルも多少下がりました。デメリットは自筆遺言書自体がトラブルの原因になることです。簡単に書く事ができるために内容の裏付けがなかったり、保管が不十分であったり。ご予算等に合わせれば良いことですが、行政書士へのご依頼のほとんどが公正証書遺言であることもまた事実ですQ:遺言書を書いても保管方法がわからないし、もし相続が終わったあとに出てきたらトラブルのもとになってしまうかも知れない。A:上のご質問同様、自筆遺言の記載を確認ください。民法改正によって自筆遺言の保管や検認手続きなどについては使い勝手が良くなりましたが、多くのトラブルの原因が解消されるわけではありません。Q:遺言書を書いたあとに気が変わるかも知れない。気安く書かない方が良いのではないか。A:もちろん遺言書は気安く書かれるべきものではありません。慎重にご家族の将来を見据えて書かれるものですが、状況が変わることもありえます。そのような場合でも、遺言書は撤回することもできますし、それを破棄して新たなものを作成することもできます。遺言書は常に日付の新しいものが有効となります。Q:遺言書を書いてしまうと、自分の財産を自由に使えなくなるのではないか。A:ご自身の財産は、当然ご自身で自由に処分することができます。遺言書に縛られることはありませんし、日々の生活を見据えて書かれることだと思います。万が一状況が変わって大きな財産を処分することになっても、その際に考えれば良いことになります。ご心配はごもっともです。でもそのご心配を解きほぐし、一歩前にすすんでみませんか。
READ MORE

今日は遺言について書いていきます。遺言については以前にも書きましたが、相続遺言に関する民法がこの7月に約40年ぶりに大幅改正されましたので、それも含めて見てみましょう。
遺言を残そうとされる目的の多くは、ご自分の作られた財産をきちんとご自分の手で、ご自分の意思で配分したいというところにあると思います。考えられるきっかけはちょっとしたことからかもしれませんが、その動機の多くは遺されるご家族のことを考え、円満でスムーズに相続を終えてもらいたいという気持ちから発せられるようです。
中には家族親族がいがみあっていたり、複雑な関係性であったり、また相続人がいないなどの理由からトラブル防止のための遺言を書かれる場合もあると思います。また事業承継にあっては、自ら思い描く将来のために、きちんと整理した形で財産を相続させる場合もあろうかと思います。
いずれにせよ遺言を残される以上、法的に効果のある遺言にしなければなりません。では法的に効果のある遺言とはどのようなものでしょうか。
遺言自体はどのような形でも残すことができます。口頭で伝える場合もあれば、録音やビデオで伝える場合もあります。また通常は皆さん考えられるところの書面で残すことが多くなります。しかし法的に効果のある遺言は、きちんと法律に従った形式で、書面として残さなくてはいけないものになります。
きちんとビデオに撮っていても、それがそれぞれの相続人が納得するものであれば問題ありませんが、争いになった場合は法的に根拠がないものとして認められないものになります。
昨日たまたまビデオで「激動の1750日」という映画を見ていて、三代目姐が「先代が言い残した」という一言で後継が決まってしまいました。実際に言い残してはいないので争いになった場合は法的根拠のないものとなりますが、特殊な世界であれ、「故人が言っていた」の一言で相続が決まってしまってはたまりません。そこかしこでトラブルが頻発するでしょう。そんなトラブルを起こさないためにも、法律が遺言の形式を定めています。
ここでの法律は「民法」になります。民法は、私人間の生活関係を規律する「私法」の一般法(国家等の公権力と私人の関係を規律する法である法律を「公法」といい、これには憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法があります)であり、その内容は「財産法」(ここには物件法と債権法があります)と「家族法」に分かれます。
「家族法」には家族や親族の範囲や関係性について規定する「親族法」の部分と、相続や遺言について規定している「相続法」の部分があり、ここで遺言についても明確に規定してます。
では民法に規定する遺言について見ていきましょう。遺言の方式について、民法では「普通方式」と「特別方式」を定めています。我々が一般的に理解している遺言とは普通方式のものになりますが、簡単に特別方式の遺言について見てみます。
「特別方式」の遺言については滅多にお目にはかかれませんし、またそういう立場になっては困るのですが、緊急時に発する遺言になります。ここでは詳細は省きますが、災難がまさに降りかかっている際に発する「危急時遺言」と、世間から隔絶された場所にあるときに発する「隔絶地遺言」があります。
「危急時遺言」には「死亡危急者遺言」と「船舶避難者遺言」がありますが、前者は病気やけが、あるいは災害が差し迫っている際に発っするものであり、後者は船舶が遭難にあっている際に発するものになります。
また「隔絶地遺言」には、「伝染病隔離者遺言」と「在船者遺言」があります。前者は伝染病隔離施設や刑務所服役中などの場合、後者は遭難していない船舶の中で作成されます。
いずれも危難は迫ってはいませんので、本人が書く事になります。以上4種類が特別方式になりますが、それぞれ証人であったり検認であったり、その手続きは詳細に決められています。民法は約120年前に制定されましたので、情報の発達していない時代を背景としています。
READ MORE

今日は物件の所有権について書いていきます。
相続にも通じる内容になりますが、所有権とは法令の範囲内で、自分の所有物を自由に使用したり処分したりする権利のことを言います。
所有権にはそれを得た経緯によって、承継取得と原始取得という2つの種類があります。
「承継取得」とは、先にその物権を所有する者がいて、その者から権利を引き継ぐことを言います。これには売買等によって権利を引き継ぐ「特定承継」と、相続等によって権利義務を一括して引き継ぐ「包括承継」があります。相続の分野では包括承継という言葉がよく出てきますね。
一方の「原始取得」とは、前の権利者の内容を前提としないで所有権を取得する場合をいい、これには無主物占有と遺失物拾得、埋蔵物発見、添付によるものがあります。
「無主物占有」とは、権利者のいない動産を占有することによって所有権を得ることであり、同様に遺失物拾得も埋蔵物発見も、所有者のいない動産の所有権を獲得することを言います。これらの場合に自分の物になる条件としては、必ず所有の意志をもって占有することが必要になります。
このように、所有者のいない動産の場合は別の者が権利者になることができますが、所有者のいない不動産の場合は原始取得をすることはできません。この場合は国庫に帰属することになります。
「添付」というものについて説明すると、添付には付合(ふごう)、混和、加工の3つの形態があります。
「付合」という言葉は聞きなれない言葉なので簡単に説明します。付合とは主体をなすある物に、従う形でついていることを言います。この付合には不動産の場合と動産の場合があります。
不動産の場合の付合ですと、その不動産に従として付合した物の所有権も取得するという性質のものであります。例えば家の前に植えてある桜の木などがこれに当たります。また付合は不動産だけでなく動産の場合も同様になります。
ただ動産の付合については若干ややこしい場合があります。動産の付合で主従関係がわかる場合は、付合している物の所有権は主たる動産の所有者の物になるのでこの点は良いのですが、主従の区別ができない場合がちょっと問題になります。この場合は、元の価格の割合で共有するということになっています。
「混和」とは物が混じり合っている状態を言いますが、この場合は付合と同様の処理になります。
「加工」とは他人の所有している動産に対して、加工を施して価値を上げた場合を言いますが、通常の場合には加工物はその動産の所有者に帰属することになります。ただしその動産(加工する材料)よりも加工による価値が著しく上回る場合には、その所有権は加工者のものになります。
READ MORE

今日は公正証書遺言を作成する際のメリット・デメリットについて書いていきます。
まずデメリットは
①遺言書作成に費用がかかる
②公証役場に出向いて作成し、2名以上の証人が必要
③遺言書の内容を秘密にできないこと
です。
①については、自筆証書遺言とは対照的に当然費用が発生します。行政書士が協力する場合にはその報酬と、公証人への手数料が必要になります。公証人の手数料は遺言に記載される、目的の財産の額によって異なります。
例えば3000万円までは23000円、5000万円までは29000円になります。これは相続人1名あたりの額であって、相続人が複数いる場合は、相続人それぞれの手数料を算出し、相続人全員分を足し込みます。
例えば相続人が子供2人であり、それぞれが2000万円相当の財産を相続したとします。その場合の基本手数料は、23000円+23000円=46000円ということになります。それに総額が1億円以下の場合は11000円が加算されます。
少なからぬ金額になりますが、もとより公正証書遺言書を遺される方はご家族の相続の負担を減らすことを願ってすることですので、円満・安心への対価としては相当額として考えられる場合が多くなります。
②公正証書の作成については、厳密な方法が取られます。公証人の前で遺言者が遺言書の内容について口述するか、公証人が遺言書の内容を読み上げて遺言者と証人の確認をとるという方法によって行われます。ここで遺言者に行為能力があるかどうかも判断します。
証人も公正証書を作成する重要な要件になりますので、途中退出することは許されず、作成の最初から最後まで立ち会うこととなります。
③については公正証書作成の過程で、内容が公証人や証人にわかることとなります。当然公証人や証人には守秘義務がありますので、ここから外部に内容が漏れる心配はありません。他の相続人等については内容を知ることはできません。
ではメリットはどのようなものになるでしょうか。
①最終的に法律の専門家である公証人が関与しますので、方式不備や内容の不備による無効は回避できます。
②遺言書が公証役場に保管されるので、紛失や改ざん等のおそれはありません。
③遺言者の死後、相続人が容易に探すことができます(相続が開始された場合、遺言書の存在を知らない場合でも通常は段取りとして公証役場を当たります)。
④家庭裁判所での「検認手続き」は不要です。
⑤自分で直接作成することができなくても、遺言能力があれば作成することができます。
⑥公正証書遺言の場合は、遺言書の内容がほぼ確実に実現されます。
自筆証書遺言の記事で書きましたが、自筆証書遺言のデメリットとされていることの多くは、法律の専門家が関与しないことで起こるものです。公正証書遺言の場合は作成の過程で専門家が必ず関与しますので、そういったトラブルを防ぐことができます。
ただ自筆証書遺言も、費用がかからず手軽に書く事ができるというメリットは大きいものですので、できれば自筆証書遺言を欠かれる際にも、行政書士のアドバイスに従って(費用はかかりますが)書かれることをお勧めします。
READ MORE

相続分野の民法の一部改正が7月1日に施行されます。
それに先立ち、本年1月13日に自筆証書遺言書の方式緩和(自書以外の財産目録可)の改正民法が施行されました。これは、財産目録について、従来は手書きでないと認められていなかった要件を、銀行通帳等を添付すればパソコンや自分以外の他者の作成によるものでも認めるという内容になります。
ニュースでも流れたのでしょうか、当職のホームページの当該ページへのアクセスも、2-3ヶ月にわたって通常月の1.5倍ほどに上がっています。相続に比べると遺言ページへのアクセスは多くないのですが、普段意識していなくてもニュースになると興味がわくのでしょうか。そのままご依頼いただけると、なおありがたいのですが。。いつかご依頼いただけることをお待ちしております。
さて要件緩和によって自筆証書遺言の作成については多少ハードルは下がりましたが(財産の多い方はなおさら)、そのほかの自筆遺言の要件についての知識はまだまだ低いようです。もちろんご自身で時間をかけて勉強し、ご自分で書かれる方もいらっしゃると思いますが(最大のメリットは費用面ですが)、要件不備で遺言書としての法的効果がなかったり、相続人にかえって迷惑を掛ける自筆証書遺言の多いことも確かです。
もちろんご自身はよかれと思って書かれている訳ですが、中途半端な知識で書かれるため、法律要件を満たしている遺言書は必ずしも多くはないと思われます。日付間違いや誤記などのケアレスミスの場合、あるいは署名の不備等の場合は相続人の方々の合意があれば大きな問題はないと思いますが、これとて訴訟になった場合は認められない場合も多くなります。
一番困るのは、相続人や相続財産の特定が曖昧な場合です。例えば、「預貯金を子供3人に等分に」という記述であれば、単純に分割することは可能ですし、銀行もその記述をもって払い戻しに応じてくれると思います。しかし、「不動産を子供3人に平等に」という文言であれば、どの不動産をどのように分割するのか特定できませんので、不動産登記は難しくなります。この場合は遺産分割協議によって具体的に不動産を分割し(あるいは特定の相続人に単独に)、分割協議書に明記する必要が出てきます。
この遺言書の場合も相続人の皆さんが不仲でなく、遺言者に寛容であれば遺言書の文言に則した形で協議は行われるのでしょうが、えてしてその遺言によって利益を受ける者は拡大解釈でその文言を了とし、利益を害する者は断固反対する。そのような事態も決して少なくはないでしょう。
このような遺言書があった場合は意見が分かれる、あるいは協議の前段部分で時間を取られる弊害が大きくなります。また協議が成立しても後々までの遺恨の原因になります。
自筆証書遺言を書かれる場合でも必ず専門家に指導を仰ぐ、あるいは公正証書遺言にする。費用はかかりますが、本来の目的を達成するためには必要なことです。行政書士のような専門家は時間を掛けて勉強し、また数々の事例からベストのアドバイスを行っていきます。
READ MORE