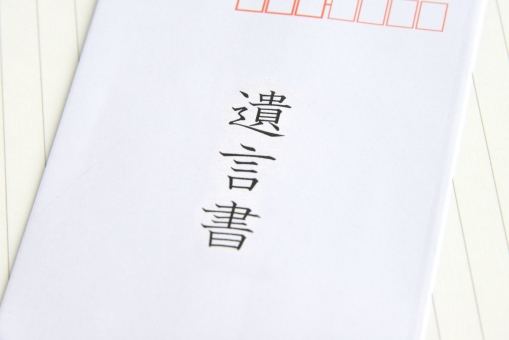今日は商法の続きを書いていきます。
前回は商号というものについて書きましたが、商号はその商号を定めた者しか使用できません。しかしその商号を定めた者が許可を与えた者については、その者の商号を使って営業をすることができます。これを「名板貸」といいます。
商号を貸した者を「名板貸人」と言い借りた者を「名板借人」と言いますが、お客さんや取引業者などが名板貸人の店と誤認して、その名板借人から不利益を被った者がいた場合は、名板貸人は名板借人と連帯して弁済する義務を負わなければなりません。
名板貸人の責任の成立要件としては次のとおりです。
①名板借人が名板人の商号を使用しているという外観があること
②名板貸人が許可をしたという帰責事由があること(許可は黙示でも認められます)
③善意無重過失である第三者が誤認したこと
です。なお、商号に付加された語句がある場合や商号が簡略化されている場合にも、第三者の誤認がある限り責任が発生します。ただこの場合には誤認された営業が、本来の商号である営業と同種であることが必要になります。
名板貸人に責任が及ぶ範囲としては、自分の商号を使って名板借人が行った、取引によって生じた債務になります。取引によって生じた債務については、名板貸人は名板借人と連帯して責任を負います。
この責任の範囲には、交通事故などの不法行為による損害賠償は原則として含まれません。しかし詐欺などの、取引行為と判断される不法行為については、責任の範囲に含まれるとされます。
では名板貸ではなく、営業を譲渡とした場合の責任についてはどうでしょうか。この場合は、譲渡される営業によって生じた債務は原則譲渡人が負いますが、譲受人が債務引受などをした場合については、譲受人も責任を負うことになります。また併せて譲渡人は、競業避止義務も負うこととなります。
次は「商業使用人」について見てみましょう。
「商業使用人」とは、雇用されて営業を補助する自然人を言います。商業使用人には、支配人や店舗の使用人などがあります。
「支配人」とは、商人や会社から営業所等の営業や事業を任された者を言います。支配人を選任した場合は、必ず登記をしなければなりません。
この支配人というものは商人等に代わる代理権を持ちますが、この代理権については営業や事業に関する一切の、裁判上または裁判外の行為に及びます。なお、支配人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできません。例えば支配人が行える業務を限定したとしても、通常に考えれば支配人の責任の範囲である、と考える善意の第三者には対抗できないということです。
では、支配人の義務についてはどうでしょうか。支配人は、雇用契約上の善管注意義務や報告義務などの責任を負っていますが、そのほか営業避止義務や競業避止義務というものも負っています。言い換えると、支配人は商人の許可を得なければ、次の4つをすることができないというものです。
①自ら営業を行うこと
②自己または第三者のためにその商人の営業範囲内の取引を行うこと
③他の商人や会社、外国会社の使用人になること
④会社の取締役や執行役または業務を執行する社員になること
です。以上支配人とは、商人から権限を付与された者になりますが、一方、表見支配人というものも存在します。表見という言葉は、民法の表見代理人の話に出てきましたね。それと同じようなものになります。
https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/date/2018/06/20
「表見支配人」とは、包括した代理権を与えられていない使用人であるにもかかわらず、支配人らしく思わせる名称を付けられた使用人のことを言います。例えば、責任権限を持っていない店員さんであるにもかかわらず、「お店責任者」などといった名札を付けられている場合がこれに当たります。
表見代理人は、裁判外の行為に関しては、善意の第三者に対しては支配人と同一の権限を有するとみなされます。権限がなくても、裁判上の行為を除き、善意の第三者に対しては支配人と同様の効力を有することとなります。責任権限がなくても、第三者に支配人と誤認させるような表示をさせている以上、裁判まで発展していない事案については、責任を持ちますよということになります。
Related Posts

今日は詐害行為取消権について書いていきます。
「詐害行為取消権」とは、債務者がその責任財産を減少させる法律行為(詐害行為)をした場合に、債権者がその行為を取り消し、減少した財産を回復させる権利をいいます。これは強制執行を行う前の準備段階として、総債権者の責任財産の保全を目的とした制度になります。
「詐害行為取消権」の成立要件としては、次の6つが挙げられます。
①保全される財産が金銭債権であること
②保全される財産が、詐害行為前に成立していること
③債務者が詐害行為時および取消権行使時に無資力であること
④財産権を目的とした法律行為であること
⑤債務者に詐害の意思があること
⑥受益者や転得者が悪意であること
です。
では、詐害行為取消権の行使の方法や効果について見ていきましょう。
詐害行為取消権は、債権者が必ず「自己の名」で行ないます。また債権者代位権と異なり、必ず「裁判上」で行わなければなりません。
取り消しを行える範囲は、債権者の被保全債権額の範囲に限定されます。建物のように目的物が不可分の場合は、被保全債権額が建物価格に足りなくても、詐害行為の全部を取り消すことができます。
詐害行為取消権を行使できる期間は、債権者が取り消しの原因(詐害行為)を知った時から2年間(消滅時効)となります。知らない場合も詐害行為から20年で時効(除斥期間)となります。
詐害行為取消権の効力は全債権者の利益のために発生することとなり、受益者や転得者から取り戻された財産は、全債権者の共同担保となります。目的物の引渡しについては債権者代位権同様、原則は債務者への引渡しとなりますが、直接債権者への引渡しを請求することもできます。
とは言っても、詐害行為取消権には効果の及ぶ範囲が定められています。債務者であっても自分の財産を処分することは自由であるはずですが、詐害行為取消権はこの自由を制約するものとなりますので、その制約を最小限に抑える内容となっています。
これから、詐害行為取消権の被告は債務者ではなく、受益者または転得者にすべきとしています。
また取り消し判決がなされる場合でも、その効力の及ぶ範囲は取り消し債権者と相手方(受益者または転得者)の関係でのみ詐害行為の抗力を失わせるものであって、第三者の法律関係には影響は及ぼさないとされています。
READ MORE
今日は民法における監督者や使用者の責任について書いていきます。
今日確認するのは、
1.責任無能力者の監督義務者等の責任
2.使用者の責任
3.工作物責任
4.注文者の責任
5.動物占有者の責任
についてです。ではそれぞれ見ていきましょう。
まず1の「監督義務者の責任」についてです。前回の不法行為の記事でも触れました、①の未成年者等の責任無能力者ですが、これらの者は、他人に違法な行為で損害を与えても責任を負わない場合があります。しかしそれでは被害者の救済が図られませんので、被害者救済の手段として責任無能力者を監督すべき「法定義務」のある、監督義務者や代理監督者が責任を負う場合があります。
監督義務者等は、監督を怠らなかったことを立証できない限り、責任を負うとされています。すぐ近くで万全の体制で監督をしていても不測の自体で損害が生じてしまった時などは、監督を怠らなかったことを証明すれば責任は問われないということになります。
ここで未成年である責任無能力者とはだいたい12才未満の者とされていますので、12才以上の責任能力を有する未成年の場合には、監督義務者は原則責任を負いません。しかし義務違反と未成年の不法行為に相当因果関係が認められる時は不法責任を負う場合があります。
次に2の「使用者責任」についてです。「使用者責任」とは、被用者(使用されている者)がその使用者の事業を執行する上で、他者に違法な損害を与えた場合の責任を言います。使用者責任成立の要件は次のとおりです。
①使用者と被用者との間に、指揮監督などの使用関係があること
②被用者の加害が事業の執行についてなされること
③被用者が不法行為の一般的成立要件を備えていること
④使用者が専任・監督上の注意義務を尽くしていないこと
です。
②の事業執行についてとは、具体例を挙げますと、タクシーや運送業の運転手が仕事中に事故を起こした場合などです。ただここで問題となるのは、どこまでの範囲が業務執行に当たるのかということです。運行中によそ見をして事故を起こしたなどの場合がこれに当たりますが、そのような場合のみならずもう少し広い概念で、客観的に見て職務行為の範囲内だと認められる場合が該当するとされています。
なお業務中の被用者の暴力行為については、その損害が業務を行うことがきっかけとなり、またその業務と密接な関連性を有すると認められるか、によって判断されます。
今述べたように、使用者はその使用者責任によって被害者に賠償を行いますが、その場合に直接の加害者は蚊帳の外かというとそうではありません。賠償をした使用者は、今度は加害者である被用者に行った賠償について求償することができます。ただし求償する内容についてはすべてをできるわけではなく、所々の事情を鑑みて、信義則上相当と認められる範囲に限定されます。
被用者が第三者と共同で不法行為を行い、その賠償を使用者がした場合には、使用者は被用者のみならず第三者にも求償をすることができます。この場合は被用者と第三者の過失割合によって求償を行ないます。
3の「工作物責任」とは、土地の工作物の設置や保存(維持管理)について適正に行う責任を言います。この設置や保存に「瑕疵」があり、そのために他人に損害を与えた場合はまずその工作物の「占有者」が責任を負います。
この占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたことを証明したときは、「所有者」が責任を負うこととなります。
ここで言う「土地の工作物」とは、工事などによって土地に固定して作られたものをいい、建物や橋、鉄道などがこれに当たります。工作物の「瑕疵」とは、工作物が通常有すべき安全性を欠いていることをいいます。その物自体の性能などが安全性を欠いている場合だけでなく、その物に係る安全設備を欠いているために危険な状態を生じさせている場合も瑕疵に該当します。
占有者は必要な注意を払ったことを証明すれば免責されると書きましたが、最終的な所有者の責任は免責が認められない「無過失責任」となります。
4の請負契約などの「注文者の責任」ですが、注文者がした指図や自己の過失がない限りは、原則注文者については第三者に損害を与えても賠償責任は負いません。
最後に「動物占有者の責任」についてです。ペットの買主などを言いますが、この動物を管理する者は、動物が他人に与えた損害については原則賠償する責任を負います。ただしこの場合も、占有者が相当の注意をもって管理したことを立証すれば免責される場合もあります。
READ MORE

今日は権利能力・意思能力・行為能力というものについて書いてみます。
まず権利能力とはどういうものでしょうか。権利能力とは、権利や義務の主体となりうる地位や資格のことであり、自然人である人間はもちろんのこと、法人も含む概念です。生まれた時に取得し、死亡した時に失います。相続の記事でも触れましたが、胎児については権利能力は認められませんが、相続や遺贈を受ける権利、また不法行為による損害賠償権は例外として、生きて生まれた場合にさかのぼって認められることになります。
次の意志能力とは、自分の行為の結果を理解(弁識)できるだけの精神能力のことをいい、一般的には10才程度の者であれば有するとされています。よく犯罪などで鑑定が行われますが、通常は意思能力を有するものであっても、泥酔している場合などは意思能力を有していないとされます。
意思能力は私的自治の前提となりますので、意思無能力者の行為はすべて無効となります。
行為能力とは、単独で有効な法律行為を出来る能力のことです。これは法律でその地位や資格が定められており、法律によって行為能力が制限されている者を制限行為能力者といいます。それらの人たちの行動を抑制するという趣旨ではなく、物事を単独で行ってしまった場合にその結果から守るという趣旨で、民法に明記されています。
制限行為能力者は未成年者、成年被後見人、被保佐人、被補助人の4つが定められています。未成年を除く3者については、保護の必要性が大きい順に並べましたが、それらについて順に見てみましょう。
まず未成年者ですが、定義としては、20歳に満たない者を未成年者といいます。20歳になると成年となります。しかし婚姻をすれば成年擬制という制度によって、成年とみなされます。これは離婚してもその後も有効になります。成年擬制は法律のいろいろな場面で出てきますので、覚えておいたほうがよいです。
例えば養子をするのは成年でないとできませんが、成年擬制の場合はできます。また商法においても未成年は登録をしないと営業ができませんが、これも必要なくなります。
未成年者が契約等の法律行為を行う場合には、親権者などの法定代理人の同意が必要になります。そしてこの規定に反して行った行為については、本人または法定代理人が取り消すことができます。
例外としてはむつかしい表現になりますが、「単に利益を得、義務を免れる法律行為」は単独でできます。贈与を受けたり債務を免除されたりがこれに当たります。成年になると様々な権利義務が発生しますが、成年擬制の場合にも権利も発生しますが、反面法律で守られる場面も減るということです。権利と義務は表裏一体です。
未成年者の法定代理人(親権者等)の権限としては、代理権、同意権、取消権、追認権があります。法定代理人は未成年が行なった法律行為について、同意をしたり後から認めることによって、行った法律行為を有効なものにすることができます。
次は成年被後見人です。これは精神上の障害によって、「事理弁識(じりべんしき)能力を欠く常況」にあり、他の者の後見が必要な者のことをいいます。事理弁識能力とは物事の結果などについて認識することができ、それに対して有効な判断が出来る能力のことです。常況とはいつでもそういう状態にあるということです。一時的な場合には使われません。成年被後見人は、家庭裁判所の後見開始の審判を受けた者がなることができます。
成年被後見人の行った法律行為は取り消せます。これは成年後見人が同意した行為でも取り消すことができます。裏を返せば、成年後見人には同意権はないということです。ただし日常品の購入など、日常生活に関する行為は取り消せません。成年後見人の権限は、代理権、取消権、追認権です。
次は被保佐人について見てみます。被保佐人は、精神上の障害によって、事理弁識(じりべんしき)能力が「著しく不十分」な者で、家庭裁判所の補佐開始の審判を受けた者をいいます。原則として単独で法律行為を行うことはできますが、不動産などの重要な財産の処分などは保佐人の同意が必要になります。
同意を欠いた場合は取り消すことができます。日常品の取り扱いに関しては取り消せません。保佐人の権限は民法13条1項に書かれている項目(不動産の処分や訴訟行為、相続に関すること等)についての同意権、取消権、追認権、代理権があります。この場合の代理権についてのみ、家庭裁判所の審判を受けるかどうかは本人自身の請求か同意が必要になります。本人が拒否すれば代理権は付与されません。
最後の被補助人とはどのような者でしょうか。これは事理弁識能力が「不十分」であり、家庭裁判所の補助開始の審判を受けた者をいいます。本人自身が審判開始を請求するか、本人以外の者が請求をした場合は、本人の同意が必要になります。前2者と異なり、補助開始の審判をする場合は同時に同意見付与の審判と代理権付与の審判、この一方または両方の審判をしなければなりません。被補助人の権限ですが、代理権付与の審判を受けた特定の行為については代理権をもち、同意権付与の審判を受けた特定の行為については同意権、取消権、追認権をもちます。以上において各後見人はひとりでも複数でも構いません。法人でもなることができます。また必要な場合には後見人を監督する立場の監督人も付けることができます。また後見人は任意に契約する(任意後見人)することもできますが、任意後見の場合は代理権のみが付与され、同意権や取消権は付与することができません。
相続の場面では、共同相続人がいる場合には必ず遺産分割協議が行われます。この協議では相続人全員の参加と合意が必要となります。ですので、相続人の事理弁識能力に問題がある場合は代理人の選任が必須となる場合があります。その者がまだ代理人を有していない場合には、状況をみて家庭裁判所への選任請求をしなければなりません。また相続人に未成年がいる場合には、親との利益相反との関係から特別代理人の選任も請求しなければならないので、注意が必要です。特別代理人についてはあらためて別の記事で書いていきます。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry62.html
READ MORE
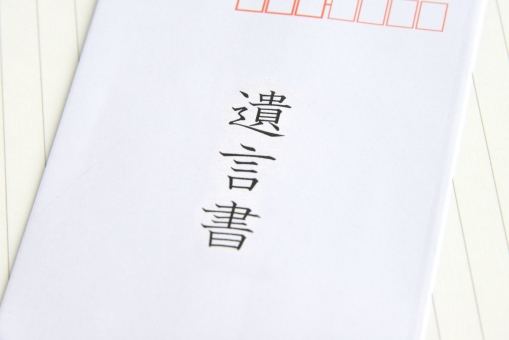
今日は相殺というものについて書いていきます。
「相殺」とは、2人のものがお互いに同種類の債権債務を有している場合に、その債権債務を対等額で消滅させる、相殺する側の一方的な意思表示のことを言います。
相殺の効果は債権債務の現実の履行を省略することにあり、相殺適状を生じた時にさかのぼって抗力を生じます。お互いの債権が相殺の要件を満たしている状況を「相殺適状」と言います。
相殺には「する側」と「される側」がありますが、相殺する側の債権を「自働債権」(自動ではありません)と言い、相殺される側の債権(相殺する側の債務)を「受働債権」と言います。
相殺が成立するには次の5つの要件があります。
①2つの債権が対立していること
②双方の債権が同種の目的を有すること
③双方の債権が弁済期にあること
④双方の債権が有効に存在していること
⑤相殺を許す性質の債権であること
です。
要件③についてですが、受動債権(相殺される側)については債務者が「期限の利益」を放棄することができますので、必ずしも弁済期にある必要はありません。ですので条文にあるように双方が弁済期にある必要はなく、自働債権のみ弁済期にあることが必要になります。
要件④の、双方の債権が有効に存在していなければならない、という要件についても例外があり、債権が時効によって消滅していた場合でも、その債権が時効消滅前に相殺することができる状態に既になっていた場合には、この債権を自働債権として相殺することができます。なお、お互いの債権が相殺の要件を満たしている状況を前述の「相殺適状」と言います。
要件⑤の相殺を許さない性質の債権についてですが、自働債権に「同時履行の抗弁権」などの抗弁権が付いている場合には相殺することができません。一方、受働債権に抗弁権が付いている場合には、相手方の利益を特に害することはないため、相殺することも許されます。
また自働債権が差し押さえられてしまった場合ですが、これは法律によって処分等が禁止されることになるため、相殺をすることができなくなります。
先に相殺は一方から相手方への一方的な意思表示と言いましたが、裏を返せば相殺の意思表示がない限りは相殺は行われず、債権は消滅しないことになります。また相殺する側の一方的な単独行為になりますので、相手方の同意は必要ありません。
なお相殺の意思表示には、条件や期限などを設けることはできません。
最後に相殺が禁止される場合について触れておきます。次のような場合は相殺が禁止されます。
①当事者が相殺禁止の特約をした場合
②受働債権が不法行為にもとづく損害賠償請求権である場合
③受働債権が差押禁止債権である場合
④受働債権が支払いの差し止めを受けた場合
です。
②について説明をしますと、例えば不法行為を受け損害賠償権を有した被害者が、その加害者に借金をしていた場合が挙げられます。この場合では、加害者側が被害者に貸していた100万円で、被害者側からの100万円の損害賠償権を相殺する、ということはできないということになります。
これは相殺がなされてしまうと、被害者側が現実の救済を受けられなくなってしまうことと、それがために報復などの不法行為を誘発するおそれがあることが理由になります。
なお立場を入れ替え、被害者側の債権を自動債権とし、被害者側から相殺することは判例から認められています。
READ MORE

今日は遺言について書いていきます。遺言については以前にも書きましたが、相続遺言に関する民法がこの7月に約40年ぶりに大幅改正されましたので、それも含めて見てみましょう。
遺言を残そうとされる目的の多くは、ご自分の作られた財産をきちんとご自分の手で、ご自分の意思で配分したいというところにあると思います。考えられるきっかけはちょっとしたことからかもしれませんが、その動機の多くは遺されるご家族のことを考え、円満でスムーズに相続を終えてもらいたいという気持ちから発せられるようです。
中には家族親族がいがみあっていたり、複雑な関係性であったり、また相続人がいないなどの理由からトラブル防止のための遺言を書かれる場合もあると思います。また事業承継にあっては、自ら思い描く将来のために、きちんと整理した形で財産を相続させる場合もあろうかと思います。
いずれにせよ遺言を残される以上、法的に効果のある遺言にしなければなりません。では法的に効果のある遺言とはどのようなものでしょうか。
遺言自体はどのような形でも残すことができます。口頭で伝える場合もあれば、録音やビデオで伝える場合もあります。また通常は皆さん考えられるところの書面で残すことが多くなります。しかし法的に効果のある遺言は、きちんと法律に従った形式で、書面として残さなくてはいけないものになります。
きちんとビデオに撮っていても、それがそれぞれの相続人が納得するものであれば問題ありませんが、争いになった場合は法的に根拠がないものとして認められないものになります。
昨日たまたまビデオで「激動の1750日」という映画を見ていて、三代目姐が「先代が言い残した」という一言で後継が決まってしまいました。実際に言い残してはいないので争いになった場合は法的根拠のないものとなりますが、特殊な世界であれ、「故人が言っていた」の一言で相続が決まってしまってはたまりません。そこかしこでトラブルが頻発するでしょう。そんなトラブルを起こさないためにも、法律が遺言の形式を定めています。
ここでの法律は「民法」になります。民法は、私人間の生活関係を規律する「私法」の一般法(国家等の公権力と私人の関係を規律する法である法律を「公法」といい、これには憲法・行政法・民事手続法・刑法・刑事手続法があります)であり、その内容は「財産法」(ここには物件法と債権法があります)と「家族法」に分かれます。
「家族法」には家族や親族の範囲や関係性について規定する「親族法」の部分と、相続や遺言について規定している「相続法」の部分があり、ここで遺言についても明確に規定してます。
では民法に規定する遺言について見ていきましょう。遺言の方式について、民法では「普通方式」と「特別方式」を定めています。我々が一般的に理解している遺言とは普通方式のものになりますが、簡単に特別方式の遺言について見てみます。
「特別方式」の遺言については滅多にお目にはかかれませんし、またそういう立場になっては困るのですが、緊急時に発する遺言になります。ここでは詳細は省きますが、災難がまさに降りかかっている際に発する「危急時遺言」と、世間から隔絶された場所にあるときに発する「隔絶地遺言」があります。
「危急時遺言」には「死亡危急者遺言」と「船舶避難者遺言」がありますが、前者は病気やけが、あるいは災害が差し迫っている際に発っするものであり、後者は船舶が遭難にあっている際に発するものになります。
また「隔絶地遺言」には、「伝染病隔離者遺言」と「在船者遺言」があります。前者は伝染病隔離施設や刑務所服役中などの場合、後者は遭難していない船舶の中で作成されます。
いずれも危難は迫ってはいませんので、本人が書く事になります。以上4種類が特別方式になりますが、それぞれ証人であったり検認であったり、その手続きは詳細に決められています。民法は約120年前に制定されましたので、情報の発達していない時代を背景としています。
READ MORE

今日は民法のうち「家族法」の分野に定められた、「婚姻」について書いていきます。ここも相続の際には非常に大きく関わってきます。
民法では現行法や改正法においても「法律婚主義」を採用しています。ですので相続される権利のある配偶者は、「婚姻関係にある者」のみになります。どんなに長く一緒に生活をし事実上は夫婦の関係にあるにしても、婚姻の届出をしない限りは婚姻は成立せず、法律上は夫婦と認められないことになります。
「婚姻」が成立した場合は、基本的には離婚をしない限りは配偶者としての権利は保障されます。
なお「婚姻」は私法上の契約であり本人の意思が最大限尊重されますので、成年被後見人であっても「単独で」することができます。
婚姻の成立要件としては次の3つがあります。
1.婚姻意思の合致(実質的要件)
2.婚姻障害に該当しないこと(実質的要件)
3.婚姻の届出(形式的要件)
です。
一つ目の要件である「婚姻の意思の合致」には、当事者間に真に社会観念上夫婦であると認められる関係の設定を欲する効果意思が必要である、とされています。つまり当事者お互いが自ら、夫婦の関係になることを望んでいることが要件になります。
本当に婚姻する意思があるわけではなく、相続などのためだけに形式的に婚姻届を出した場合はその届出は無効になります。
次の「婚姻障害」には、次のようなものが該当します。
①婚姻適齢
②重婚禁止
③再婚禁止期間
④近親婚の禁止
⑤直系姻族間の婚姻禁止
⑥養親子関係者間の婚姻禁止
⑦未成年者の婚姻
になります。
「婚姻適齢」とは、男性は18歳、女性は16歳にならないと婚姻できないというものです。これに違反した場合は婚姻が取り消されます。なお女性が男性と異なるのは合理性を欠くとして、女性も18歳に引き上げる方向で民法改正が進められています。
「重婚禁止」とは、配偶者のある者は重ねて婚姻することができないというものです。日本においては「一夫一婦制度」が維持されています。
なお重婚については、行方不明者であった配偶者が現れた場合の対応に問題が残ります。これについては先に「失踪宣告」で記事に載せましたので、ご確認ください。
https://estima21-gunma-gyosei.com/archives/786
「再婚禁止期間」とは、女性が再婚するには、婚姻の解消又は取消しの日から起算して100日経過後でなければすることができないというものです。なおこの期間の例外として、女性が前婚の解消若しくは取消しの時に懐胎(妊娠)していなかった場合、または女性が前婚の解消若しくは取消しの後に出産した場合には、再婚禁止期間の規定を適用されません。
以前はこの期間が6ヶ月経過後とされていましたが、平成28年6月1日施行の改正民法により見直しが図られました。なおこの規定は、父親の特定を法律上可能にするために設けられています。
次の「近親婚の禁止」では、優生学上の理由から、直系血族または3親等以内の傍系血族の間では婚姻することはできないというものになります。前回の親族の記事で確認しますと、3親等の血族である叔母とは結婚できませんが、その子であるいとことは結婚できることになります。菅元首相の奥さんもいとこでしたっけ。
「直系姻族間の婚姻禁止」については優生学上の理由はありませんが、同義上の理由から設けられています。これについては姻族関係が終了した後も禁止が解除されません。
「養親子関係者間の婚姻禁止」についても直系姻族間と同様の取り扱いになります。
以上挙げた規定については、違反した場合はすべて婚姻が取り消しとなります。
最後の「未成年者の婚姻」については、最初の項の婚姻適齢に述べましたが、婚姻適齢に達しても未成年者である限りは、婚姻するためには父母の同意が必要になります(父母の一方が反対等しても、一方の同意で足ります)。これについては18歳成人の改正民法が2022年4月1日より施行されますので、規定が変わることになります。
なお実際は父母の反対があったとしても、婚姻自体は有効になります。
READ MORE

今日は相続にも大きく関係してくる、親族というものについて書いていきます。
相続を受けることのできる者(相続人)は「相続人」である「配偶者」「子」「直系尊属」「兄弟姉妹」になりますので、親族の範囲を見た上で、これらの者がどの位置にいるのかを見てみます。
また今回成立した相続関係の民法改正において、「相続人以外の親族の貢献を考慮する方策」が加えられましたので、今まで以上に「親族」という言葉が使われる機会が多くなると思います。
https://www.yuigon-souzoku-gunma.com/category13/entry69.html
「親族」とはどのようなものを言うのでしょうか。民法における「親族」とは、次の者を言います。
①6親等以内の血族
②配偶者
③3親等以内の姻族
です。
まず「血族」とは、血縁関係のある者相互間(誰から見てもお互いに)および、法的に血縁があると制度上みなされる(擬制)者相互間を言います。前者を「自然血族」、後者を「法定血族」と言います。
「自然血族関係」は出生によって生じ、死亡によって終了します。「法定血族関係」は養子縁組によって生じ、離縁や縁組みの取り消しによって終了します。
次の「配偶者」は、婚姻によって戸籍上の地位を得た者になりますが、配偶者は血族にも姻族にも属さず親等もありません。
「姻族」とは「配偶者側の血族あるいは血族の配偶者相互間」を言います。例えば配偶者の父や、本人の父の兄弟(叔父)の配偶者は姻族になります。「姻族関係」は配偶者を通じての関係になりますので、配偶者の一方の血族と他方の血族は姻族にはなりません。具体的に言うと、本人の父と配偶者の父は姻族関係には当たりません。
また姻族関係は婚姻によって生じ、離婚によって終了することになります。離婚した元配偶者の親とは知り合いではあっても、法的つながりはなくなるということです。これは離婚の場合であり、死別の場合は届出を行わない限りは姻族関係は当然には消滅しません。
では先に出てきた「親等」とはどのようなものでしょうか。
「親等」とは親族間の遠近度を比較する尺度であり、親族間の「世代」によって決まります。本人から見て「世代」がひとつ変われば1親等という数え方をします。
相続人に当てはめて見ますと、配偶者に親等はありません。子と直系尊属(父母)が1親等、孫や祖父母は2親等になります。兄弟姉妹は親を経由して下がりますので、これも2親等と数えます。本人の叔父や叔母は祖父母を経由しますので3親等、その子であるいとこは4親等になります。
親族については世代をまたがる垂直の広がりと、直系から枝分かれをした横への広がりがあります。
縦への広がりで見てみますと、本人から世代が上の者たちを「尊属」、世代が下の者たちを「卑属」と言います。ですので父は尊属、子は卑属になります。兄弟姉妹やいとこは世代が同じですので、尊属にも卑属にも当たりません。
横への広がりで見てみますと、本人から垂直に遡ることのできる父母や祖父母や曽祖父母、あるいは垂直に下がることのできる子や孫やひ孫などは「直系」になります。
縦横併せてマトリックスで見ますと、上の世代を「直系尊属」、下の世代を「直系卑属」と言います。垂直から枝分かれをした叔父叔母などは「傍系」と言います。これも上の世代を「傍系尊属」、下の世代を「傍系卑属」と言います。
整理してみますと、血族には直系血族と傍系血族があり、直系血族には直系尊属と直系卑属があります。また傍系血族にも傍系存続と傍系卑属があることになります。姻族にも同様の、直系傍系、尊属卑属の関係があります。
改正民法の特別寄与に関しては、具体的に権利の範囲にあるかは事案ごとに確認を要するとことになります。
READ MORE

今日は民法の意思表示について書いていきます。
法律用語の場合、前回の善意・悪意のように独特の表現や意味が使われています。その説明においても独特の微妙な解釈の出来る言い回しがされる場合が多いです。心理留保を「うそ」というように噛み砕いて平易な言葉で説明される場合もありますが、それだとかえって範囲が狭まってしまう場合もありますので、基本的には遠まわしでも回りくどい言い方を使っていきます。
私も行政書士のホームページで主要業務の説明をしていますが、例えば建設業許可など建設業法という法律で決まっていることなので、文として読みやすくこそすれ基本的には表現をあまりいじることなく書いています。グーグル対策なのか個性を出すためかわかりませんが、無理に表現をこねくり回しているものも多く見られますが、そこに意味を見い出せませんでしたのでそういう体裁で作りました。グーグル対策的には良くないことなのかな?まあよいので、話を続けます。
意思表示とは一定の法律効果を期待して、意思を外部に表示する行為のことです。意思表示は、
①効果意思
②表示意思
③表示行為
という段階を経ますが、③の表示行為がなされても、①②の意思を欠く場合には、意思表示があったとはいえないとされています。これを意思主義と言いますが、ここでの効果意思とは、一定の効果の発生を期待してする意思のことであり、表示意思とは意思表示のことでもありますが、効果意思を表示しようとする意思のことです。表示行為はそれらの行為を行うことです。
意思主義では単に行為を行っただけでは意思表示とは言えず、期待する効果が存在しており、またそれを表に出したいという意思がないと意思表示には当たらないということです。
民法を含む私法には、
①権利能力平等の原則
②私的所有権絶対の原則
③私的自治の原則
という3大原則があり、私的自治の原則からは意思主義が望ましいとされています。
効果意思を欠く場合を意思の不存在といい、効果意思を作る状況に瑕疵がある場合を瑕疵ある意思表示といいます。ちなみに「瑕疵」もよく使われる言葉ですが、これは本来備わっているものが備わっていない状況をいう概念です。単純に言えば「きず」のことですかね。
先ほどの効果意思を欠く場合を意思の欠缺(けんけつ)といいます。欠缺とは、ある要件が欠けていることを言います。
意思主義の対義語に表示主義がありますが、発信する側から見た場合には意思主義が有効とされますが、商売などにおいて相手方は表示をのみを見て判断するする場合が多くなります。その場合には効果意思や表示意思は推測でしかありませんので、相手方を保護するという立場から、表示そのものを重視する表示主義も認められています。
ではこれらの意思表示の中でも、法律で無効とされたり取り消されたりする意思表示について見ていきましょう。これらには、
①心理留保
②通謀虚偽表示
③錯誤
④詐欺
⑤脅迫
の5つがあります。心理留保は相手方を保護する表示主義に基づいたものであり、他の4つは意思主義の意思の欠缺によるものとなります。
まず「心理留保」とは、表意者が表示行為に対応する真意のないことを知りながらする単独の意思表示のことです。平たく言えば冒頭の「うそ」のようなものです。表示主義に基づいていますのでその意思表示は有効となります。効果意思や表示意思がなくとも成立します。相手方を保護するものですね。
しかしこれはあくまでも相手方が善意であった場合に限られ、相手方が表意者の真意でないことを知っていた場合や知ることの出来た場合、いわゆる悪意の場合はその意思表示は無効になります。保護される必要がないということになります。
次の「通謀虚偽表示」とは複数の者が、相手方と通謀してする真意でない意思表示のことです。通謀とは、あらかじめ申し合わせて企むことです。これが成立する要件は、
①意思表示が存在すること
②表示と具体的に期待する法律効果が不一致であること
③真意と異なる表示をすることについて、相手方と通謀している
ということです。当事者間では保護されるべきものではありませんので、無効となります。
ここに関与してくる第三者に関してですが、表示後に登場した第三者には対抗できません。「第三者」というのは「当事者および包括承継人以外のもので、虚偽表示の外形を基礎として新たに独立の法律上の利害関係を有するに至った者」を言います。めんどくさい表現ですが、法律できちんと定義されているんだから仕方がありません。これは覚えどころで、私も記述の試験対策で覚えました。新たに云々の前には、それぞれの法律の場面に関与してくる第三者の状況が入ってくることになります。
行政書士の勉強は合格基本書と過去問があれば独学でも問題ないと思いますが(私もそうでしたが)、自分でノート(バインダー式)を作ることと、記述式の想定問題集(私はLECのものを買いましたが、試験に出るまで何年でも使えますよ)は買ったほうが良いと思います。バインダー式であれば、別の参考書からの違う観点を追記したりできますし。
READ MORE

今日は民法における委任契約というものについて書いていきます。
「委任」とは当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって効力が生じる諾成契約になります。
「諾成契約」とは、当事者の意思表示のみで成立する契約のことを言います。ちなみに当事者の合意のみでは足らず、物の引渡しや給付を成立要件とする契約は「要物契約」と言います。
委託する側を「委任者」、承諾する側を「受任者」と言います。ここで委任とは法律行為を委託すると言いましたが、法律行為以外の事務の委託も当然あるわけで、それは「準委任」と言い委任の規定が準用されます。
委任をするにあたっては、委任者側にも受任者側にも義務や責任が発生します。
ではまず委任者側の義務について見ていきましょう。委任者は原則、受任者に経済的に負担をかけないという義務を負い、具体的には次のような義務が発生します。
①報酬支払い義務
②費用前払い義務
③立替費用償還義務
④債務の弁済または担保供与義務
⑤損害賠償義務
です。
まず①についてですが、民法においては委任というものは、原則無償委任になります。ですので、報酬の支払い義務が発生するためには報酬支払いの特約が必要になります。また特約があった場合でも、その報酬は原則後払いになります。
②では、委任された事務を処理するについての必要な費用について、事前に受任者から請求があった場合には前払いをする必要があります。あくまでも遂行に必要な費用の場合です。
③の立替費用とは、必要な費用が前払いされずに、受任者によって立替えられた費用のことです。この場合は立替えた費用を請求できるのみならず、支出以降の利息も請求することができます。
④の債務とは、委任事務を行うについての費用的なものに収まりきらず、受任者が債務を負った場合のものを言います。この場合の債務は必要と認められる範囲に限られますが、その弁済を自分に代わってするようにと、受任者は委任者に対して請求することができます。まだ弁済期の到来していない債務については、委任者に担保を請求することもできます。
⑤の損害賠償義務とは、受任者が自分に過失がないにもかかわらず損害を被った場合に、委任者に損害賠償を請求できる権利になります。この場合の委任者の責任は無過失責任(委任者に責任がなくても負う責任です)になります。
委任契約はその目的を完了したときに終了しますが、それ以外にも終了となる場合があります。
まず、理由がなくても当事者双方が一方的にいつでも解除が行える、「無理由解除」(告知と言います)というものがあります。もともと委任契約というものは無償契約が原則であるように、当事者間の信頼関係が基礎となるものになります。ですので、この信頼関係が崩れた時など、委任契約を継続することが難しいからです。
しかし関係が崩れたから一方的にというのも理不尽ではありますので、やむを得ない事由がある場合を除き、相手方に不利な時期の解除については、損害賠償を条件に認められることとなります。
また告知以外でも、委任者が死亡したり破産手続開始の決定を受けたときや受任者が死亡したり破産手続開始の決定を受けたとき、あるいは後見開始の審判を受けた場合は、当然に終了します。
READ MORE

相続分野の民法の一部改正が7月1日に施行されます。
それに先立ち、本年1月13日に自筆証書遺言書の方式緩和(自書以外の財産目録可)の改正民法が施行されました。これは、財産目録について、従来は手書きでないと認められていなかった要件を、銀行通帳等を添付すればパソコンや自分以外の他者の作成によるものでも認めるという内容になります。
ニュースでも流れたのでしょうか、当職のホームページの当該ページへのアクセスも、2-3ヶ月にわたって通常月の1.5倍ほどに上がっています。相続に比べると遺言ページへのアクセスは多くないのですが、普段意識していなくてもニュースになると興味がわくのでしょうか。そのままご依頼いただけると、なおありがたいのですが。。いつかご依頼いただけることをお待ちしております。
さて要件緩和によって自筆証書遺言の作成については多少ハードルは下がりましたが(財産の多い方はなおさら)、そのほかの自筆遺言の要件についての知識はまだまだ低いようです。もちろんご自身で時間をかけて勉強し、ご自分で書かれる方もいらっしゃると思いますが(最大のメリットは費用面ですが)、要件不備で遺言書としての法的効果がなかったり、相続人にかえって迷惑を掛ける自筆証書遺言の多いことも確かです。
もちろんご自身はよかれと思って書かれている訳ですが、中途半端な知識で書かれるため、法律要件を満たしている遺言書は必ずしも多くはないと思われます。日付間違いや誤記などのケアレスミスの場合、あるいは署名の不備等の場合は相続人の方々の合意があれば大きな問題はないと思いますが、これとて訴訟になった場合は認められない場合も多くなります。
一番困るのは、相続人や相続財産の特定が曖昧な場合です。例えば、「預貯金を子供3人に等分に」という記述であれば、単純に分割することは可能ですし、銀行もその記述をもって払い戻しに応じてくれると思います。しかし、「不動産を子供3人に平等に」という文言であれば、どの不動産をどのように分割するのか特定できませんので、不動産登記は難しくなります。この場合は遺産分割協議によって具体的に不動産を分割し(あるいは特定の相続人に単独に)、分割協議書に明記する必要が出てきます。
この遺言書の場合も相続人の皆さんが不仲でなく、遺言者に寛容であれば遺言書の文言に則した形で協議は行われるのでしょうが、えてしてその遺言によって利益を受ける者は拡大解釈でその文言を了とし、利益を害する者は断固反対する。そのような事態も決して少なくはないでしょう。
このような遺言書があった場合は意見が分かれる、あるいは協議の前段部分で時間を取られる弊害が大きくなります。また協議が成立しても後々までの遺恨の原因になります。
自筆証書遺言を書かれる場合でも必ず専門家に指導を仰ぐ、あるいは公正証書遺言にする。費用はかかりますが、本来の目的を達成するためには必要なことです。行政書士のような専門家は時間を掛けて勉強し、また数々の事例からベストのアドバイスを行っていきます。
READ MORE