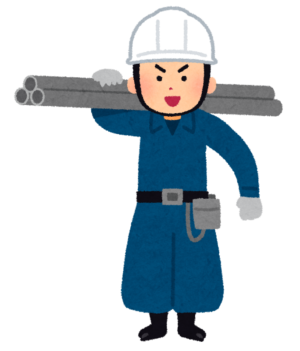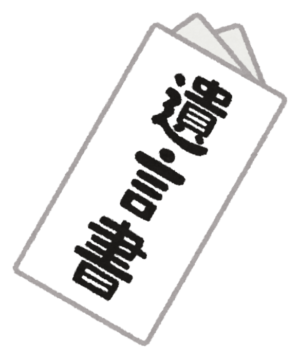今日は建設業許可取得の必要性について書きます。
建設業は時に公共性も伴いまた総じて発注金額も大きいところから、様々な法律による規制が設けられています。特に建設業法第一条の「この法律は、建設業を営む者の資質の向上、建設工事の請負契約の適正化等を図ることによつて、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進し、もって公共の福祉の増進に寄与することを目的とする」ことから、許可や運用には厳しいルールや罰則が設けられています。
しかし建設業界は企業ベースでは99.9%が中小企業であり、そのうちの95.5%が小規模企業やひとり親方等の個人事業主です。
建設業許可については厳しい許可要件や取得にかかる費用も発生しますので、すべての事業者に許可取得を強制することは合理的ではありません。ですので一定の規模(請負金額)以上の建設業者について、取得を強制する(建設業許可がないと、一定額以上の請負工事を施工することができません。施工した場合は違法となります)法律となっています。
許可取得のハードルや中小企業の状況については別の記事で記載していきます。
建設業許可は人や施設、財務面などの要件を満たさないと許可を受けることができません。特に人に関するものは、経験年数を証明しなくてはならなかったりかなり煩雑な手間を要します。
もちろん役所のホームページ等から知識を得て、ご自分で許可申請をすることも可能です。しかしお忙しい経営者の方々にとっては時間はお金には変えられませんので、必然的に行政書士等の専門家に許可取得を依頼することが多くなります。
建設業許可は一定基準を超える建設業者(あるいは関連する電気工事業者等)が取得しなければいけない許可ではありますが、それ以外の業者ももちろん取得することができます。
現在は法的に建設業許可を取る必要がない状況であっても、近い将来により範囲を広げた工事に参加する意欲がある場合は、現段階でも検討する価値は高いと思います。
昨今は社会的にも、また行政からも「コンプライアンス」の必要性が強く望まれています。特に建設業においては社会に安心を与える重要性から元請業者等に対してもより強く望まれていますし、元請業者自身も自らの責任という観点から、契約する下請け等に対しても建設業許可を有した業者を採用する方向性も見えてきています。
ここのところの人手が足りない業者が足りないという状況においても、まず優先されるのはコンプライアンスという時代であることは否めません。
先に書きましたとおり、許可申請やその維持についてはそう安くはない諸々の費用が発生します。ですので現在の状況と今後の展望を鑑み費用対効果の面も含めて、この機会に建設業許可の取得をご検討されてはいかがでしょうか。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/
Related Posts
本日は建設業許可取得についてお話します。
以前書きましたとおり建設業を営もうとする者は建設業法によって、一定の基準以上の工事を請け負う場合は、建設業の許可を受けなければいけません。一定の基準とは「軽微な建設工事のみを請け負う業者以外は、建設業許可を受けなければならない」ということです。逆に言うと1件でも軽微な工事以外の工事を行う場合は、建設業の許可が必要になります。
許可なしで工事を行った場合は無許可営業として法律で罰せられることとなります。では軽微な工事とはどのようなものでしょうか。軽微な工事とは、
①建築一式工事では1,500万円未満の工事または、延べ面積150㎡未満の木造住宅工事
②建築一式工事以外の工事では、500万円未満の工事、となります。
許可を受ける必要がある業者は、発注者から直接工事を請け負う元請負人はもちろん、下請負の場合も含みます。これは個人であっても法人であっても同様です。また注意点としては、
①上記の金額には消費税等の税金も含まれること
②全体の工事を期間等で2つ以上の契約に分割して請け負う時は、その合計額で計算すること
③材料が注文者等から支給された場合は、その材料費(市場価格で計算し、運搬費等も含みます)も含まれることです。
うっかりして軽微な工事の範疇を超えないようにしましょう。
以前元請業者のコンプライアンス遵守について書きましたが、昨今下請けの無許可業者に500万円以上の工事を施工させていたとの内容で、元請業者に行政指導がなされるケースが増えているようです。うっかりの場合もあるでしょうが、元請業者にとってはそのうっかりで社名に傷が付く場合もあります。ですので、建設業許可を取得している建設業者を優先的に指名するケースが増えていくものと思われます。
なお一式工事という名称に触れましたが、建設業の許可については、次の29業種があります。請け負う工事の業種ごとに許可が必要であり、許可を取得している業種の工事以外原則行えません。許可以外の業種の工事を行う場合は、許可を受けている建設業者と下請け契約を結ぶことになります。
一式業種として2業種あります。一式工事とは複数の下請企業を元請企業が統括して行われる大規模な工事のことであり、その全体のマネジメントを行う許可が一式業種許可です。①土木工事業 ②建築工事業です。
専門業種として27業種あります。①大工工事業 ②タイル・レンガ・ブロック工事業 ③ガラス工事業 ④造園工事業 ⑤左官工事業 ⑥鋼構造物工事業 ⑦防水工事業 ⑧さく井工事業 ⑨とび・土木工事業 ⑩鉄筋工事業 ⑪内装仕上工事業 ⑫建具工事業 ⑬石工事業 ⑭舗装工事業 ⑮機械器具設置工事業 ⑯水道施設工事業 ⑰屋根工事業 ⑱しゅんせつ工事業 ⑲熱絶縁工事業 ⑳消防施設工事業 ㉑電気工事業 ㉒板金工事業 ㉓電気通信工事業 ㉔清掃施設工事業 ㉕管工事業 ㉖塗装工事業 ㉗解体工事業です。
別の記事で書きますが、許可にも業種別の他、一般建設業と特定建設業の区分もあります。それぞれの業種では一般か特定のどちらかの許可を受けることとなり、同じ業種で一般と特定の両方の許可を受けることはできません。なお解体工事業許可における、とび土木工事の経過措置に関しては前に投稿した記事のとおりです。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry4.html
READ MORE

私の勉強ノートを見つけましたので、これからこれをもとにブログを書いていきます。
最初に士業を志したのは17年前。当時も漠然とした思いではあったのですが、40歳を目前にして、会社を辞めて自分で士業をやりたいという思いが強くなり、急に勉強を始めました。その時に選んだものは中小企業診断士でした。まあ会社にいても資格が邪魔になることはないし、自分のスキルやノウハウを活かせると思ったからです。
当時も会社に特に不満もなく給料も良かったのですが、とにかく無性に自分の力を試したかったんでしょうね。家でも会社でも、半ば公然とその思いは伝えていました。
年齢も年齢ですので決して若気の至というわけではないのですが、結果としては明らかに当時は進まなくて正解だったんでしょう。その頃小中学生だった4人の子供も大学を終え、無事に社会人として生活(上3人の娘は結婚し、独身は社会人2年目の男の子だけですが)していますし、それもこれも勤めていた会社のおかげでした。
当時は単身赴任ではなく、転勤してきた群馬の借家住まいでしたが、とにかく忙しい時期でした。会社もみなし労働を導入し、その中でも今話題の企画業務型裁量労働営業として土日以外はカウントしなくても残業は100時間を優に超えていましたし、そんな環境で酒も控えて帰って勉強をしていた時期でした。
中小企業診断士の試験も方式が変わったばかりでまだ1次試験も今ほど難しくはなかったんでしょうが、思いもかけず1回で合格してしまいました。ただそこまでで、結局仕事が忙しいのやら楽しいのやらで、結局2次試験は受けずじまいでした。そこから10数年が経って子供たちも巣立ち、そろそろ次もということで会社も辞め行政書士としての今に至ります。
思い立って再度試験勉強を始めたのは4年ほど前の8月ですが、もう診断士の試験は間に合いませんでしたので、何か資格試験はないかなということで行政書士の勉強を始めた次第です。今考えるとあまりに無謀ですが、せっかくやりだした勉強でしたので2つの勉強を並行して行っていました。
翌年の診断士は1次はクリアしましたが、一発合格を狙った2次の最後の財務でつまずきました。横の受験者が問題用紙のページを切り取って見やすくしていた?(問題用紙を見られた方ならわかると思いますが)のが見えましたので、3科目まで出来のよかった私も調子に乗って切り取ったのが運の尽き、逆にページのやりくりがうまくできなくなりパニックになってアウトでした。その時のことは今もよく覚えていません。結果はBで落第。3科目までAで、4科目目だけDで足切り。悔やまれてなりません。
2年目の2次は財務さえやれば大丈夫だろうということと、この試験特有の訳のわからなさ(これもわかる方にはわかると思いますが)から他の科目の勉強はあまり意味がないと考え、ほとんどやらずに受験し落第してしまいました。
昨年は再度1次試験を受けましたが、平均点も68点超えでクリアしました。でも行政書士に受かっていましたし、2次も問題ないだろうとタカをくくって勉強もやらず散々な結果に終わりました。今も試験の復習はしていませんが、かなり大きな事故をしでかしたんでしょう。今年の2次はモチベーションを上げないとむつかしいかな。そろそろ過去問引っ張り出してみようかな。。
診断士試験を目標にされる方は、1年目で受かる決意で臨んで下さい。そもそも一度に2つの勉強はしない方がよいです。覚えるのがむつかしいというよりも、両方のモチベーションを維持するのは無理です。
ということで行政書士試験の話に戻りますが、当然1年目は記念受験でしたが、難易度が非常に高い(というか問題の質自体が議論されるほどのレベル)年でしたので当然落ち、翌年はその影響で問題が易しくなったにもかかわらずモチベーションが低くて落ち(診断士に受かると思っていましたので)、その翌年になんとか受かった次第です。
診断士の試験は科目が多く門外漢な分野も多いのでLECの通信教育で勉強しましたが、行政書士の方はまったくの独学でした。使用したのは書店で売っているLECの合格基本書と同じく過去問だけです。
最初は何回も見てひたすら覚えるだけで、他の手段は使いませんでした。2年目はさすがに飽きたので、法律の解釈本も買いましたが、こちらは記憶するというよりも解釈の幅を広げるのに役立ちます。
人によっても違うんでしょうが、一番良かったのは自分でノートを作ることでした。他の人の文章を何回も見ていると、自分が間違って解釈していた場合もそのまま通り過ぎてしまい記憶の訂正がされないので、咀嚼したものを自分の言葉でまとめるのが一番よいです。
簡潔に見やすくまとめようとすると、必然的により正確に解釈することが必要になるからです。それと本だけに頼ると、直前に限られた時間で内容を再確認しようとした際に、丁寧に読み込むと時間がかかり内容を飛ばし読みしてしまいがちだからです。自分のノートなら、短時間で何回も重要点を確認することができるからです。
ということで作成したノートにネタがたくさんありますので、診断士の科目も含め、これからブログに書いていきます。
よく行政書士試験の難易度はどのくらいという話がありますが、これは人によって受け取り方が違うと思います。暗記科目だし、受かるまで受験できると考えれば、そこまでむつかしい試験ではありません。ただ暗記科目だからといっても、試験問題は解釈のむつかしい文章形式で出されますので、条文などの本当の理解が重要になってきます。私も何回も見直して初めて正しい理解に至ったものが数多くあります。
行政書士試験は60%をクリアすれば良いとはいっても、たかだか60点というものではありません。残りの40%近くは出来ないようなむつかしい問題や、明らかに試験問題としてはくだらない問題もありますので、うまくできてやっと60点にたどり着く試験といってもよいと思います。選択問題の多くのは4択か5択になるでしょうが、大体は2つまでは絞り込めます。ただその2択になってしまった時点で、かなりやっかいな状況であることは否めませんね。
行政書士試験が簡単かどうかは見方が別れますが、ざっくりと偏差値で62程度かなというイメージです。診断士試験は科目が多く、経済学や情報システムなどもこなさなくてはいけないので時間はかかりますが、それでも行政書士試験のようなひねくれたイメージはありませんでしたのでやりやすいです。
行政書士試験が落とすための試験という意味であるならば、結構むつかしいと思います。重箱の隅をつつくような問題や、本当にどうでもよい問題もありますので。最初の憲法の文章など、長くて時間ばかりかかります。ここの時間配分をやりくりしないと、やりやすい後半の問題も慌てることになります。ちなみに私は憲法を解いた後に、先に最後の一般も問題を解きました。
たまたま1回や2回で受かれば、結果として簡単だったと言えるんでしょう。簡単だと言われる方のパターンはそういうことだと思います。受かったから簡単。でも受かった方でも次の年の問題を解けば確率は5分5分だと思います。難易度は年によりますし(落とす問題がどの程度仕込まれているか)、200時間の勉強でもたまたまその年の問題がハマれば受かり、1000時間の勉強でもハマらなかったら落ちる。1年に1度の試験がこのような内容でよいのかとは思いますが、実際そのようなイメージの試験でした。とはいえ、きっちり勉強すれば、それほどむつかしい試験ではないですかね。
行政書士試験の勉強は独学で十分こなせると思いますし、模擬試験は必要ありません。ただ独学でする場合には、条文の解釈を正しく行う必要があります。出来れば違う参考書を併せて読むほうが良いと思います。
あとひとつ、記述式の問題集や予想問題は購入したほうが間違いなくよいです。私はLECのものを買いましたが、全体で60問あったと思います。条文の理解にも役立ちますし、その年出題されなくても、間違いなくいつかは出るであろう問題です。受かるまで使えます。私もこれがなかったら受かっていなかったかもしれません。ながなが書きましたが、最後のこれを言いたかったんです。
READ MORE
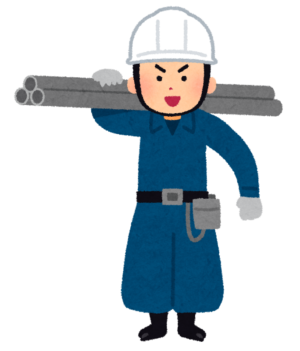
週末の暑さとは打って変わって、昨日今日は雨模様で少し肌寒い天気ですね。でもあさってからGW前半にかけては暑いくらいの好天が続くようですね。GW後半の天気が少し気がかりですが、今年は日の並びも良いし、景気には良い影響を与えるでしょう。
私もメーカーに努めていた頃はここが前半最大の山場であり、仕掛けていた企画の成果が気になるところでした。新人行政書士として迎えた今年は、のんびり旅行を楽しむ余裕がありますが、来年からは遊ぶ暇もないことを期待しています。
今日は建設業許可の種類について書いてみます。
まず営業所の所在地によって申請先が異なる、知事許可と国土交通大臣許可の2種類があります。
知事許可とは、1つの都道府県でのみ建設業法に基づく営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は都道府県知事が行い、申請先は各都道府県知事となります。
国交大臣許可とは、2つ以上の都道府県にまたがって営業所を設ける場合の許可となります。この場合の許可は国土交通大臣が行い、申請先は主たる営業所を管轄する地方整備局等になります。実務的には知事許可と同様に都道府県の窓口に申請することになります(手数料の収め方や受付日等が異なる場合があります)。
知事許可と大臣許可の違いは、契約を行える営業所が他県にも置かれているかどうかだけの問題であり、基本的には許可内容にそのほかの違いはありません。
また同一業者が知事許可と大臣許可の両方を受けることはありません。どちらか一方の許可だけです。知事許可を取得していても他県に営業所を開設した場合は大臣許可に変更をし、大臣許可の場合であっても一つの県以外の営業所を閉鎖した場合は、残った県の知事許可に変更します。
なおこの2つの許可区分はあくまでも営業所の所在地に基づくものであって、施行する工事現場はどこでも構いません。知事許可を受けた者が他県で工事を施行することにはまったく問題ありません。
申請先による区分のほか、下請に出す工事金額の総額によっても2つの許可に区分されます。ひとつは一般建設業許可であり、もうひとつは特定建設業許可です。
まず一般建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。
①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円未満の工事のみを行う建設業者
②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円未満の工事のみを行う建設業者
では特定建設業許可とはどのようなものでしょうか。次のいずれかが該当します。
①発注者から直接受注した工事について、下請に出す工事金額が4000万円以上の工事を行う建設業者
②建築一式工事においては、下請に出す工事金額が6000万円以上の工事を行う建設業者
ひとつの業種については一般建設業許可と特定建設業許可の両方は取得できず、業種ごとにどちらか一方のみの許可となります。金額についてはいずれも消費税等込の金額です。
なお注意しなければいけない点は、この一般建設業か特定建設業かの区分については直接請負う金額に制限はなく、あくまでも下請けに発注する金額によって決まるという点です。大規模な工事を請負ってもそのほとんどを自社施工で行い、下請けへの発注金額が4000万円に満たなければ、一般建設業の許可でも大丈夫ということになります。
ただしひとつでも特定に該当する工事を請け負う場合は、やはり特定建設業許可が必要であることは言うまでもありません。
なお別記事でも書きますが、特定建設業許可は一般建設業許可と比べてその責任範囲が増すため、取得要件も厳しくなり技術者の要件や財務要件のハードルが高くなります。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry6.html
READ MORE

今日は建設業許可の新規取得について書いていきます。
新規取得とは文字通り新たに許可を取得することですが、これにはいくつかのパターンがあります。
①新規取得
②許可換え新規
③般・特新規
④業種追加
です。
以上4つについてもう少し詳しく見ていきましょう。
まず建設業許可の新規取得とはどのようなものでしょうか。第一義的には今まで建設業許可を取得していなかった建設業者が許可を取得する場合です。軽微な工事のみを行っていた建設業者が、軽微な工事の範囲を超える工事を請け負うようになった場合や、元請業者の要請を受けて取得する場合があります。
一方、「廃業届」を提出した建設業者が再度建設業許可を申請する場合もあります。以前に許可を有していた者が許可取得後に要件の一部でも欠いた場合は、廃業届を提出して廃業することとなります。
例えばひとつの営業所のみで建設業許可を取得していた建設業者で専任技術者がひとりしかいなかった場合に、その専任技術者が退社してしまい2週間以内に常勤の後任が採用できなかったときなどは、やむをえず「廃業届け」を提出して廃業しなければなりません。
しかしこのケースにおける廃業は法的罰などによる廃業とは異なるため、要件を欠いた要因が解決すれば、すぐにでも再度の許可申請をすることができます。再度許可を取得するために申請する場合もこの「新規」に該当します。
「許可換え新規」とはどのようなものでしょうか。許可換え新規とは次の場合をいいます。
①複数の県で営業所を設けている建設業者が、他の県の営業所をすべて閉鎖し、ひとつの都道府県の区域内のみに営業所を設けることとなったときです。この場合は残った営業所のある都道府県に知事許可の申請を行います。国交大臣許可が失効し知事許可となることです。
②都道府県知事の許可を受けた者がその都道府県の営業所をすべて廃止して、別のひとつの都道府県に営業所を設置することとなったときです。この場合は新たな営業所のある都道府県に申請を行います。許可は知事許可で変わりませんが、従前の県での知事許可が失効し、新たな県で知事許可を申請することになります。
③都道府県知事の許可を受けた者が、別の都道府県にも営業所を有することとなったときです。この場合は国交大臣の許可申請をすることとなります。知事許可と大臣許可を両方受けることはありませんので、これらの場合は従前の知事許可は失効することになります。
「般・特新規」とはどのようなものでしょうか。般・特新規とは次の場合をいいます。
①一般建設業許可を、同じ業種の特定建設業許可に変えて許可申請することをいいます。逆に特定建設業許可を一般建設業許可に変えて申請する場合も同様です。一般許可と特定許可の両方は持てませんので、特定建設業の許可が下りた場合は一般建設業の許可は失効します。逆も同様です
②複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その一部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、あらかじめその業種の特定建設業許可について廃業届を提出してからあらためて般・特新規の申請をしなければなりません
③複数の業種について特定建設業のみの許可を受けている建設業者が、その全部の業種について特定の要件を満たせなくなった場合は、あらかじめその全部の業種の特定建設業許可について廃業届を提出してから、あらためてすべての業種の一般建設業の申請をしなければなりません。この場合の申請は般・特新規とはならず、通常の新規許可申請となります
般・特新規申請の場合では元の許可番号は変更とはならずそのまま引き継がれることとなります。
最後に「業種追加」についてですが、業種を追加される場合も新規建設業許可申請が必要になります。当然この際には申請手数料や、行政書士への報酬が発生します。新規申請される際には、一般業種と特定業種を同時に申請される場合は二つの申請が必要になります。
しかし同じ一般業種(特定業種)内なら、一度に何業種でも申請することができ、手数料や報酬も1回分のみとなります。ですので、新規申請の際に既に複数業種申請の目処が立っているようでしたら、費用面からはまとめて申請されることをお勧めいたします。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry2.html
READ MORE

今日は建設業者が公共工事を直接受注することの要件について書いていきます。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry42.html
公共工事とは国の各省庁や都道府県市町村といった地方公共団体、あるいは独立行政法人等も含めた、いわゆる官公庁が発注する工事のことをいいます。
税金で賄われる工事であり公共性が問われるものですので、その運用は建設業法によって厳しく規制されています。また各官公庁ともより良い行政を目指し、発注を行うに当たっては、客観的な評価に基づいた適正な建設業者を、適正な発注価格で契約するという「入札制度」で運用しています。
一方地方公共団体においては地域活性化の一環として、地元業者との契約や育成を行うといった一面も備えています。
ではまず建設業者が公共工事を受注するメリットについて考えてみましょう。
請け負うメリットとしては多くのものが挙げられますが、まず第一には当然、売上の増加が見込まれることです。特に公共工事はインフラの整備や維持も継続して行う必要があるため、不況期でも安定した発注量が見込めるという大きなメリットがあります。
また請求先は官公庁ですので、現金回収ができしかも取りっぱぐれはありません。Aランクの取引先です。情報収集や営業努力については民間に対してするものと比べても力の抜けるものではありませんが、少なくとも交際費等の出費はかかりません。
信用力という点からも、公共工事の請負が多いほど当然企業としての信用が高くなっていきます。優良債権がきちんと回収できていることが一目瞭然であり、官公庁から財政面も技術面もお墨付きをもらえる効果があるからです。銀行などの金融機関からの信用が厚くなることはもちろん、民間企業からの受注増にもつながるものです。
もうひとつ期待できる効果としては、前述した地元企業が優先されることが多いことと、小規模企業にも地域活性化の点から枠が設けられていることです。まずは限られた規模やランクの工事にはなりますが、そのレベルの公共工事を請け負うことで、次のステップにつなげていける可能性があります。
では公共工事は誰でもが受注できるのでしょうか。
公共工事を受注するのには、官公庁があらかじめ公表する工事の「入札」に参加しなければなりません。入札自体の話はおくとして、ここでは入札参加の要件について見てみます。
まず前提条件としては、建設業許可業者でなければなりません。軽微な工事のみを行う建設業者であっても建設業許可を取得すれば、入札に参加する第一の要件はクリアできます。
次の要件は毎年必ず決算変更届けを提出していることです。建設業許可業者としての義務ですので当然ですが、変更届けを提出していれば次のステップに進むことができます。
ここまでは形式要件であり、受けようとする建設業者は当然クリアしています。ここから各建設業者に備わっている技術力や経営力、資力等によって客観的な点数化が行われ、ランク付けされていく過程に進みます。
その過程が「経営事項審査」(けいしん)というものになります。経営事項審査を経て獲得した点数やランクに基づいて、各省庁の入札採用につながっていきます。経営事項審査は経営状況と経営規模という2つの客観的な審査が行われ、最終的に点数化された「総合評定値通知書」というものが交付されることになります。次回はそれぞれの分析について見ていきます。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry42.html
READ MORE

前回の記事で中小企業について触れましたので、今日は「中小企業」「小規模企業」について書いていきます。
行政書士のお客様は、中小企業や小規模企業、あるいは個人事業主がほとんどとなります。かく言う私も個人事業主でありますが、ではそもそも中小企業とはどういうものであって、現状はどのような状況でしょうか。
ちなみに「中小企業基本法」では中小企業を「多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人がその能力を発揮しつつ事業を提供することによりわが国経済の基盤を形成しているもの」と位置づけています。
また「中小企業憲章」では中小企業は「意思決定の素早さや行動力、個性豊かな得意分野などの多種多様な可能性を持つ。経営者は企業家精神に溢れ、自らの才覚で事業を営みながら、家族のみならず従業員を守る責任を果たす」といい、また「社会の主役として地域社会と住民生活に貢献し、伝統技能や文化の承継に重要な機能を果たす。中小企業は国家の財産ともいうべき存在である」とも謳っています。
ここでは数字面的なものだけ書いておきます(以下2014年統計から)。
その前に中小企業の定義とはどのようなものでしょうか。「中小企業」の定義は「中小企業基本法」によります。中小企業は資本金または従業員数に基づき区分されます。
①製造業・建設業・運輸業等では資本金3億円以下または従業員数300人以下
②卸売業では資本金1億円以下または従業員数100人以下
③小売業・飲食店等では資本金5千万円以下または従業員数50人以下
④サービス業では資本金5千万円以下または従業員数100人以下
どの業種も資本金か従業員数のいずれか一方に該当すれば中小企業となります。
ちなみに「小規模企業」とは、常時使用する従業員の数が20人以下(卸業・小売業・飲食店・サービス業は5人以下)の事業者と定義され、こちらは従業員数のみで判断されます。
また中小企業は法人税等でも優遇されますが、この場合の中小企業の定義は法人税法における中小企業の定義が適用され、業種にかかわらず「資本金1億円以下」の企業となります。
会社は大きいことによるメリットも当然ありますが、大きいゆえに様々な義務も厳しくなります。ですのでこの括りは重要となり、中小企業であるメリットも非常に大きいこととなります。いつぞやシャープが自主再生の過程で、資本金をこの基準にまで下げることを検討し、批判の的となったことも記憶に新しいことです。
企業ベースでは中小企業の割合は全企業(一次産業は除きます)の99.7%を占め、小規模企業は85.1%を占めます。建設業は特に顕著であり、中小が99.9%、小規模が95.5%となります。
小売業ではそれぞれ99.6%、82.1%、宿泊飲食業では99.9%、85.3%となります。では従業者数ではどうでしょうか。同じく全企業で70.1%、23.5%、建設業89.2%、58.8%、小売業62.9%、19.4%、宿泊飲食業73.4%、26.9%となります。
まとめますと、大企業は全企業数の0.3%ですが従業員数は29.1%を占めます。企業数はほとんどありませんが、従業者数で見ると一次産業を除く3割の方が大企業で働いており、個人事業主を含む中小企業で働いている方は、のこりの7割の方ということになります。
ここも建設業が突出して顕著な数字となっていますが、中小企業で働いている方が9割であり、6割の方は小規模企業で働いているということになります。これはとりもなおさず、土木工事や電気工事等が様々な専門性をもちそれを元請がまとめるという、建設業界特有の構造によるものでしょう。
中小企業については興味深い記事もいろいろ書けますので、折に触れて投稿していきます。
READ MORE

そろそろビールが一段とおいしい季節になってきました。今週は暑さも一息ですが、そろそろビアガーデンもオープンしてきましたね。
以前は飲み会でも「とりあえずビール」が定番でしたが、10年ほど前からお酒の嗜好の多様化が進んだりあるいは若者の酒離れが進んだりして、ビール離れが進んできました。1杯目からまずはビールではなく、チューハイやハイボールやらが花ざかりです。
お酒をあまり飲まない方は、ビールの苦味(くみ)が苦手なんでしょう。先週サントリーさんの特定のウイスキー原酒が底をついたというニュースがありましたが、隔世の感があります。ジャパニーズウイスキーの原酒がなくなるなんて。
ウイスキー需要は2000年代後半までずっと継続して右肩下がりでしたので、貯蔵樽も多くあったようです。もちろん熟成には年数がかかりますが、工場の規模から言えば仕込むスペースなどしれているでしょうし、具体的な数字はわかりませんが、それだけ高額品の伸びるペースが予想外だったということでしょうか。
サントリーさんがハイボールに火をつけたのを皮切りに、ここにきて一層チューハイも度数が7-9%のものが多く発売されてきました。ひと頃は女性をターゲットにした3%ものが人気を博しましたが、完全にシフトチェンジした感があります。
業界ではチューハイ類を称して「低アル」カテゴリーと区分していましたが、これでは「高アル」と呼んだ方がふさわしいくらい。当方も飲み過ぎの感があるので、ノンカロリーで甘くないアル度の低いものを探しているんですが、これがないんですよ。
ウイスキーは一過性のブームではなく、今までは飲まず嫌いで飲んでいなかった、新しいお酒が加わったと認知されているのではないでしょうか。以前はオヤジの酒などと揶揄されて、あるいは度数の高いイメージから、最初から選択肢として加わっていなかったんですが。
ウイスキーはいわゆる甲焼酎同様、割ってしまえば強い癖もなくカロリーも低い。おまけに蒸留酒はビールやワインのような醸造酒とちがって、悪酔いしません。それに定番のジャパニーズウイスキーはスコッチやバーボンと違ってとにかく飲みやすい。角瓶などその最たるもので、ストレートで飲んでも飲みすぎてしまいます。裏を返せば個性がないというか。ひと頃はストレートでばかり飲んでいましたが、角瓶は飲みすぎてしまい非常に危険でした。
ストレートで喉の焼け付く感を味わうには、バーボンがおすすめです。バーボンはジャックダニエルやターキーが特に好きです。フォアロゼも粗野でチープな味わいが良いと思います。昔はヘンリーマッケンナが好きでした。
私もハイボールを飲みだしてから、ビールの苦味(くみ)が苦手になりました。昔はビールしか飲まなかったんですが。お酒をよく飲む男性にとっては、度数の低いお酒は「損した感」がありましたが、今は「得した感」ってやつですか。ただでさえ苦しいビールメーカーにとっては、痛し痒しの状況ですね。
お酒の中で一番おいしいと思うものはコニャックです。いまではあまり飲みませんが。あとダークラムとシェリーですね。って、どれも糖分が多くて今は自主規制です。バブルの頃は高価なワインも普通に売れていましたので、扱っていたシャトーワインの社内試飲会も行っていました。これも普通にシャトーマルゴーやロートシルトなどのビンテージもみんなで比較していました。味は忘れないもので、良い経験になっています。
もう時効ですが、この頃の課の旅行では地場の永田屋さんという酒卸さんからしこたまワインを買い付けて旅先で飲み明かしたこともありました。目玉はロマネコンティとラターシュでしたが、ビンテージは忘れましたが、ロマネが15万円、ラターシュが4万円でした。もちろん他のシャトーワインも色とりどりで。でも真打が登場する頃にはみんなベロベロで、価値などわかったものではありませんでした。
READ MORE

群馬県高崎市在住の行政書士の鈴木と申します。本日からブログをスタートしました。
建設業許可や農地転用を中心とした手間のかかる許認可申請のことや、遺言書作成や相続問題といった身近なことでお悩みの方も多いと思います。解決の一助にでもなればと考え、ブログでの掲載も始めることとしました。
できる限り毎日アップできればと考えていますが、チリも積もればなんとやらで、お力になれる話題もそのうち出てくるかなと思います。
お仕事でお悩みの方も多いと思いますので、今まで会社人として身につけた知識やスキルも、話のネタとして散りばめていければと考えています。また趣味のことについても話のまくらとして、脱線しない程度に書いていこうかなと思います。
また、記事については建設業許可や遺言相続、農地転用というものを主体にと考えていますが、毎日各カテゴリーをランダムに書いていきますので、体系的に記載した、当ホームページのリンクも貼っておきます。
ちなみに趣味は競馬と番組収集です。キャンディーズ解散コンサートの録画に始まってビデオテープに番組を収集してきましたが、悲しいかな録画メディアが変わるたびに意味がなくなるんですね。特にアナログの場合は年数が経過すると転写とかで劣化してしまいますし。音楽もレコード収集に始まりカセットへの録音収集と、こちらも1000本以上集めましたが。
ちなみに番組収集は現在進行形ですが、ブルーレイにBSやCSから録画したものをDVDにダビングして保存しています。現在で800枚、4000番組以上あります。面白いネタがあれば触れていきます。今日は初日ですので、明日から行政のことやいろいろな話を書いていきます。
一番好きな曲です。アコーディオンのノスタルジックな響き。BillyJoelのViennaも同じく大好きです。81年の武道館。桜も散り際で。。この年はすぐ斜め後ろで見てました。PianoManは後ろからも見られます。
数年前赴任していた富山市の松川の桜です。単身赴任の会社への行き帰り、いつも眺めていました。夜のライトアップもとてもきれいで、休日には船頭と観光客を乗せた船が行き来していました。
READ MORE
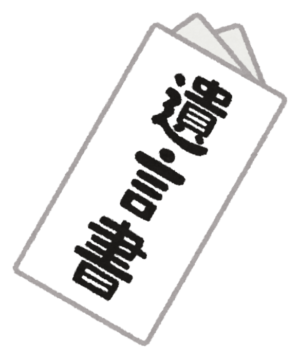
今日は経営事項審査の次の段階、経営規模等評価について書いていきます。
経営状況の分析が終わると、申請した機関から「経営状況分析結果通知書」が届きます。今度はそれをもとに、許可行政庁に「経営規模等評価申請」とその結果を交付してもらう「総合評定値請求」を行ないます。
申請では「経営状況分析結果通知書」をあわせて提出します。申請する行政庁は、知事許可であればその都道府県知事へ、大臣許可であれば管轄する地方整備局になります。大臣許可の場合も実際に提出する窓口は、通常は知事許可と同様になります(提出日を指定されることが多いようです)。事前に予約をしてから申請を行ないます。
経営状況分析では主に財務面等の経営の健全性について評価を出しましたので、経営規模等評価では、建設業としての営業規模や技術力、人材、設備、あるいは建設業者としての社会性等について評価を受けることになります。ではどのような項目で評価されるのでしょうか。評価項目は、
①完成工事高(XⅠと記号化されます)
②自己資本額および平均利益額(XⅡ)
③技術職員数および元請完成工事高(Z)
④その他の審査項目(W)の4つになります。
その4つの項目を足して、総合評定値(P点といいます)が求められます。このP点がその建設業者の最終評価(実際は入札を行いたい官公庁に申請すると、総合評定値をもとに各官公庁独自にランク付けされますが)になります。
各項目にはそれぞれ決められた部分点数があり、それらを足しこんでその項目の合計点とします。各項目の詳細は次回に説明しますが、規模が大きければどこまでも点数が加算されるかというとそういうわけではなく、それぞれに上限値と下限値が設けられています。
また項目ごとに比重に差を付けており、各項目の合計点にXⅠが0.25、XⅡが0.15、Zが0.25、Wが0.15を掛けて求めることになります。P点を全体1とした場合、この4項目を足しても0.8にしかなりません。
あと0.2は何かというと、これが前段の経営状況分析(Y)の点数になります。これを式で表すと、P=XⅠ×0.25+XⅡ×0.15+Z×0.25+W×0.15+Y×0.25となります。
ちなみに参考に各項目の上限点数だけ記しておきます。XⅠが2309点、XⅡが2280点、Zが2441点、Wが1919点、Yが1595点です。ですので総合評値P点の最高値は2136点となります。
総合評定値は業種ごとに出されますので、経営状況分析同様、経営規模等評価も業種ごとに申請します。各項目の内容については、次回書いていきます。
https://www.gyosei-suzuki-office.com/category1/entry83.html
READ MORE

この土曜日に前橋の赤木千本桜を見に行ってきました。初めて行きましたが、あいにくの曇り空。週中の天気予報では雨でしたが朝から雨が降る気配もなく、今日から桜まつりということで8時に家を出ました。
今年は3月が異常に暑かったこともあって桜も散り頃で、ここも朝からすごい桜吹雪。こんなにすごい桜吹雪の回廊を通ったのは初めてで、ほんとにびっくりしました。♫桜舞い散るではなく、桜降りしきるでした。写真ではなく、動画を撮ればよかった。
3月の高い気温も、地球温暖化の影響でしょうか。温暖化といえば、先週CSで「空の大怪獣ラドン」という東宝の特撮映画を見ましたが、その中で技師のおじさんが「最近は地球温暖化で暑くて困る」と言っていました。1956年の映画ですよ。笑ってしまいました。
さて、今日は建設業許可の中の経営事項審査の改正についてお話します。建設業として公共事業を元請として受注する際にはその工事業種の経営事項審査(経審)を受けていることが前提となりますが、この平成30年4月1日から経営事項審査の審査項目及び基準が改正されました。今後の審査基準は新基準となります。
申請様式に変更はありませんが、評価点について4つほど変更がありました。具体的には、
①社会保険未加入業者への評価について
②防災活動への貢献の状況の評価について
③建設機械の保有状況の評価について
④評価対象となる建設機械の範囲の拡大の変更です。
特に国交省が建設業許可業者に対して取り組んできた、社会保険等未加入対策についての目標期限も迫っていることもあり、社会保険等未加入業者への評価が厳しくなりました。
一方、国や地方公共団体等に対する建設業許可業者の防災活動への貢献による加点が大きくなりました。
また建設業に使用する建設機械の保有台数による加点も大きくなりました。保有台数が少ないほど、改正前との比較では加点幅が大きくなったということです。
建設業許可業種の公共事業の元請け受注をされる方は、改正のメリット、デメリットを押さえることも必要になるかと思います。
http://gyosei-suzuki-office.com/category1/entry43.html
READ MORE
建設業許可の新規取得、許可換え新規、般・特新規について